【注意】夏休み明けの不登校・行きしぶりが増える理由と親がすべき対応5選
- 2025/08/28
- 2025/08/29
夏休みが明けると、学校に行きたがらない子どもが急増します。実際、夏休み明けは全国的に「登校しぶり」や「不登校」が増えやすい時期です。
「うちの子だけ…?」「甘やかしすぎたのかな…?」と感じる保護者の方へ。
この記事では、なぜ夏休み明けに子どもが不安定になるのかを解説しつつ、家庭教育の視点から子どもを支えるために、今すぐできる5つの具体策をご紹介します。
一人で抱え込まず、お子さんと一緒に乗り越えていきましょう。
なぜ夏休み明けは不安定になりやすいのか?
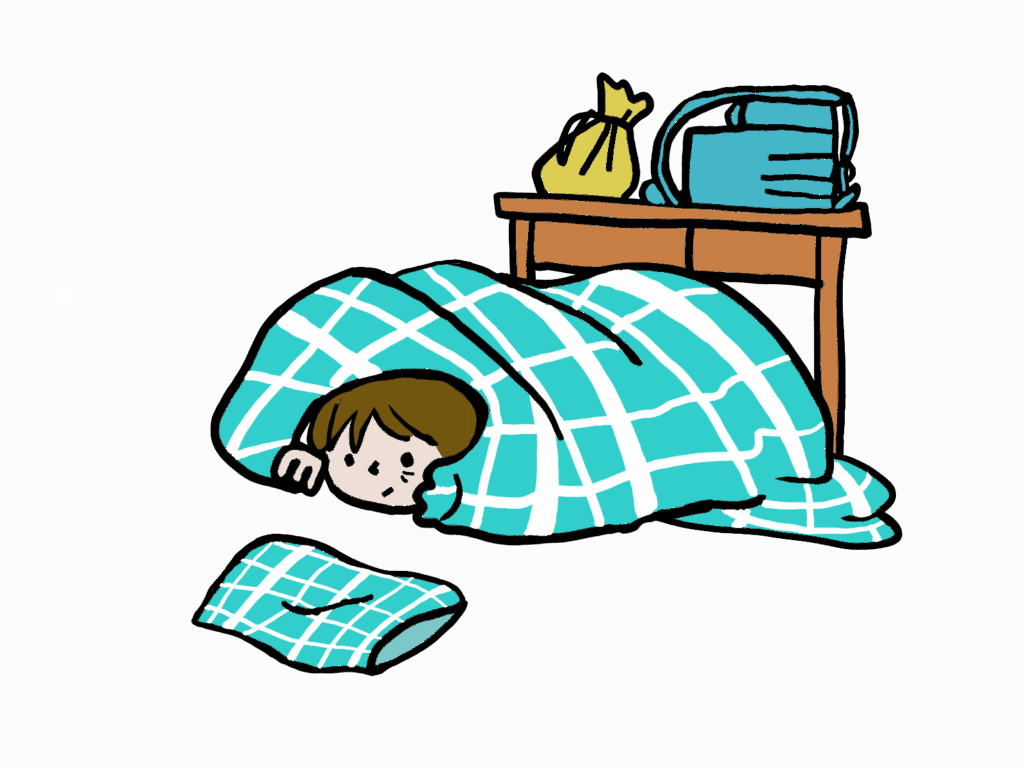
📌 理由①:生活リズムの乱れ
夏休み中の自由な生活から、急に規則正しい学校生活に戻ることは、子どもにとって想像以上に大きな負担です。
夜更かしや遅起きが習慣化していると、体内時計がズレてしまいます。その結果、朝のスイッチが入らず、登校準備にエネルギーが出ません。「起きられない」「だるい」といった身体的な不調が、心の不安定さにもつながってしまうのです。
📌 理由②:心身の疲労が蓄積している
「夏休み中は遊んでいたから元気なはず」と思われがちですが、これは大きな誤解です。
実は、普段とは違う環境や活動に適応することで、子どもは知らず知らずのうちに心身にストレスを溜め込んでいます。旅行や帰省、習い事や部活動、友人との遊びなど、楽しい活動であっても、脳や体は常に刺激を受け続けています。
この疲れが”遅れて出てくる”ことがあり、夏休み明けになって急に体調を崩したり、情緒が不安定になったりするのです。
📌 理由③:学校への不安が再燃する
長期間学校から離れていると、勉強の遅れ、提出物の心配、クラスメイトとの人間関係など、様々な不安が頭をよぎります。
「また始まるのか」「みんなについていけるかな」「夏休みの宿題、大丈夫だったかな」といった心配が積み重なり、学校という場所そのものに対する不安が強くなってしまいます。
特に、夏休み前に何らかの困りごとや嫌な体験があった子どもにとって、学校は「また同じことが起きるかもしれない場所」として認識されてしまうことがあります。
親が今すぐできる5つのこと
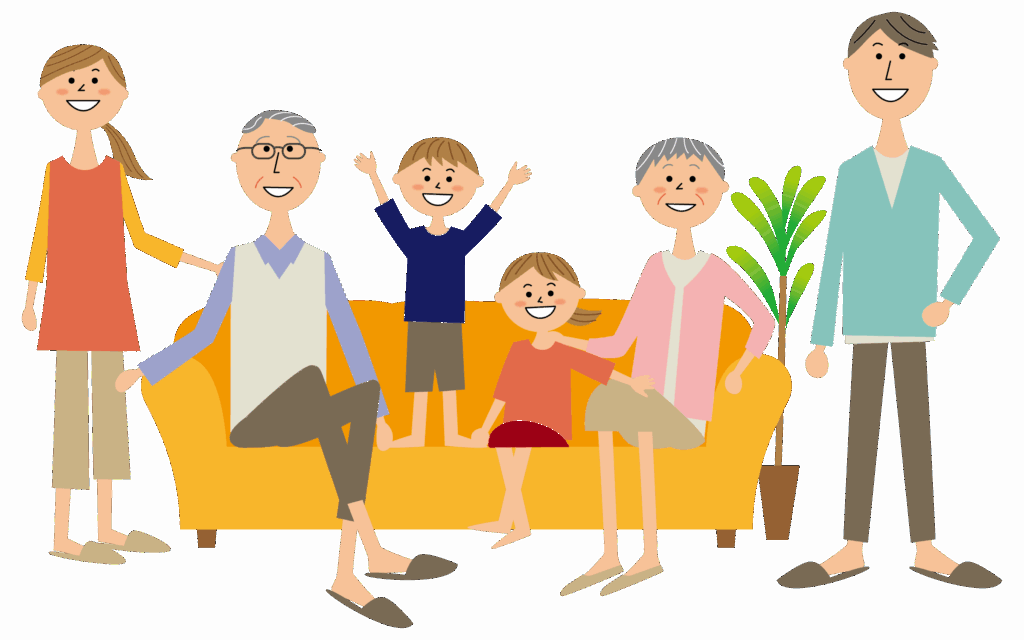
ここからは、家庭教育と非認知能力の育成という視点から、お子さんを支えるための具体的な方法をご紹介します。
✅ 1. 子どもの”考える力”を育てる:選択と内省の場をつくる
子:「今日は学校ムリ…」
親:「そっか。何が無理なの?」
お子さんが「学校に行きたくない」と言ったとき、まずは理由を問い詰めるのではなく、子ども自身が自分の気持ちと向き合えるように声をかけてみましょう。
「どんな気持ちかな?」「何が心配なの?」といった質問を通して、自分の感情や状況を言語化する練習をサポートします。親が先回りして判断するのではなく、子どもが自分で「選ぶ」経験を重ねることが大切です。
この積み重ねが、自己決定力・自己理解の育成につながり、将来的に自分で困難を乗り越える力となります。
✅ 2. 必要以上に干渉せず、子どもに考える時間を与える
親:「早く起きなさい!」「急がないと!」「今日も行かないつもり?」
子:「もう、うるさいって!もう学校行く気なくなった。」
お子さんを心配する親心から必要以上に干渉してしまうことはありますが、親の干渉が原因で子どもが「学校に行きたくない」となってしまうこともよくあるのです。
分かっていることを言われると子どもは「俺(私)は、親から信じてもらえていないのかな?」などと不安になります。その結果、親御さんに対して強く反発することもありますので、登校の朝は特に必要最低限の干渉に留めておきましょう。
また、必要以上に干渉しないというのは、お子さんが登校できなかったときも同じです。
お子さんが学校に行けなかったら親としては心配になりますし、不安からあれこれ言いたくもなります。しかし、親御さんから話をするのは必要な内容だけに留めて、あえて子どもに自分の気持ちや考えと向き合う時間を与えてあげたいものです。
✅ 3. 気持ちを”言葉にする力”を育てる:感情語の対話
子:「なんか疲れた…」
親:「疲れたって、どんな感じ? 体が疲れた?気持ちが疲れた?それとも両方?」
子どもは自分の感情を具体的に表現することが苦手な場合があります。「疲れた」「嫌だ」「ムカつく」といった漠然とした表現から、より具体的な感情語を使えるようにサポートしましょう。
「不安」「心配」「さみしい」「怒り」「困惑」など、感情を具体的な言葉にする練習を重ねることで、感情理解・情緒調整の力(非認知能力の核となる部分)を高めることができます。
感情に名前を付けることができれば、その感情とうまく付き合う方法も見つけやすくなります。
✅ 4. 親の”反応”を整える:安心の土台をつくる
「また行けなかったの?」「どうして行けないの?」ではなく、 「そう感じたんだね」「話してくれてうれしいよ」「一緒に考えてみよう」
お子さんが不安や困りごとを打ち明けたとき、親の最初の反応がとても重要です。親が動揺したり、すぐに解決策を提示したりすると、子どもは「話さない方がよかった」と感じてしまうかもしれません。そうなると子どもは親御さんにすら自身の気持ちを吐露できなくなってしまいます。
まずは、お子さんの気持ちをそのまま受け止めること。親の落ち着いた受け止めが、子どもに”話していい”という安心感を与え、信頼関係の維持につながります。
この信頼関係こそが、お子さんの回復への第一歩となります。
✅ 5. 自立の一歩を支える:環境と習慣の整え方
「明日の準備、何からやってみる?」 「チェック表つくってみる?」
生活リズムを整えたり、学校の準備をしたりする際も、指示や命令ではなく、お子さんと一緒に”工夫”を考えることを心がけましょう。
「7時に起きなさい」ではなく、「何時に起きたい?そのためには何時に寝る?」といった問いかけで、子ども自身に考えてもらいます。
親が手を出しすぎず、かといって放っておきすぎることもなく、適度な距離感でサポートすることが、お子さんの自主性や計画力といった非認知能力の育成につながります。
登校しぶりが続いたら?
もし登校しぶりが数日、数週間と続くようであれば、親御さん達だけで無理に解決しようとせず、次のような相談機関があることを知っておいてください。
- 学校との連携:担任の先生やスクールカウンセラーと相談し、別室登校や保健室登校などの配慮を検討する
- 教育支援センター・フリースクールの活用:学校以外の学びの場で、お子さんのペースに合わせた支援を受ける
- 訪問支援や家庭教育支援への相談:専門家からの個別支援やアドバイスを受ける
- 医療機関の受診:心身の不調が続く場合は、小児科や児童精神科での相談も検討する
早い段階で「家庭でできること」だけに抱え込まず、信頼できる専門家とつながることが大切です。一人で悩まず、お子さんに最適な支援の形を一緒に探していきましょう。
まとめ|子どもの「成長する力」を信じて対応しましょう!
子どもは、”登校できた・できない”の白黒では測れません。
大切なのは、「登校」よりも、「不安を抱えながらも自分で向き合える力」を育てること。
夏休み明けの不安定な時期も、お子さんが自分自身と向き合い、感情をコントロールし、困難を乗り越える力を身につける大切な成長の機会です。
親の関わり方が、お子さんの人生にとって本当の土台になります。完璧を目指さず、お子さんのペースを大切にしながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。
「今」のお子さんを受け入れ、「これから」の成長を信じて、温かく見守っていけば大丈夫です。
🟧 専門家のサポートをお求めの方へ
もしお一人で悩みを抱えていたり、具体的な対応についてより詳しく相談したい場合は、お気軽にお問い合わせください。お子さんとご家族にとって最適なサポートの形を一緒に考えさせていただきます。
✅ 専門家に相談したい方はこちらからご連絡ください→https://lin.ee/ktXdpWc
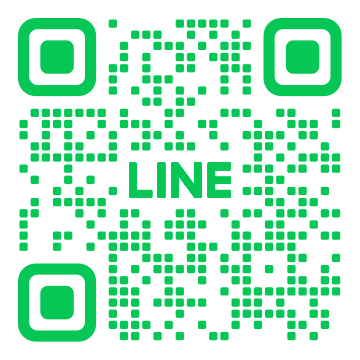
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














