夏休み直前、子どもの“ちょっと休みたい”が続く理由と親の対応
- 2025/07/15
- 2025/07/17

「最近、学校を休みたがるんです…」という相談が増えています
「うちの子、最近『学校休みたい』って言うことが多くて…」 「朝起きるのが辛そうで、無理矢理起こすのも心配で」 「夏休みまでもう少しなのに、どうしてこのタイミングで?」
6月から7月にかけて、このようなご相談をいただくことが増えています。
実は、この時期は子どもたちにとって疲労が蓄積しやすい時期。新学期から約3ヶ月が経ち、学校生活に慣れてきた時期だからこそ、「気が緩む」「疲れが出る」「不安が表面化する」ということが起こりやすいのです。
お子さんの「ちょっと休みたい」という気持ちは、実は自然な反応なのかもしれません。
なぜ今?子どもが”休みたくなる”3つの背景
① GW明けからノンストップの疲れ
ゴールデンウィーク明けから夏休みまでの約2ヶ月間、子どもたちは本当によく頑張っています。
- 運動会や参観日などの学校行事
- 学習内容の本格化とテスト
- 暑さの中での登下校と体育授業
- 友達関係の構築と維持
これらを毎日続けてきた反動が、この時期に出やすくなります。大人でも2ヶ月間休みなく働き続けたら疲れますよね。子どもならなおさらです。
② 「慣れ」からくる気のゆるみ・不満の表面化
学校生活に慣れてきたことで、最初は我慢していたことに気づきやすくなります。
「あの子の話し方、実は嫌だった」 「この授業、つまらないな」 「給食のこの献立、苦手だな」
新学期の緊張感が薄れた分、これまで見えなかった不満や不安が表面化しやすくなるのです。これも成長の証拠とも言えるでしょう。
③ 嫌なことや不安を”避けたい”気持ちが強まる
疲れが溜まると、ちょっとした出来事でも「行きたくない」という気持ちが膨らみやすくなります。
- 苦手な授業がある日
- 友達とのちょっとした行き違い
- 宿題が間に合わなかった時
- 体調が少し悪い時
普段なら乗り越えられることでも、心の余裕がない時は「避けたい」という気持ちが強くなってしまいます。
“休みグセ”がつく前にできること
まず大前提として、学校を休むこと自体が悪いことではありません。
体調不良や心の疲れを感じた時に適切に休むことは、自分を守る大切な行動です。
ただし、「行きたくないときは休めばいい」という思考パターンが定着してしまうと、負のループに陥りやすくなります。
- 嫌なことがあると逃げる
- 逃げることで一時的に楽になる
- でも根本的な解決にはならない
- 再び同じ状況に直面して逃げる
このループを断ち切るためには、「不安やモヤモヤにどう向き合うか」を一緒に考えることが大切です。
夏休みの過ごし方がカギ

休み明けの登校に大きく影響するのが「夏休みの過ごし方」です。
避けたい過ごし方:
- 昼夜逆転の生活
- 一日中ゲームやスマホ
- 嫌なことから目をそらすだけの時間
- 何の目標も持たないダラダラした日々
目指したい過ごし方:
- 規則正しい生活リズム
- 心と体の回復
- 小さな自信を取り戻す経験
- 新学期への前向きな気持ち作り
夏休みは、お子さんの心を回復させ、新学期への活力を蓄える大切な時間です。
親ができる3つの関わり
① 学校の話ではなく「気持ち」に寄り添う
避けたい声かけ: 「明日は学校行けそう?」 「みんな頑張ってるよ」 「休んでばかりじゃダメでしょ」
おすすめの声かけ: 「今日はどんな気持ちだった?」 「何か嫌なことがあったの?」 「どうしたら気持ちが楽になるかな?」
学校に行く・行かないの話ではなく、まずはお子さんの気持ちに寄り添うことから始めましょう。
嫌なことがあるなら、それをどうしたら解決できるのか、一緒に考えるサポートをしてあげてください。
② 生活リズムを整える”仕掛け”を一緒に考える
生活リズムの乱れは、心の不安定さにも直結します。
具体的な取り組み例:
- 朝食を一緒に作る
- 散歩やラジオ体操などの軽い運動
- 夜の過ごし方を見直す(スマホ・ゲーム時間の調整)
- 就寝・起床時間の習慣化
理想は、お子さんが自分で生活リズムを整えることです。
しかし、既に生活リズムが崩れかかっている場合は、「なぜそうした方がいいのか」という話をしながら、「どう整えるか」という部分まで一緒に考えてみてください。
③ 夏休みに”やりきれる経験”を一つでも
自己効力感(「自分はできる」という感覚)を育てることが、登校への原動力になります。
やりきれる経験の例:
- 簡単な家庭での役割(お風呂掃除、食器洗いなど)
- 自分で決めた小さな目標(本を5冊読む、絵を描くなど)
- 興味のある分野の探究(昆虫観察、料理など)
- 地域のイベントやボランティアへの参加
大切なポイント:
- 親が決めるのではなく、子どもが決める
- 達成可能な小さな目標から始める
- やる・やらないは子ども次第
- できた時はしっかり認めてあげる
「やりきった」という経験は、お子さんの自信に確実につながります。
心の回復に必要な親の姿勢
お子さんが「休みたい」と言った時の親の対応は、その後の親子関係にも大きく影響します。
心がけたいこと:
- 頭ごなしに否定しない
- 「なぜ?」を問い詰めすぎない
- 子どもの気持ちを受け止める
- 一緒に解決策を考える姿勢を示す
避けたいこと:
- 「甘えている」と決めつける
- 他の子と比較する
- 無理矢理学校に行かせようとする
- 感情的になって叱る
お子さんにとって、家庭が「安心できる場所」であることが何より大切です。
専門家のサポートを検討するタイミング
以下のような状況が続く場合は、専門家のサポートを検討することをおすすめします。
チェックポイント:
- 2週間以上、登校を嫌がる日が続いている
- 食欲や睡眠に明らかな変化がある
- 以前楽しんでいた活動にも興味を示さない
- 家族以外の人との関わりを極端に避ける
- 自分を責めるような発言が増えている
一人で抱え込まず、学校のスクールカウンセラーや地域の相談機関を活用することも大切です。
まとめ:お子さんの”ちょっと休みたい”は心のSOSかもしれません
夏休み直前の「休みたい」という気持ちは、お子さんの心からのSOSかもしれません。
その背景を一緒に読み解き、夏休みを子どもの成長につなげる期間にしていきましょう。
今日から始められること:
- お子さんの気持ちに寄り添う対話を心がける
- 夏休みの過ごし方を一緒に考える
- 小さな「やりきれる経験」の機会を作る
お子さんの「休みたい」という気持ちも、成長の過程の一部です。
その気持ちを受け止めながら、お子さんが自分らしく学校生活を送れるよう、サポートしていきましょう。
わが子に合った関わり方を相談したい方へ
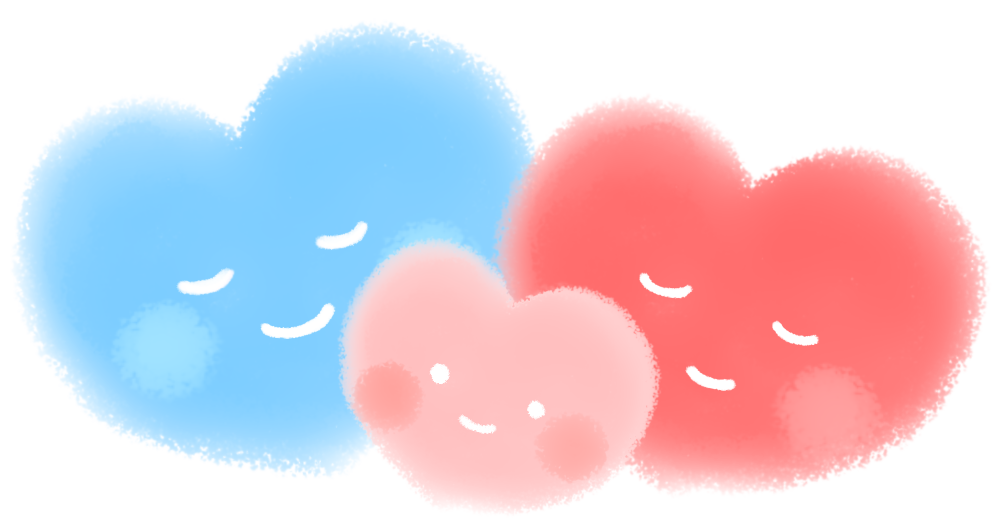
「うちの子の場合はどうしたらいいの?」
「具体的な声かけ方法を知りたい」
「夏休みの過ごし方を一緒に考えてほしい」
そんな方のために、個別サポートをご用意しています。
まずは、お気軽にご相談ください。
以下のいずれかからご連絡いただけます。
🌟 お問い合わせフォームから送信する
→ 簡単な入力だけでOK。お子さんの状況に合わせてご返信します。
🌟 公式LINEで相談する
→ 日常のやりとり感覚でメッセージをお送りいただけます。
ご家庭だけで悩まず、必要な時は専門家のサポートもご検討ください。
お子さんの笑顔と、ご家族の安心のために、一緒に歩んでいきましょう。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














