夏休みが終わったら、うちの子行けるかな…。
夏休みの過ごし方で変わる⁉ 登校しぶりを防ぐ親の関わり方
- 2025/08/01
- 2025/08/12

親御さん
夏休みの後半。子どもがダラダラ過ごす様子に、ちょっと不安を感じていませんか?
実は、”夏休みの家庭での過ごし方”が、夏休み明け(2学期)のスタートを左右することがあります。この記事では、登校しぶりを防ぐための親のサポート方法をご紹介します。
1. 夏休み明けに行きしぶりが増える理由

「学校、なんか行きたくない…」が出やすい時期
夏休み明けに子どもが学校に行くのを嫌がる理由は、実はとても自然なことです。主な理由として以下のようなものがあります:
- 朝起きられない – 夏休み中の不規則な生活リズム
- 勉強や友だち関係の不安 – 長期間離れていることへの心配
- 家でのラクさに慣れてしまう – 自由な時間への依存
文科省の調査でも、長期休み明けは不登校が増えやすい時期と言われています。つまり、多くの家庭で共通して起こりうる課題なのです。
2. 家での関わり方が、夏休み明けを左右する

「干渉しすぎ」も「放ったらかし」もNG!
親の関わり方によって、子どもの2学期スタートが大きく変わってきます。
干渉しすぎると:
「もう宿題やったの?」→ 言われるまでやらない子に
放任すぎると:
「自分でやるでしょ」→ ノープランでダラダラに
大事なのは、“見守りつつ寄り添う”スタンスです。子どもの自主性を尊重しながらも、必要なサポートを提供するバランスが重要になります。
3. よくある親の本音と夏明けのリスク
多くの親が抱える夏休み中の悩みには、以下のようなものがあります:
- つい口出しして、あとで後悔
- 勉強しない姿にイライラ…
- 自分から動いてほしいのに、動かない…
この時期、親の声かけが子どもの自信ややる気に影響します。イライラした気持ちをそのまま子どもにぶつけてしまうと、かえって子どもの学校への不安を高めてしまう可能性があります。
自身の感情と子どもに伝えたいことを混同してしまうと、怒りの気持ちだけが子どもに伝わってしまい、その結果子どもから強い反発が生まれて親子間で喧嘩など亀裂が生まれることも珍しくありません。イライラしてしまうお気持ちも分かりますが、少し落ち着きながら子ども達には対応していきたいですね。
4. 登校しぶりを防ぐ!親の3つの関わり方
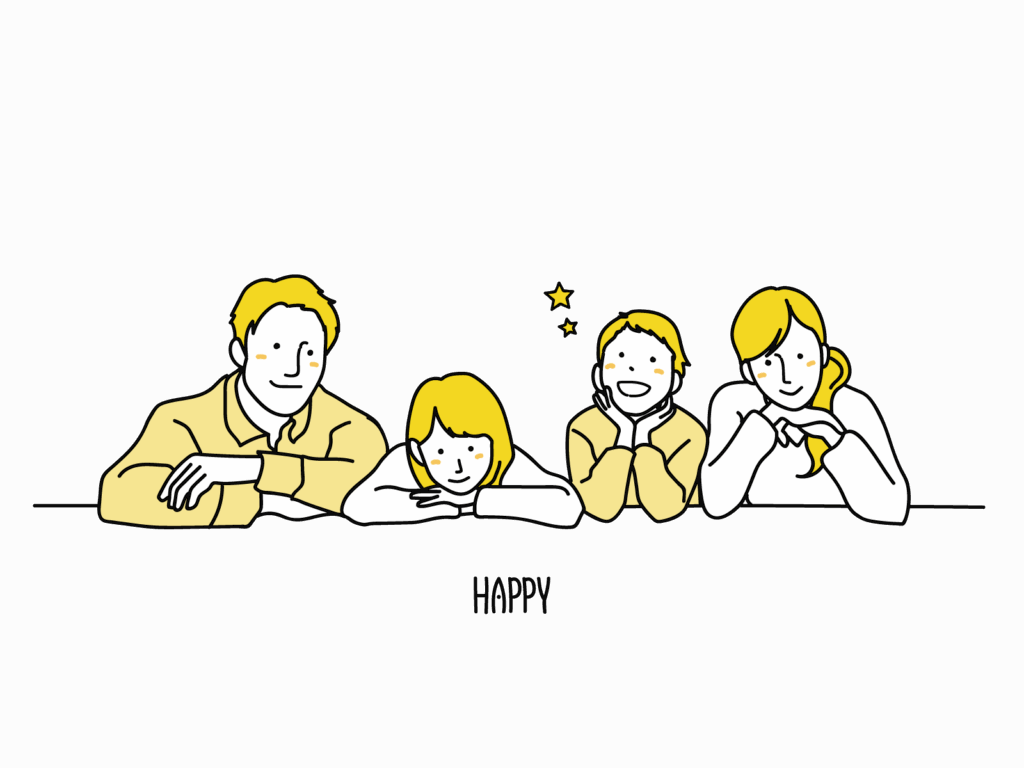
✅ 1. 考える力を引き出す「伴走の声かけ」
困ったときはすぐアドバイスするのではなく、「どうしたらいいと思う?」と一緒に考える声かけを心がけましょう。
この声かけにより、自分で考えて動く力が育ちます。親が答えを与えるのではなく、子ども自身が解決策を見つけるプロセスを大切にすることで、自立心と問題解決能力が養われます。
ただ、この言葉を何度も使うのは避けたいところです。子ども達も知能のある人間ですから、「なんで同じことばかり言うの?」などと疑問に感じることも出てきます。同じ内容でも聞き方を変えていく、つまり、親御さんの言葉のバリエーションを増やしていくことも子どもとのコミュニケーションにおいて重要になってくるでしょう。
✅ 2. 生活リズムは”ゆるやかに”戻す
「明日から早起きしてね」は禁物です。急激な変化は子どもにとって大きなストレスになります。
効果的な方法:
- 起床・就寝を少しずつ整える(1日15分ずつなど)
- 朝ごはんづくりなどで”動く習慣”をつくる
- 学校の時間割に合わせた活動を段階的に取り入れる
無理なく”学校モード”に切り替えることで、スムーズな新学期スタートが可能になります。親御さんだけで決めてしまうのではなく、子どもと一緒に無理のない計画を立てていけるといいですよね。
✅ 3. 達成感は「自分で感じる」しくみを
子どもが自分で成果を実感できる環境を作ることが大切です。
具体的な方法:
- チェックリストを作って、自分でマーク
- 終わったあと「どうだった?」と感想を聞く
- 達成したことを一緒に振り返る時間を作る
親が確認するのではなく、自分で振り返って「できた」と感じられることが大切です。この体験が自信につながり、学校生活への前向きな気持ちを育みます。
5. まとめ:夏休みは”自立”のチャンスに
学校がない今こそ、子どもの力を伸ばすタイミングです。「どう過ごすか」が「どう育つか」に直結します。
親の関わり次第で、子どもが”自分で動く力”を育てる夏になります。完璧を求めず、子どもの成長を信じて、適切なサポートを続けることが何より重要です。
2学期が始まってからの登校しぶりを防ぐためには、夏休み中の今から、子どもの自立を促す関わり方を心がけましょう。きっと、子どもは自分なりのペースで成長していくはずです。
ご相談はこちら
「うちの子にはどう関わればいいの?」
「みちびき」では、お子さんの性格や状況に合わせた個別サポートをご用意しています。
お問い合わせフォーム または 公式LINE から、お気軽にご相談ください。
状況をうかがった上で、具体的な声かけや対応策をお伝えいたします。一人で悩まず、専門家と一緒に最適な解決策を見つけましょう。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














