非認知能力を家庭で伸ばす3つのステップ
- 2025/11/07
- 2025/11/07

〜”できない”を”やってみよう”に変える家庭の関わり方〜
「非認知能力」という言葉を耳にする機会が増えてきました。でも、「それって具体的にどう育てればいいの?」「家庭で何をすればいいの?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。
非認知能力は、学力テストでは測れない、でも人生を豊かにする大切な力です。そして、この力を育むのに最も適した場所が「家庭」なのです。
この記事では、家庭教育の中で非認知能力を伸ばす具体的なステップを、今日から実践できる形でお伝えします。子どもが動けない、やる気が出ない、失敗を怖がるといった姿に悩んでいる方にこそ、読んでいただきたい内容です。
非認知能力とは?家庭で育つ”生きる力”

非認知能力とは、テストの点数では測れない、人が社会で生きていくために必要な力のことです。
認知能力と非認知能力の違い
- 認知能力:テストで測れる力(計算力、読解力、記憶力など)
- 非認知能力:生き方に関わる力(意欲、共感、粘り強さ、自己調整、自信など)
どちらも大切ですが、実は非認知能力こそが、認知能力を支え、学んだ知識を活かすための土台になります。
非認知能力の具体例
- 意欲・やる気:新しいことに挑戦したいと思える気持ち
- 共感力:他者の気持ちを理解し、思いやれる力
- 粘り強さ:困難に直面しても諦めずに続ける力
- 自己調整力:感情をコントロールし、適切に行動する力
- 自己肯定感:自分を信じ、価値ある存在だと思える感覚
家庭教育が”非認知能力の土台”になる理由
非認知能力は、特別な教材やプログラムで育つものではありません。毎日の会話、生活習慣、親の態度、家族との関わり――こうした日常の積み重ねの中で、少しずつ育っていくものです。
子どもは、親がどんな言葉をかけるか、どう反応するか、どんな姿勢で向き合うかを敏感に感じ取っています。朝のあいさつ、食卓での会話、失敗したときの対応、すべてが子どもの「生きる力」を育てる教材になるのです。
つまり、家庭こそが非認知能力を育む最高の学びの場。親が意識的に関わることで、子どもの心の土台は確実に強くなっていきます。
🔗 関連記事:🏠 家庭教育とは?家庭教育力が低下する理由と、今“親にできること” – みちびき | 伸びゆく力を共に育む、親子のみちしるべ
家庭で非認知能力を伸ばす3つのステップ
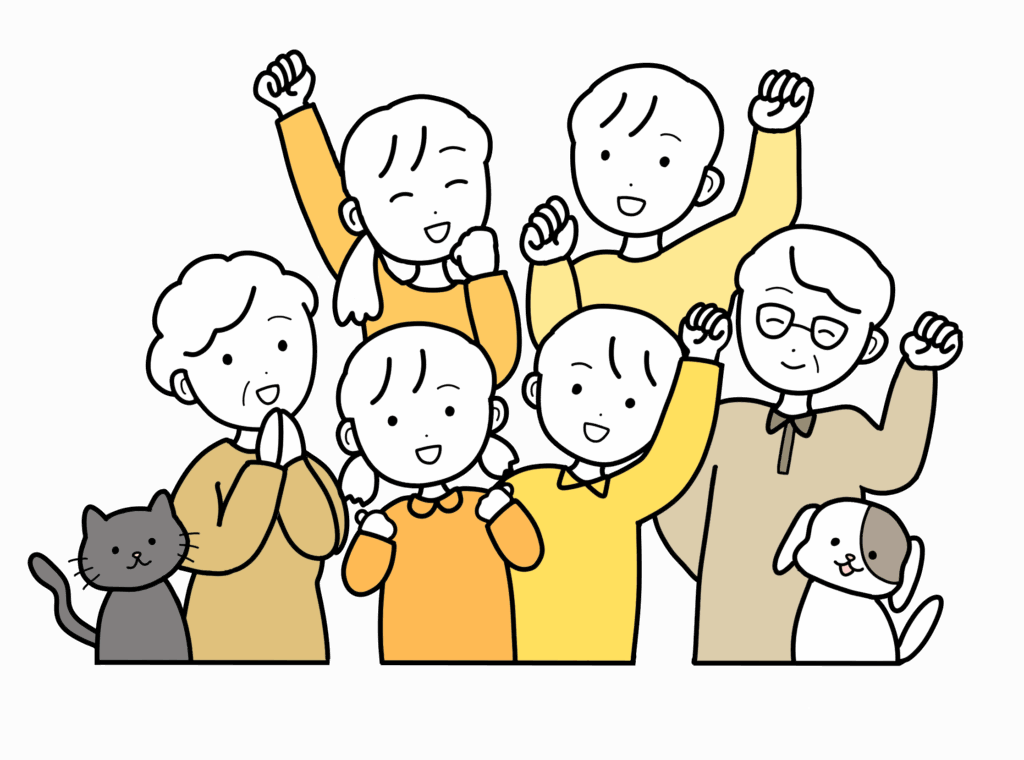
非認知能力を育てるには、段階的なアプローチが効果的です。ここでは、家庭ですぐに実践できる3つのステップをご紹介します。
🟢 ステップ1:子どもの”今”を理解する
非認知能力を伸ばす第一歩は、子どもの行動や言葉の裏にある感情を理解することです。
子どもの行動の裏にある”感情”を見抜く
子どもが「やりたくない」「できない」と言うとき、それは単なる怠けや甘えではないかもしれません。その背景には、不安、恐れ、自信のなさ、疲れなど、さまざまな感情が隠れています。
例えば、宿題をやらない子どもは、「面倒くさい」のではなく「間違えたら怒られるかもしれない」という不安を抱えているかもしれません。朝起きられない子どもは、「怠けている」のではなく「学校で何かつらいことがある」のかもしれません。
「できない」ではなく「まだ練習中」と捉える姿勢
子どもの今の状態を、固定されたものとして見ないことが大切です。「この子はできない子」ではなく、「まだ練習中の段階」と捉えることで、親の関わり方が変わります。
「できない」と決めつけてしまうと、子どもも「自分はダメなんだ」と思い込んでしまいます。でも、「まだ練習中」と思えば、「今はここまでできたね。次はこうしてみようか」という前向きな声かけができるようになります。
親が”正解”を急がないことが第一歩
親はつい「早く正しい答えを」「早くできるように」と焦ってしまいがちです。でも、非認知能力を育てるには、この「急がない」姿勢が何より大切です。
子どもが自分のペースで考え、試行錯誤できる時間を確保すること。そして、その過程を温かく見守ること。それだけで、子どもは「自分のことを信じてくれている」と感じ、挑戦する勇気を持てるようになります。
🟡 ステップ2:肯定的な関わりと小さな成功体験
理解の次に大切なのは、子どもが「できた」という実感を積み重ねられる関わりです。
「やれたね」「助かったよ」と事実を認める声かけ
子どもを褒めるとき、「すごい!」「えらい!」といった評価の言葉よりも、「やれたね」「お手伝いしてくれて助かったよ」という事実を伝える言葉の方が効果的です。
評価の言葉は、「親が良いと思ったからOK」というメッセージになりますが、事実を伝える言葉は、「あなたの行動には価値がある」というメッセージになります。これが自己肯定感につながります。
結果よりも”過程”を褒める
テストで100点を取ったこと、何かに成功したことだけを褒めていると、子どもは「成功しないと認められない」と思うようになります。
そうではなく、「毎日コツコツ練習したね」「諦めずに最後までやったね」「自分で工夫して考えたね」といった過程を認めることが大切です。
過程を褒められた子どもは、結果がどうであれ「努力すること自体に意味がある」と学びます。これが粘り強さややり抜く力を育てます。
家庭で「できた」が積み重なると、自己効力感が育つ
小さな「できた」体験の積み重ねが、自己効力感(自分はできるという感覚)を育てます。
自己効力感が高い子どもは、新しいことにも「やってみよう」と思えますし、失敗しても「次はこうしてみよう」と前向きに捉えられます。
家庭でできる小さな成功体験の例:
- 朝、自分で起きられた
- 洗濯物をたたむのを手伝った
- 宿題を自分から始められた
- 友達とケンカして、自分から謝れた
- 苦手な食べ物に挑戦してみた
どんなに小さなことでも、それを認め、価値づけることで、子どもの自信は少しずつ育っていきます。
但し、子どもが既にできていることに対して「できてるね」と伝えるのは幼い対応になります。子どもの年齢が上がってくると認める対応をしているつもりでも、子ども側は「バカにしてるの?」と捉えてしまうこともあります。気を付けたいところです。
🔵 ステップ3:自分で考え、選ぶ場面を作る
最後のステップは、子ども自身が考え、決断する力を育てることです。
親が先回りしすぎない、”任せる”練習
親はつい、子どもが困らないように先回りしてしまいがちです。でも、それでは子どもが自分で考える力、判断する力が育ちません。
「もう時間だから宿題やりなさい」ではなく、「何時から宿題始める?」と聞く。「これ持った?」ではなく、「明日の準備、自分でチェックしてみて」と任せる。
最初は忘れ物をしたり、失敗したりするかもしれません。でも、その経験こそが学びになります。
自分で考えるための問いかけの例
- 「明日の準備、どうする?」
- 「何分休憩したら始められそう?」
- 「うまくいかなかったとき、どうしたらいいと思う?」
- 「今日はどんなことがあった?どう感じた?」
- 「あなたはどう思う?」
こうした問いかけは、子どもに「自分で考えていいんだ」「自分の意見を持っていいんだ」というメッセージを伝えます。
失敗を許容し、改善を一緒に考える
任せると、当然失敗もあります。でも、その失敗を責めるのではなく、「どうすればうまくいくかな?」と一緒に考えることが大切です。
失敗を責められると、子どもは挑戦しなくなります。でも、失敗を学びの機会として扱ってもらえると、「失敗してもいいんだ。次に活かせばいいんだ」と思えるようになります。
これが、困難に直面しても諦めない粘り強さと、自分で問題を解決する力を育てます。
家庭教育で非認知能力が伸びると、子どもはどう変わる?
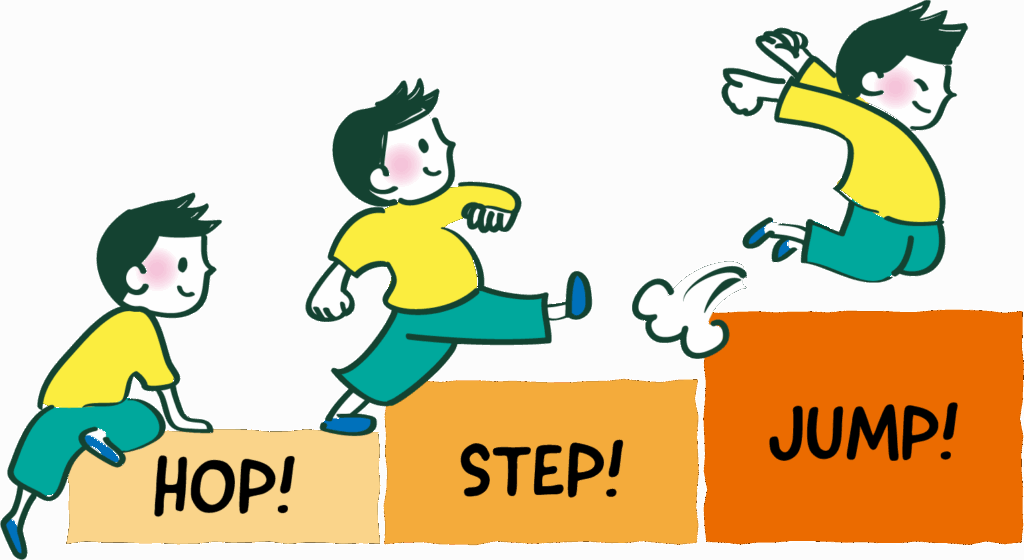
非認知能力が育った子どもには、目に見える変化が現れます。
「失敗=終わり」から「失敗=次のチャンス」に変わる
非認知能力が育つと、子どもの失敗への捉え方が変わります。
今まで「間違えたらどうしよう」「失敗したら恥ずかしい」と怖がっていた子どもが、「うまくいかなかったけど、次はこうしてみよう」と前向きに考えられるようになります。
これは、レジリエンス(回復力・立ち直る力)とも呼ばれ、人生を通じて役立つ重要な力です。
親子の対話が増え、感情のやり取りが柔らかくなる
子どもが自分の感情を言葉にできるようになり、親もそれを受け止められるようになると、家庭の雰囲気が変わります。
「今日はこんなことがあって嫌だった」「こうされて嬉しかった」と素直に話せる関係は、子どもの情緒の安定につながります。
また、親も「私も今日は疲れてる」「あなたのこと、本当に心配してるの」と感情を伝えられるようになることで、互いに理解し合える関係が築けます。
学校・友人関係への適応力も高まる
非認知能力は、学校や友人関係にも良い影響を与えます。
自己調整力が育つと、感情的になりすぎず、落ち着いて行動できるようになります。共感力が育つと、友達の気持ちを理解し、良い関係を築けるようになります。自己効力感が育つと、学習にも前向きに取り組めるようになります。
家庭で育った非認知能力は、学校という社会の中で、子どもを支える大きな力になるのです。
まとめ:家庭教育は”心の筋トレ”
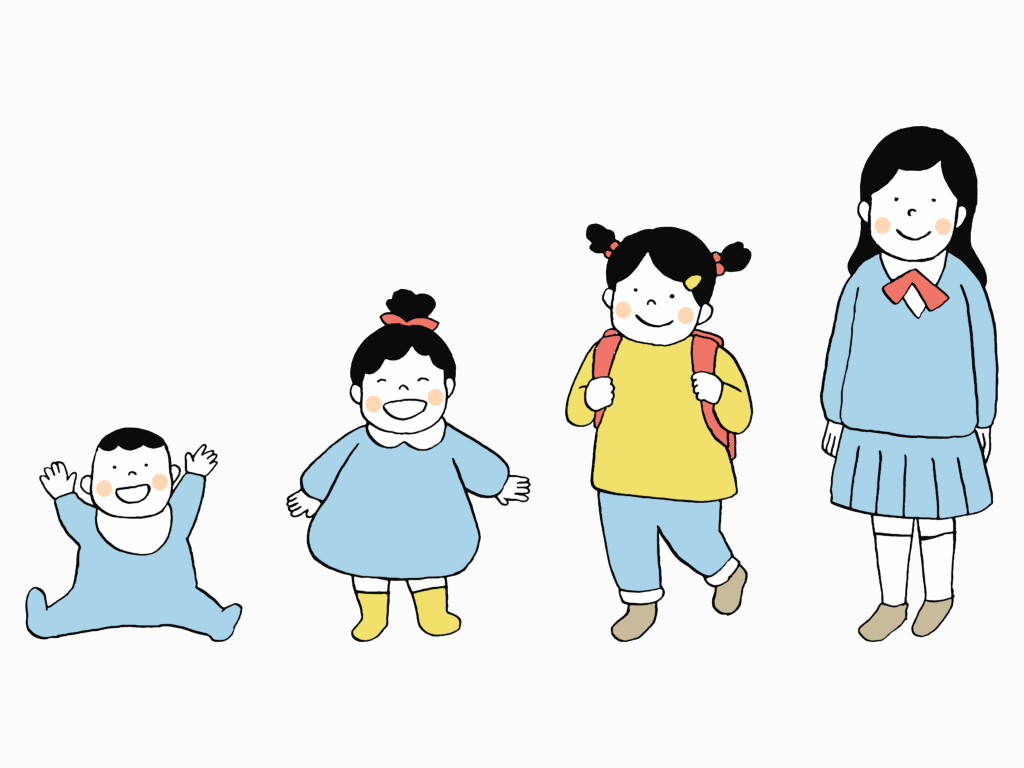
非認知能力は、一夜にして育つものではありません。まるで筋トレのように、毎日の小さな積み重ねが、やがて大きな力になります。
非認知能力を育てる3つのステップ
- 子どもの”今”を理解する:行動の裏にある感情を見抜き、急がず見守る
- 肯定的な関わりと小さな成功体験:過程を認め、「できた」を積み重ねる
- 自分で考え、選ぶ場面を作る:任せて、失敗を学びに変える
親が「待てる」「見守れる」「励ませる」関わりを続けることで、子どもは自分を信じる力を育てていきます。
完璧な親である必要はありません。大切なのは、子どもと真摯に向き合い、一緒に成長しようとする姿勢です。
今日から、ほんの少しだけ、子どもとの関わり方を意識してみませんか?小さな変化が、やがて子どもの大きな成長につながっていきます。
家庭教育は、子どもの心を育てる”心の筋トレ”。親子で一緒に、少しずつ、確実に、育っていきましょう。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














