「やる気が続かない子」に共通する理由と、家庭で育てられる“自分を高める力”とは?
- 2025/07/09
- 2025/07/17
お子さんを見ていて「やる気がないように見える」「やり始めても続かない」「失敗するとすぐに投げ出す」
そんなお悩み、ありませんか?
親としては「もっと頑張ってほしい」「最後までやり遂げてほしい」と思うものの、何度声をかけても変わらない我が子を見て、困り果ててしまうこともあるでしょう。もしかすると「うちの子はもうできない子なんじゃないかしら・・・」と半ば諦めておられる方もいるかもしれません。
でも実は、これらは”怠けている”のではなく、「自分を高める力」がまだ育っていないだけかもしれません。
この力は生まれつきの才能ではなく、家庭での関わり方次第で確実に育てることができます。今日は、その具体的な方法をお伝えします。
「自分を高める力」って何?

📌 みちびきで定義する3つの非認知能力のうちのひとつ
「自分を高める力」とは、単なる「やる気」や「根性」とは違います。以下の3つの要素から成り立つ、とても大切な能力です。
目標に向かって努力を続ける力 小さな困難があっても「もう少し頑張ってみよう」と思える力。一度や二度の失敗で諦めず、継続して取り組める粘り強さです。
小さな成功を積み重ねて、自信を育てていく力 「やればできる」という感覚を自分の中に蓄積していく力。過去の成功体験を糧にして、新しい挑戦にも前向きに取り組めるようになります。
自分で「やってみよう」と思える内発的動機づけ 人に言われたからではなく、自分の心の中から「面白そう」「やってみたい」と感じられる力。この内側からのエネルギーこそが、本当の成長を支えます。
この「自分を高める力」は、学校でも将来でも求められる「生きる力」の土台になります。勉強だけでなく、人間関係、仕事、趣味など、人生のあらゆる場面で必要となる大切な力なのです。
この力が弱いとどうなる?(親が気づきやすいサイン)
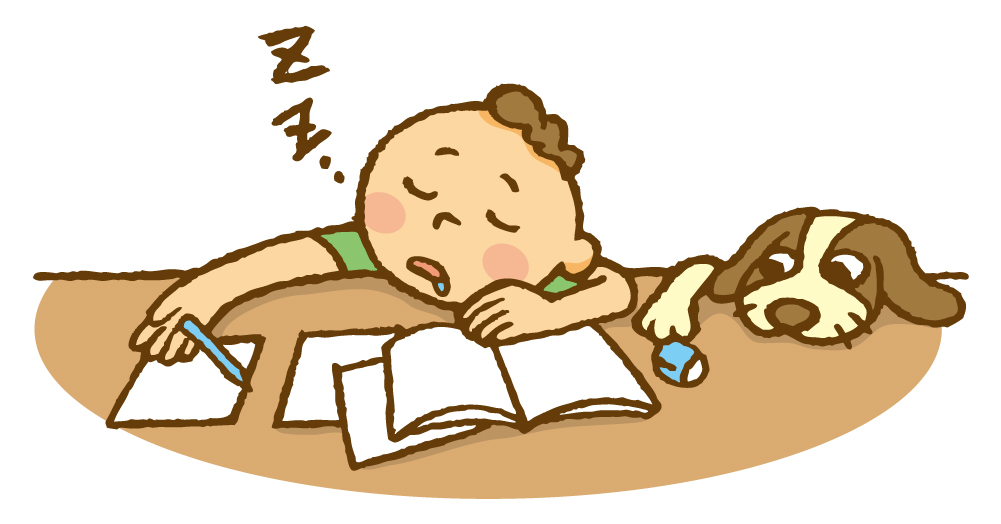
「自分を高める力」が十分に育っていないお子さんには、以下のような行動パターンが見られることがあります。
宿題や学習を先延ばしにする 「後でやる」「明日やる」と言いながら、結局ギリギリまで手をつけない。やらなければいけないことは分かっているのに、なかなか行動に移せません。
少しでも難しいことはやらない 「分からない」「できない」と感じると、すぐに諦めてしまう。挑戦する前から「無理だ」と決めつけて、避けてしまいがちです。
「どうせムリ」とすぐ諦める 失敗を恐れるあまり、最初から期待値を下げてしまう。「どうせ自分にはできない」という思い込みが強くなっています。
褒めても「たまたまだよ」と受け取れない せっかく良い結果が出ても、「運が良かっただけ」「偶然うまくいっただけ」と考えてしまい、自信につながりません。
これらの行動の裏には、“成長している実感”の欠如があることが多いのです。子どもの「投げやり」な態度は、決して怠けているわけではなく、「頑張っても意味がない」と感じてしまっているサインかもしれません。
家庭でできる5つの育て方
ここからは、「自分を高める力」を家庭で具体的に育てる方法をご紹介します。どれも今日から始められる、実践的な内容です。

1. 小さな目標を”いっしょに”決める
「今日は何を頑張ってみる?」「どんなことにチャレンジしてみたい?」
目標設定で大切なのは、親が一方的に決めるのではなく、お子さんと一緒に話し合って決めることです。自分の意思で決めたことは、がんばりやすくなります(自己決定力の育成)。
最初は「漢字を3個覚える」「本を5分読む」など、確実にクリアできる小さなものから始めましょう。大きすぎる目標は、達成できずに自信を失う原因になってしまいます。
ポイント:「できそう?」「これなら頑張れる?」と子どもの感覚を確認しながら、一緒に決めることが大切です。
2. 目標に向かっている”途中”を褒める
「頑張ってるね」「集中してるね」「諦めないで取り組んでるね」
結果が出る前の、取り組んでいる最中の姿勢や努力を認めることで、お子さんの自己効力感がアップします。
「テストで100点取れたらすごいね」ではなく、「毎日コツコツ勉強してるね」「分からないところを質問できたね」といった、プロセスに注目した声かけを心がけましょう。
ポイント:結果より「やっている姿勢」を承認することで、子どもは「努力すること自体に価値がある」と感じられるようになります。
3. できたことを見える化する(カレンダー・表など)
成長の「見える化」が、やる気のエンジンになります
頑張ったことや達成したことを、カレンダーにシールを貼ったり、チェック表に印をつけたりして、目に見える形で記録しましょう。
「今日もできた」「3日連続でできた」「1週間続けられた」という小さな積み重ねが、子どもにとって大きな自信となります。
ポイント:完璧を求めず、「できた日」を素直に喜び合うことが大切。できなかった日があっても「また明日頑張ろう」と前向きに捉えましょう。
4. 結果が出なかった時こそ「どう感じた?」と聞く
失敗を「意味のある経験」に変える内省力を育てる
うまくいかなかった時こそ、子どもの気持ちに寄り添う絶好のチャンスです。「どうしてできなかったの?」ではなく、「どんな気持ち?」「何が難しかった?」と感情や体験に焦点を当てて聞いてみましょう。
「悔しかったんだね」「難しかったけど頑張ったね」と気持ちを受け止めながら、「次はどうしてみる?」と一緒に考えることで、失敗を成長の材料に変えることができます。「やって終わり」ではなく、上手くいかなかったときこそそれをどう改善すればいいのか等まで考えていけるといいですね。
ポイント:責めるのではなく、一緒に振り返る姿勢が大切。失敗から学ぶ力こそが、将来の成功につながります。
5. 「あなたならやれる」と”信じて見守る”
親の信頼は、子どもの心に「挑戦してみよう」という勇気を与える
「できるかな?」「大丈夫かな?」という不安な気持ちを抱きながらも、「あなたならきっとできる」「お母さん(お父さん)はあなたを信じてる」というメッセージを伝え続けましょう。
すぐに手を出したり、代わりにやってあげたりするのではなく、子どもが自分で取り組めるよう、少し離れた場所から温かく見守ることが大切です。
ポイント:信頼のメッセージは言葉だけでなく、態度や表情からも伝わります。親の安心した表情が、子どもに安心感を与えます。
実際の支援現場から(ケース紹介)

小学4年生のAくんの変化
Aくんは、何かを始める前から「どうせムリ」「できないよ」と言ってしまう子でした。宿題も「難しい」と感じると、すぐに「分からない」と投げ出してしまい、お母さんも困り果てていました。
そこで、まずは1日5分の「できたメモ」を親子でつけることから始めました。
「今日できたこと」を毎日ひとつずつ書くだけの簡単な取り組みです。最初は「朝起きられた」「朝ごはんを食べた」といった当たり前のことから始めました。
1週間続けると、Aくんは「こんなにできてるんだ」と驚きの表情を見せました。2週間目には「今日は漢字練習もできた」「友達に優しくできた」など、少しずつ内容が充実してきました。
1ヶ月後、Aくんは自分から「明日は算数のプリント、これやってみる」と言うようになりました。「できた」という実感を積み重ねることで、新しいことにチャレンジする勇気が生まれたのです。
お母さんは「同じ子とは思えないくらい、前向きになりました」と驚かれていました。
まとめ|「できるかどうか」より「続けることの価値」に目を向けよう
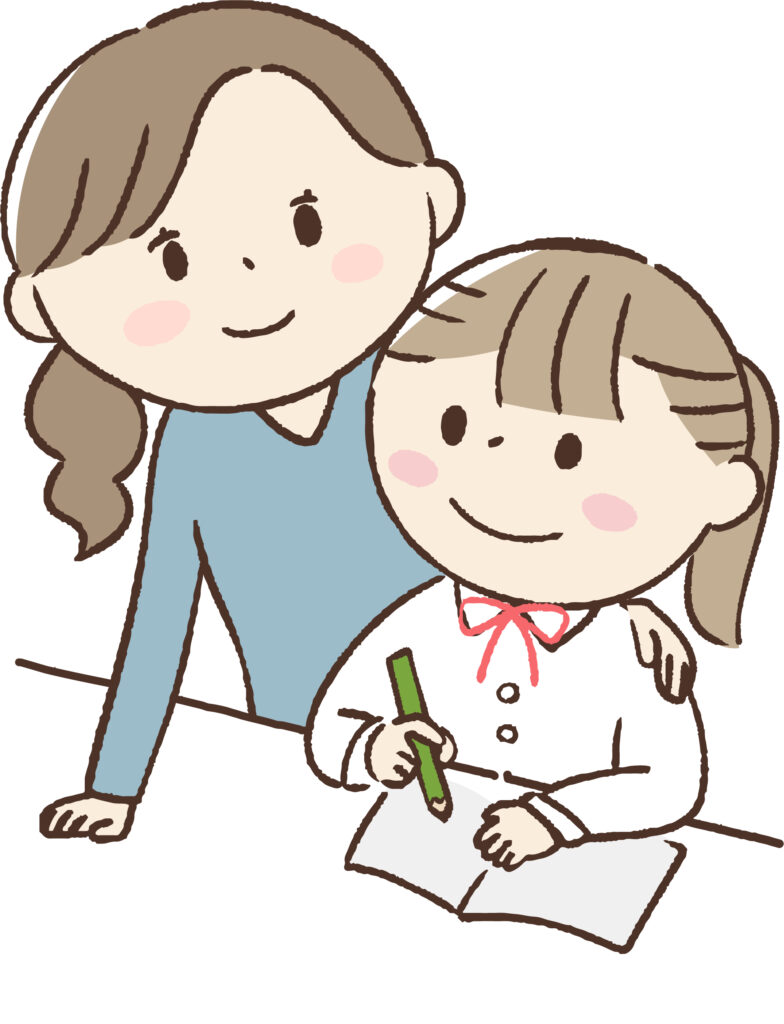
子どものやる気は、もともと”ない”のではなく、”育てられるもの”です。
結果ではなく、過程を見てくれる大人がいること。それが「自分を高める力」を伸ばす一番の栄養です。
「テストで何点取れた」「コンクールで入賞した」といった目に見える成果も大切ですが、それ以上に大切なのは、「毎日少しずつ取り組んだ」「諦めずに続けた」「失敗しても立ち上がった」という、目には見えにくい成長の過程です。
お子さんの小さな変化や努力に気づき、それを言葉にして伝えることで、「自分を高める力」は確実に育っていきます。
完璧を求めず、お子さんのペースを大切にしながら、温かく見守り続けてください。その積み重ねが、お子さんの人生を支える大きな力となるはずです。
🟧 より具体的なサポートをお求めの方へ
「うちの子の場合はどうしたらいい?」「具体的な声かけの方法を知りたい」という方のために、個別の家庭教育サポートも行っています。
お子さんの性格や状況に合わせた、カスタムメイドのアドバイスをご提供いたします。
▶ 子どもへの具体的な声かけを知りたい方は「みちびき」までご相談くださいhttps://lin.ee/ktXdpWc
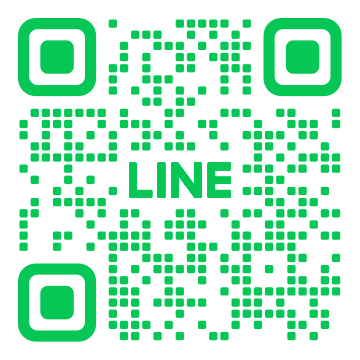
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














