「運動会に行きたくない」と言われた朝に—— 行き渋る子どもへの親の声かけと家庭でできるサポート
- 2025/10/15
- 2025/11/18

秋の空気とともにやってくる”運動会シーズン”。子どもが「行きたくない」「お腹が痛い」と言い出す朝、親はどうしていいか迷ってしまいますよね。
実は、運動会の”行き渋り”は珍しいことではありません。人前に出る不安、競争のプレッシャー、音や雰囲気への過敏さなど、多くの子どもがこの時期に一度は抱く自然な反応です。
「無理に行かせるべき?」「休ませたら甘やかしになる?」——そんな葛藤を抱える保護者の方へ。この記事では、支援現場でもよく見られる運動会前後の心理変化を踏まえながら、家庭でできる具体的なサポート方法を紹介します。
「無理に行かせる」でも「諦める」でもない、”中間の選択”があることを知っていただければ幸いです。
なぜ”運動会前後”に行き渋りが起きやすいのか?
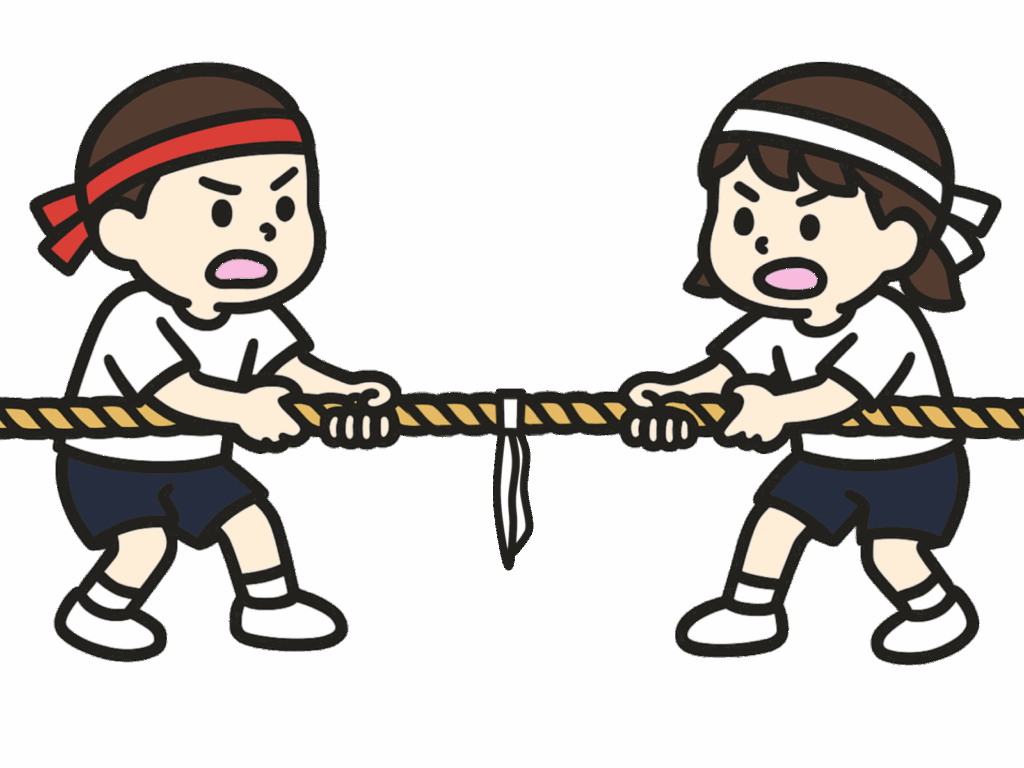
運動会は、子どもにとって特別な負荷がかかるイベントです。普段は元気に登校できる子でも、この時期だけ行き渋りが出ることは決して珍しくありません。
その背景には、いくつかの心理的・身体的要因が重なっています。
① 競争・注目へのプレッシャー
「みんなの前で失敗したくない」という感情は、子どもにとって非常に強いストレスです。
●練習での失敗経験が記憶に残っている
●順位や結果を意識してしまう
●教師や親からの期待を感じている
●観客(保護者や来賓)の視線が怖い
子どもは、大人が思う以上に「失敗したらどう思われるか」を気にしています。特に、自己肯定感が育ちきっていない段階では、「できない自分」を見せることへの恐怖が行動にブレーキをかけるのです。
② 感覚過敏・環境変化への負担
運動会は、いつもの学校生活とは全く違う刺激に満ちています。
●大きな音(拡声器、スピーカー、歓声)
●強い日差しや気温の変化
●いつもと違う時間割・動線
●大勢の人がいる混雑した空間
特にHSP(Highly Sensitive Person)傾向や発達特性のある子どもは、”いつもと違う環境”に過敏に反応しやすく、心身ともに疲弊してしまいます。
「なんとなく嫌」「理由は分からないけど行きたくない」という言葉の背景に、こうした感覚的な負担が隠れていることも少なくありません。
③ 家庭内での“緊張の共有”
意外かもしれませんが、親の関わり方も行き渋りを強めることがあります。
親が「頑張って」「楽しんできて」「いい結果出せるといいね」と過度に励ますと、子どもは「成功しなきゃいけない」というプレッシャーを感じます。
また、親自身の不安や焦り(「休んだらどう思われるだろう」「クラスで一人だけ欠席になったら」など)も、子どもに伝わります。親の緊張が、子どもの登校エネルギーをさらに削いでしまうのです。
💬 支援現場の声
「行けるかどうか」よりも、「行きたい気持ちが残っているか」を大切に。
親ができる3つのサポートステップ

運動会の朝、子どもが「行きたくない」と言ったとき。親ができることを3つのステップで整理します。
🟢 ステップ1:行ける・行けないを“白黒”で決めない
多くの親は「行くか、行かないか」の二択で考えてしまいがちです。しかし、子どもの心はもっと繊細で揺れ動いています。
「どこまでなら行けそう?」と聞いてみましょう。
●「開会式だけ見に行ってみる?」
●「お昼までいて、午後は帰ってもいいよ」
●「見学席で見てるだけでもいいよ」
●「学校の近くまで行って、様子を見てから決めよう」
こうした“グレーな選択肢”を提示することで、子どもは「完璧にやらなくてもいい」「自分のペースでいい」という安心感を得られます。
結果として、「じゃあ行ってみようかな」と動き出せることも多いのです。
🟡 ステップ2:“できた事実”を見逃さず認める
たとえ運動会に行けなかったとしても、その朝までに子どもが何かしらの行動をしているはずです。
●朝、起きることができた
●運動会の服を出した
●靴下を履いた
●リビングまで来た
●「行きたくない」と言葉にできた
どんな小さな一歩でも、「できたね」と事実を認めましょう。
「でも行けなかったじゃない」と結果だけを見るのではなく、そこに至るまでのプロセスに目を向けることが重要です。
親に認められた“できた事実”が、次の行動エネルギーになります。
🧩 非認知能力との関連
「自分で決めて動けた」「やってみた」という成功体験が、“やり抜く力(GRIT)”の芽を育てます。
🔵 ステップ3:行けなかった日も“失敗”にしない
もし運動会に行けなかったとしても、それは「失敗」ではありません。
「行けなかったから終わり」ではなく、「また次があるね」と未来志向で締めましょう。
●「今日は無理だったけど、明日はどうかな?」
●「運動会は難しかったけど、普通の日なら行けそう?」
●「今日の気持ちを教えてくれてありがとう。次はどうしたいか一緒に考えよう」
運動会を通して、子どもは“自分を理解できた経験”を得ています。
●自分は大勢の前が苦手だと分かった
●音が大きいと不安になることに気づいた
●親に正直に話せた
これらは、すべて成長のステップです。
家庭教育は、“できたか”ではなく、“感じたか”を大切にする場です。
欠席・遅刻・途中参加になりそうな時の連絡例
運動会に行けない、または遅れそうなとき、学校への連絡に悩む保護者は多いです。
以下のような表現で伝えると、柔軟な対応を受けやすくなります。
📩 先生への連絡テンプレート
いつもお世話になっております。
本人が朝から体調・気持ちの面で不安が強く、参加が難しそうです。
状況を見ながら、途中から見学や短時間参加の形で伺うかもしれません。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
ポイント:「欠席」と断定せず、「柔軟な参加」の可能性を残す表現にすることで、子ども自身も「まだ行けるかも」という選択肢を持ち続けられます。
また、「体調・気持ちの面で」と伝えることで、身体的な不調だけでなく心理的な負担があることを学校側にも理解してもらいやすくなります。
但し、学校側も安全配慮義務がありますから、できること・できないことが出てきます。判断は学校側に任せるしかありませんが、子どもの気持ちを伝えながら学校の先生と一緒に妥協案を探していけると安心でしょう。
家庭教育として大切にしたい考え方
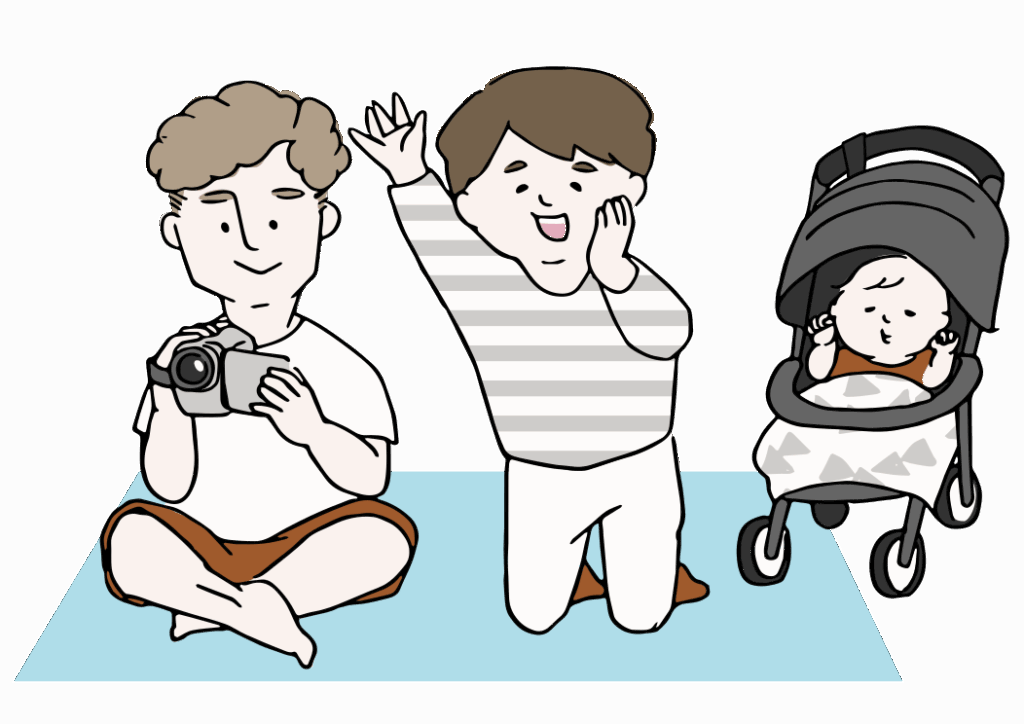
運動会の行き渋りは、家庭教育を見つめ直す機会でもあります。
行き渋りは「弱さ」ではなく、「環境と感情のバランスの乱れ」
子どもが行けないのは、決して「弱いから」「根性がないから」ではありません。
その子にとって、運動会という環境が負荷になっているだけです。環境と感情のバランスが崩れているサインと捉えましょう。
子どもの“感情理解力”を育てるチャンス
「なんで行きたくないの?」と問いかけ、子どもが自分の感情を言葉にする経験は、非認知能力の重要な要素である感情調整力を育てます。
●「緊張してる」
●「失敗が怖い」
●「音がうるさいのが嫌」
こうした言葉が出てくること自体が、成長の証です。
親が落ち着いて“共感→提案→見守り”を意識すると、家庭教育力が上がる
親が焦ると、子どもも焦ります。逆に、親が落ち着いて対応すると、子どもも安心します。
家庭教育の基本は、以下の3ステップです。
- 共感する:「そうか、行きたくない気持ちなんだね」
- 提案する:「じゃあ、こういうのはどう?」
- 見守る:「あなたが決めていいよ」
この姿勢が、子どもの自律性と自己効力感を育てます。
🔗 関連記事:
【まとめ】“頑張らせる”より、“見守る”勇気を
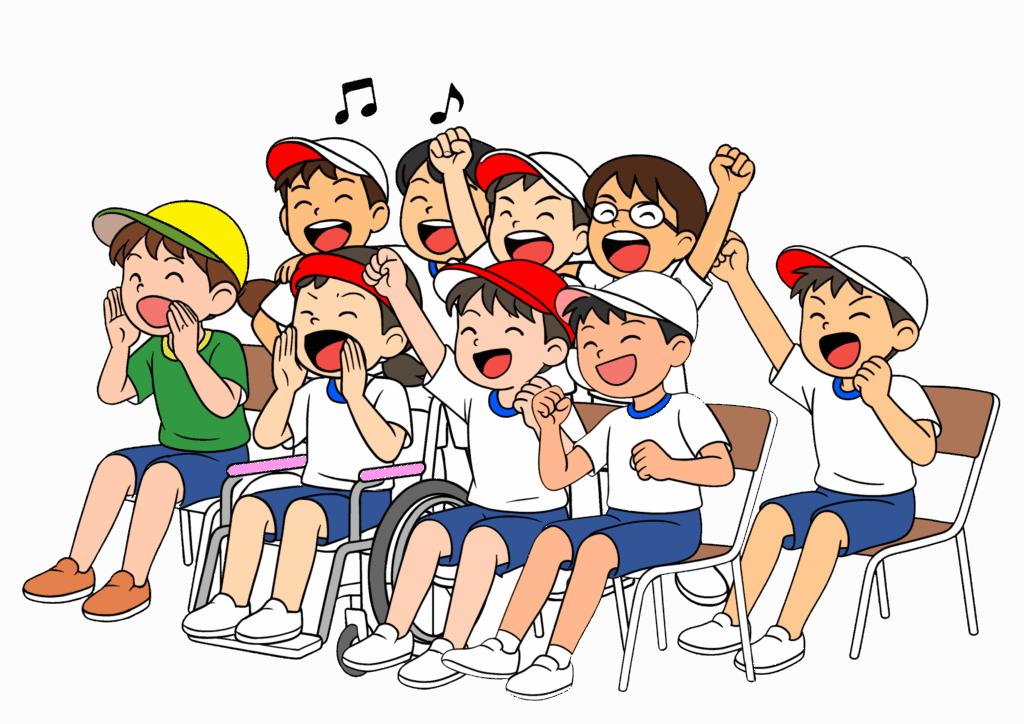
運動会は「一日限りのイベント」ではなく、「子どもの成長過程の一部」です。
行き渋りをきっかけに、親子で“感情のやりとり”を深めることが、家庭教育の本質です。
●無理に行かせようとしない
●行けなかったことを責めない
●小さな一歩を認める
●「また次がある」と未来を示す
“一緒に考えた時間”こそ、子どもの心を育てる財産になります。
運動会に行けても、行けなくても、あなたとお子さんが一緒に悩み、話し、決めたこと——それが何よりの成長体験です。
今日この瞬間の親子の対話が、明日の子どもを支える力になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 運動会を休ませると、「逃げ癖」がつきませんか?
A. 「逃げ癖」という言葉で片付けると、子どもの本当の困難が見えなくなります。大切なのは、「なぜ行けないのか」を一緒に考え、子どもが自分で選択できるようサポートすることです。無理に行かせることが、逆に学校全体への拒否感を強めることもあります。
Q2. 周りの子はみんな参加しているのに、うちの子だけ休むのが心配です
A. 他の子と比較することは、親子双方にプレッシャーを与えます。子どもにはそれぞれのペースがあります。「今は難しい」という状態を受け入れ、長期的な視点で成長を見守りましょう。
Q3. 先生や他の保護者にどう説明すればいいですか?
A. 詳細に説明する必要はありません。「体調・気持ちの面で参加が難しい」と伝えれば十分です。理解してくれる人は理解してくれますし、理解しない人に無理に説明する必要もありません。
Q4. 運動会の後、学校に行けなくなることはありますか?
A. 運動会をきっかけに不登校が始まるケースもあります。行き渋りが続く場合は、学校のスクールカウンセラーや地域の相談機関に早めにつなぐことをお勧めします。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも家庭教育の一部です。
この記事が、運動会の朝に悩むあなたの心を少しでも軽くできたら幸いです。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














