親の習い事とは?——「子による」を前提に、家庭の回し方を一緒に設計する
- 2025/10/03
- 2025/10/03

朝の支度、別れ際、宿題、就寝。毎日くり返すのに、うまくいく日といかない日がある。書籍やネットには答えが並びますが、結局どれも最後は「子による」。親としては「また、そのセリフか・・・」と思うことは1度や2度ではないはず・・・。ただ、それは子の気質・状況・家庭の関わり方によって”効くレバー”が違うからです。
親の習い事を提唱している“みちびき”は、この「子による」を分析して言語化し、実践に変える場。本記事では、専門語を使わずに家庭の回し方(=家庭オペレーション)を解説し、一概に言い切らない方法論を示します。
「家庭の回し方」= 家庭の”運用設計”
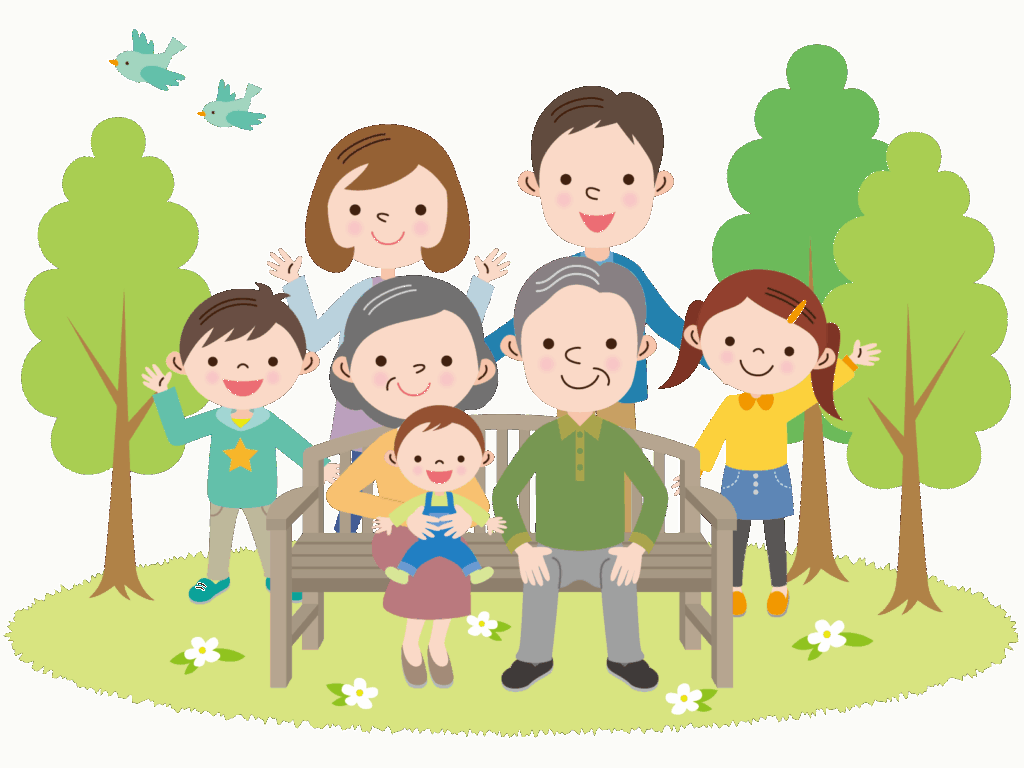
家庭の回し方(=家庭オペレーション)とは、感情や偶然に左右されずに毎日を再現可能に回すための運用設計のことです。
目的:偶然ではなく仕組みで安定させる
気分や体調に左右されにくい、安定した日常の土台を築きます。
我々親も子ども達と同様人間です。特に女性はホルモンバランスなどの影響からイライラしやすい日も出てきます。そんな時、自分自身をよく理解していると対処できることも増えてきます。
要素(ただし中身は各家庭で変わる)
- 声かけの骨格(順序だけ固定)
- 環境の整え方(置き場・時間の合図・見える化)
- やり過ぎ防止の上限(促し回数・説得延長ナシ)
※ここで”型”を押し付けることはしません。方法は仮説であり、各家庭で調整します。何が合うかは、実際にやってみなければわかりません。だからこそ、短いサイクルで試しながら、お子さんに合う形を見つけていきます。
なぜ「一概にこうすればいい」と言えないのか
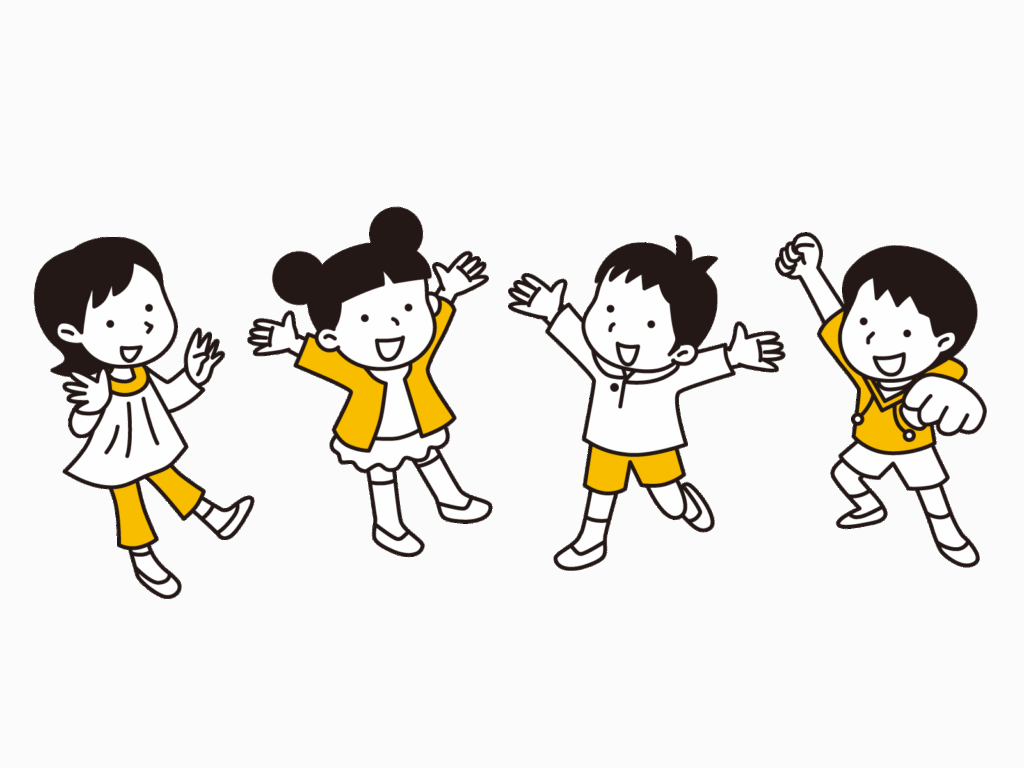
その理由は、子どもには大きな個体差があるからです。気質やその日の状態、家庭の関わり方や環境が違えば、同じ対応をしても同じ結果にはなりません。ここを見落とすと、どんな“正論”も現場では空回りします。
一方で、現場を重ねると傾向別のパターンは確かに見えてきます。たとえば「見通し不安が強い」「没頭の中断に弱い」「反発が出やすい」「依存度が高い」など。私たちは専門家として、こうしたパターンごとの“型”(当たり)を提示できます。
大事なのは、型をそのまま当てはめるのではなく、親御さんと協力して微調整することです。お子さんの様子を一緒に観察し、言葉の量・待ち時間・距離・選択肢・環境の合図といったレバーを最小限ひとつだけ動かしながら、あなたの家庭に合う回し方へ整えていきます。
つまり、「子による」は諦めではなく方法です。個体差を尊重しつつ、パターンで当たりを付け、親×支援者で最小限の調整をかける——この三段構えが、みちびきの支援の中核です。
「子による」朝の準備時間の親の対応
同じ「朝の準備」でも、効く手が異なります。
●見通し不安が強い
短い予告や視覚合図で落ち着きやすい。次に何をするかが見えると、動き始めやすくなります。
●没頭中断に弱い
予告を減らし環境の切替(置き場・照明・画面)で自然移行。言葉での予告が、かえって抵抗を生むことがあります。
●反発が強い
命令調を避け、合意ベースの言い換え。同じ内容でも、言い方を変えるだけで受け取り方が変わります。
●依存が強い場面
距離や共同作業比率を段階的に調整。いきなり離れるのではなく、少しずつ距離を取ります。
ここに挙げたように、やり方は”子による”。ここを分析→助言→実践→再分析という短いサイクルで合わせていくのが、みちびきの価値です。
みちびきの進め方(「子による」を方法にする)
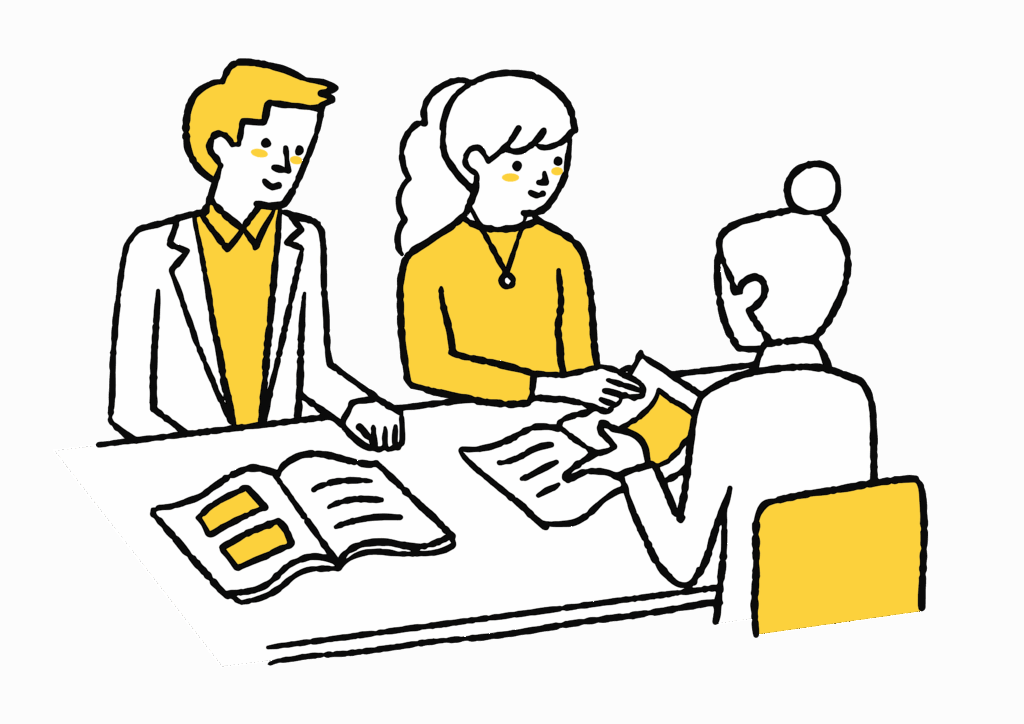
① 分析(家庭教育コーディネーター=支援者)
電話カウンセリングやメッセージカウンセリング(親子会話)にてお子さんの日常生活の様子をヒアリングします。止まりやすいタイミング、親子の位置関係、最初の一言、子の反応などを元にアセスメント(分析)します。
② 助言(家庭教育コーディネーター→親御さん)
アセスメント(分析)した上でお子さんやそのご家庭に合った対応をアドバイス(助言)します。これまでやってきた子どもに対する対応を変えていくのは、容易ではありません。これまでのやり方と真逆過ぎて受け入れ難い内容もあるかもしれませんが、その場合は遠慮なく担当の家庭教育コーディネーターにおっしゃってください。「こうしてください。」という一方的な話だけではなく“何故そうするのか”アセスメントによって導き出した理由もお伝えします。
③ 実践(親御さん)
アドバイス内容をご家庭で実践していただきます。これまでと異なるやり方になることが殆どですから、始めから上手くいかなくても大丈夫です。支援初期は特に“上手くできていない”事実に気づき、受け入れることが大切です。それができれば少しずつ変わっていくことが可能になるでしょう。焦らず進めていくことが肝要です。
④ 再分析(家庭教育コーディネーター=支援者)
何より大事なのは、実践していただいた後のお子さんの反応です。それを親御さんから再度ヒアリングし、再度アセスメントしていきます。改善の兆しが見えたら、その方向で磨き込みます。変化が乏しければ、別の角度から試します。ここで初めて「子による」という判断ができるようになってきます。
この流れを繰り返しながら支援を進めていきます。
同じテーマでも、真逆の助言になることがある
テーマ:出発前の”最初の1動作”が始まらない
同じ困りごとでも、お子さんのタイプによって、まったく逆のアプローチが有効なことがあります。
A案(見通し不安タイプ)
「間に合う?」「次は何するの?」と確認が多い、想定外(雨具・持ち物変更)で停止、「失敗したくない」「怒られたくない」の言い回しが多いなどの傾向が見られます。
この手のタイプのお子さんは、事前に親子で話し合っておくと安心することがあります。
🔴事前相談:親子で朝の流れを確認(例:①顔を洗う→②着替え→③靴下→④水筒)、子の不安も整理しておくとよい
🔴必要に応じて見える化:紙やホワイトボードに工程を書き、玄関やリビングに貼って常時確認できる状態にしておくと朝の不安軽減ができるでしょう。
次の行動が見えることで、心の準備ができます。タイマーで時間が視覚化されると、さらに安心して動けることもあるので、お子さんが必要と捉えている場合は活用してみるのも一つです。
B案(没頭中断に弱いタイプ)
好きな活動(動画・ゲーム・読書)からの離脱で荒れがち、「今いいところなのに」「あとちょっと!」が口癖、次の活動に入れば普通に動けるという傾向が見られます。
この手のタイプの子は、親御さんが先回りしてしまうと子どもからの反発が強く出てしまいがちです。
🔴事実から始める:時間を過ぎても好きな活動を続けてしまった“結果”で対応。起きた直後ではなく、落ち着いた時に短い振り返りを実施。朝のことは“夕方学校から帰ってきてから”が鉄則。
🔴声掛けの頻度を減らす工夫:没頭し過ぎて自分で止めることが困難な場合は、視覚タイマーや時間で勝手に切れる設定を活用するのも一つです。
言葉での予告が、かえって抵抗を強めることがあります。環境が静かに変わることで、自然に次の行動へ移れます。
どちらが合うかは分析しながら実践で判断します。
よくある落とし穴と回避策

声かけ増量の力技
言葉は最小。まず環境(置き場・合図)を整える。
言葉を増やすほど、子どもは動かなくなることがあります。環境が整っていれば、最小限の声かけで十分です。
促しの連打
上限1回を決める。超えたらその日は切り上げ。
何度も促すと、親も子も疲弊します。1回と決めることで、促す側も楽になります。
合う/合わないの見極め不足
1週間は同条件、変更は1要素のみ。
毎日やり方を変えると、何が効いているか判断できません。同じ条件で続けることで、初めて見えてくるものがあります。
ご相談ください。
書籍やネットの一般論は出発点として有益です。ただ、そのままでは合わないことも多い。
みちびきでは、現在の状況を精査しどの対応が最適なのかご家庭と一緒に探していきます。
「親の習い事」=学びを”あなたの家庭に合う回し方”へ変える時間。まずはお気軽にご相談ください。
FAQ(よくあるご質問)
Q. 一般論は無意味ですか?
A. 無意味ではありません。仮説の材料として活用し、お子さん用に調整します。
書籍やネットの情報は、考えるための出発点です。そこから、お子さんに合う形へカスタマイズしていくことが大事だと考えます。
Q. どれくらいで変化が出ますか?
A. 個差がありますが、理解の早いご家庭だと1ヶ月ほどで変化が見えてくることが多いです。
劇的な変化を期待するのではなく、小さな兆しを大切にします。「少し楽になった」という感覚が、最初の一歩です。
Q. 記録が苦手です。
A. 気になった点だけのピックアップでも構いません。詳細に関しては電話カウンセリング時に伺うことも可能です。
完璧な記録は必要ありません。「今日はどうだったか」という感覚を、簡単な記号で残すだけで大丈夫です。
Q. 夫婦で意見が割れます。
A. 意見が割れても構いません。
大事なことは“お子さんの為に何が最適か”です。やり方は様々ありますから、親御さんのお気持ちを整理しながら調整していきます。時には妥協も必要になることもありますが「なぜそうした方がいいのか」を紐解いていきます。
全てに同意する必要はありません。「促しは1回まで」という一点だけでも合意できれば、家庭は回り始めます。
「子による」は、諦めの言葉ではありません。それは、お子さん一人ひとりに合う道を、丁寧に探すための出発点です。みちびきは、その道を一緒に歩きます。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














