🏠 家庭教育とは?家庭教育力が低下する理由と、今“親にできること”
- 2025/10/24
- 2025/12/02

【家庭教育×非認知能力で「親が育つ力」を取り戻す】
近年、「家庭教育力の低下」が社会問題として取り上げられています。核家族化・少子化、共働きの増加、スマートフォンの普及など、家庭の形や時間の使い方が大きく変化する中で、”子どもにどう関わればいいのか”と迷う親が増えています。
家庭教育は「しつけ」や「勉強を教えること」ではなく、子どもの非認知能力――自立心・共感力・感情の安定などを育む「家庭の学びの場」です。
この記事では、家庭教育力が低下している背景と、みちびきが大切にする”家庭でできる育ちのサポート”を解説します。
家庭教育とは?学校教育との違い
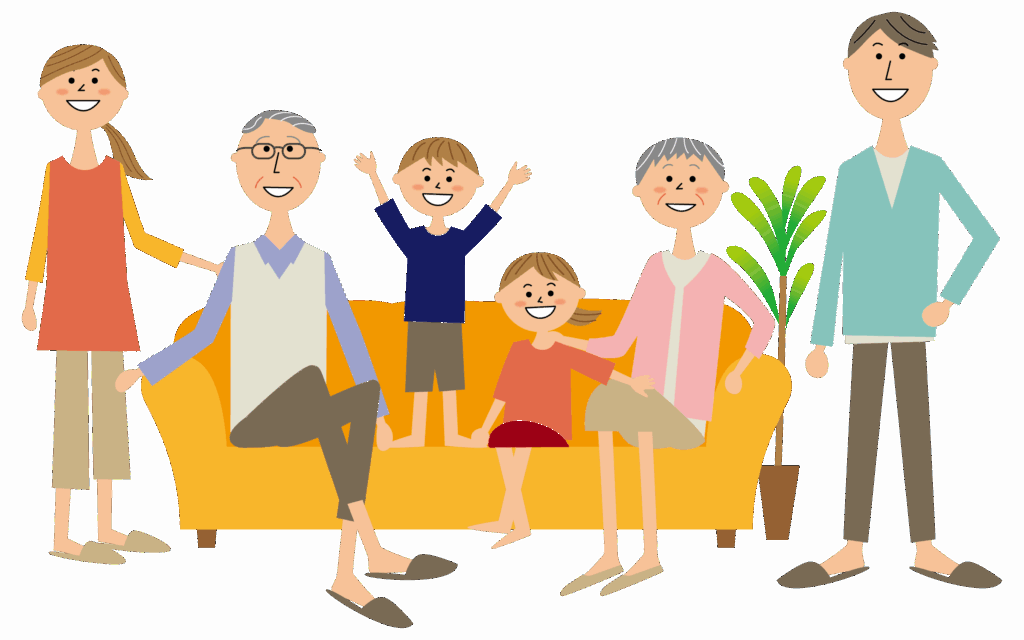
家庭教育とは、家庭の日常生活の中で、子どもが「どう生きるか」「人とどう関わるか」を学んでいく教育です。
学校教育が社会で生きるための知識を学ぶ場であるのに対し、家庭教育はその知識を支える心の土台を育てる場といえます。家庭での会話、生活リズム、親の言葉がけ、感情の扱い方――どれも子どもにとって人格形成の教材になります。
学校教育と家庭教育の違い
- 学校教育 = 社会で生きるための“知識”を学ぶ場
- 家庭教育 = その知識を支える“心の土台”を育てる場
つまり、学力や技能を習得する前に、それを受け止め、活かせる心の器を育てるのが家庭教育の役割なのです。
🔗 関連記事:非認知能力を家庭で伸ばす3つのステップ – みちびき | 伸びゆく力を共に育む、親子のみちしるべ
なぜ家庭教育力が低下しているのか?
家庭教育力の低下には、社会構造の変化が大きく関わっています。ここでは主な5つの要因を見ていきましょう。
1. 核家族化・少子化による孤立
昔は祖父母や近所との関わりの中で自然に学べた「家庭教育」も、いまは家族だけで完結するようになりました。子どもも親も他者の目や支えを感じにくくなっています。
複数世代で子育てを分担していた時代とは異なり、現代の親は子育てのノウハウや価値観を身近な人から学ぶ機会が減少しています。その結果、育児の判断をすべて自分で下さなければならないプレッシャーが増しているのです。
2. 地域社会とのつながりの希薄化
地域の見守り・支援機能が低下し、家庭が孤立しやすくなりました。育児・教育を「家の中だけで完結」させようとすることが、結果的に親のストレスや不安を増大させています。
かつては近所の人が子どもを叱ったり、親同士が自然に情報交換をしたりする機会がありました。しかし現在は、プライバシー意識の高まりや地域活動への参加率低下により、こうした支え合いの仕組みが機能しにくくなっています。
3. 保護者の精神的・時間的負担
長時間労働・共働き・ワンオペ育児により、親が子どもとゆっくり向き合う時間を確保しづらい状況です。精神的な余裕のなさが、家庭教育の質にも影響を与えています。
特に日本では、仕事と育児の両立支援が十分に整っていない職場も多く、親が疲弊した状態で帰宅することも珍しくありません。心の余裕がないまま子どもと接することで、本来伝えたい愛情や価値観が届きにくくなっているのです。
4. 過保護・放任・無関心の広がり
子どもを守る気持ちが強すぎて「自分で考える力」を奪う過保護、あるいは忙しさから関わりを手放す放任・無関心――どちらも、子どもの自立心・責任感の発達を妨げる要因になります。
過保護は一見、愛情深く見えますが、子どもが失敗から学ぶ機会を奪い、挑戦する意欲を削いでしまいます。一方、放任や無関心は、子どもに「自分は大切にされていない」というメッセージを送ることになり、自己肯定感の低下につながります。
5. メディア・スマホ依存の拡大
長時間のスマホ・ゲーム利用によって、家庭内での会話や体験が減少しています。学習時間の減少、生活リズムの乱れ、集中力の低下など、子どもの生活習慣や社会性の形成に影響が出ています。
デジタル機器は便利なツールである一方、使い方を誤ると家族のコミュニケーションを阻害します。食事中もそれぞれがスマホを見ている、会話がLINEで完結してしまうといった状況は、子どもの対人スキルや感情表現力の発達に影響を及ぼす可能性があります。
家庭教育で大切なこと
家庭教育で最も大切なのは、“教える”ことよりも“共に感じる”ことです。
日常の何気ない関わりの中に、子どもの成長を支える要素が詰まっています。
- 朝のあいさつ、食卓での会話、子どもの失敗への対応
- 「あなたはどう思う?」と聞く姿勢
- 「ありがとう」「助かったよ」と伝える習慣
これらの小さな関わりが、子どもの「自己肯定感」「共感力」「やり抜く力」を育てます。
💡 非認知能力とは
非認知能力とは、学力では測れない“生きる力”のことです。感情のコントロール力・自己表現力・協働力などを指し、これらは将来の幸福度や社会的成功と深く関わっています。
家庭教育の本質は、知識を詰め込むことではなく、子どもが自分で考え、感じ、行動する力を育むこと。そのためには、親自身が子どもの話に耳を傾け、感情を受け止め、共に悩み、喜ぶ姿勢が何より大切なのです。
家庭教育学級との違い
行政が行う家庭教育学級は、地域の保護者が学び合う「啓発の場」です。一方で、みちびきの支援は「一家庭ごとの課題解決」に焦点を当てています。
それぞれの特徴
- 家庭教育学級:一般的な知識提供(横のつながり)
- みちびき:個別の状況に合わせた支援(縦の深掘り)
家庭教育学級では、多くの家庭に共通する子育ての基本や、他の保護者との交流を通じた気づきが得られます。一方、みちびきのような専門的な支援では、それぞれの家庭が抱える固有の課題に寄り添い、具体的な解決策を一緒に見つけていくことができます。
どちらが優れているということではなく、家庭の状況やニーズに応じて、適切な支援を選択することが大切です。
🔗 関連:「家庭教育コンサルティングとは?家庭が“自走する”仕組み」
家庭教育における課題
現代の家庭教育には、大きく分けて2つの課題があります。
1. 家庭の役割を再認識する必要性
家庭教育を「しつけ」や「勉強を見ること」だけと捉えるのではなく、「人として育てる」意識への転換が求められています。
子どもに「やってはいけないこと」を教えるだけでなく、「なぜそうすべきか」を一緒に考え、子ども自身が価値観を形成していけるよう支えることが、これからの家庭教育には必要です。
2. 専門的な支援・知識へのアクセス不足
子育てに関する正確な情報を得られず、不安の連鎖が起こっています。
インターネット上には膨大な情報があふれていますが、その中から自分の家庭に適した情報を見極めるのは困難です。また、相談できる専門家や信頼できる支援機関を知らない、あるいはアクセスしづらいという問題もあります。
こうした情報格差が、家庭教育力の差を生む一因となっているのです。
子どもの教育は親の責任ですか?
「責任」という言葉にプレッシャーを感じる親は多いですが、家庭教育は“完璧な親”を目指すものではありません。
親自身が「関わり方を学ぶ」ことが、子どもにとって最大の教育になります。
子どもは、完璧な親からではなく、悩みながらも成長しようとする親の姿から多くを学びます。失敗を認め、謝ることができる親、自分の感情と向き合い、調整しようとする親の姿勢こそが、子どもに「人として成長し続けること」の大切さを伝えるのです。
🌱 “家庭が変わると、子どもが動き出す”
親が変化を恐れず、学び続ける姿勢を持つことで、家庭全体に良い循環が生まれます。それは決して親だけの責任ではなく、家族みんなで育ち合う過程なのです。
まとめ
● 家庭教育力の低下は、社会構造の変化と家庭の孤立が背景にある
核家族化、地域とのつながりの希薄化、親の負担増加などが複合的に影響しています。
● しかし、“関わり方”を見直せば、家庭教育は取り戻せる
特別なことをする必要はありません。日常の会話、言葉がけ、共に過ごす時間の質を少し意識するだけで、大きな変化が生まれます。
● 非認知能力を育てる家庭の力が、子どもの未来を支える
学力以上に大切な、生きる力の土台は家庭で育まれます。親が子どもと真摯に向き合い、共に感じ、共に成長することが、何よりの教育なのです。
家庭教育に正解はありません。しかし、子どもと向き合おうとする姿勢、学び続けようとする意欲が、必ず子どもの心に届きます。
完璧を目指すのではなく、少しずつ、できることから始めてみませんか?
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














