進路・受験サバイバル:親の関わり方×非認知能力で「崩れない家庭」をつくる
- 2025/10/31
- 2025/11/18
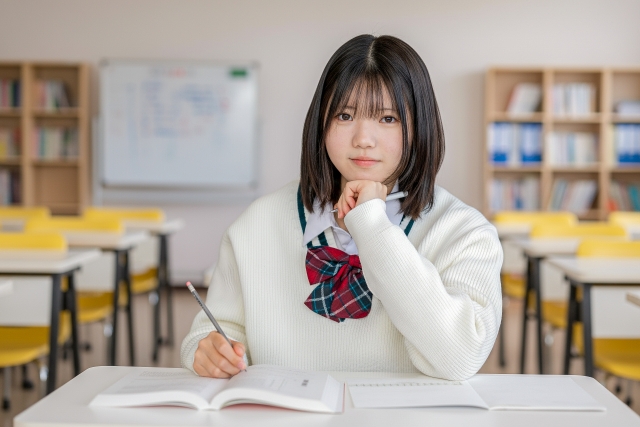
受験が近づくと、多くの家庭で起こるのはこういうことです。
「勉強しなさい」と言ったつもりが、子どもは黙り込む。もう眠いのに「まだやらなきゃ」と机から離れられない。親も眠れない。朝は起きられない。家の空気がピリピリして、誰も深呼吸できていない。
受験という言葉を聞くと、親はまず「点数」「偏差値」「合格可能性」に意識が向きます。もちろんそれは大事です。ただ、実際に家庭が崩れるきっかけはそこではありません。
家庭が揺れるポイントは、だいたい同じ3つです。
- 生活(睡眠・朝の切り替え・食事・体力)
- 感情(不安・焦り・自己否定)
- 対人関係(親子の空気・先生とのズレ・周りとの比較)
逆にいうと、この3つを安定させることができれば、子どもは「いま持っている力」をきちんと試験で出せるようになります。これは、いわゆるハイパフォーマンスな子だけの話ではありません。不登校を経験している子でも、母子登校があった子でも、朝が弱い子でも同じです。
このブログでは、受験期の親が「何をやるべきか」ではなく、どんな関わり方なら家庭が壊れずに乗り切れるのかを整理します。
1. 受験期に崩れやすい3つの領域
① 生活:睡眠・朝・体力が崩れる
受験期は夜型に寄りやすいです。模試、塾、提出物、面接準備…やることが増えるほど、睡眠時間が犠牲になります。寝不足のまま朝を迎えると、起きられない・遅刻が増える・体調が落ちる、という悪循環が起こります。
このとき親がやりがちな声かけは、
- 「明日遅刻したらどうするの」
- 「いい加減に寝なさい」
実はこれ、どちらも逆効果になることがあります。なぜかというと、子どもは「できていない自分」をすでに自覚しているからです。追い打ちをかけられると、開き直るか、さらに自分を責めるかのどちらかに振れます。
大事なのは「行動を正す前に、体を戻す」ことです。
たとえば、
- 「まず水飲んで、顔だけ洗おう」
- 「3分だけベッドから出よう」
というように、「次にやる一歩」を小さく示すと動きやすい。
これはサボりを許すという意味ではなく、「いま動けるだけ動く」を積み上げていく関わり方です。登校が不安定な子や、朝の不調が続く子にも有効です。
② 感情:不安と自己否定が暴走する
受験期は、子ども自身がずっと頭の中でこう考えています。
- 「落ちたらどうしよう」
- 「みんなはもう決まったって聞いた」
- 「これ以上頑張れって言われても無理」
この不安に対して、親はつい「大丈夫」「心配しなくていい」と言ってしまいがちです。でも”根拠のない安心”は、子どもにとっては現実を見てもらえていないように感じることがあります。
代わりに効果的なのは、不安そのものを悪者にしないことです。
- 「そう思ってるんだね。どこが一番こわい?」
- 「面接がこわい?それとも点数?それとも先生に言われるのがこわい?」
こうやって不安に”名前”をつけると、不安は少しだけ小さくなります。不安は「逃げたいから出るもの」ではなく「準備したいから出るもの」と捉え直してあげると、子どもは次の行動に移りやすくなります。
③ 対人関係:家の空気が一番きつい
受験期の家庭でいちばん崩れるのは、実は点数でも遅刻でもなく、空気です。
- 親は「このままだと間に合わない」という焦りがある
- 子は「もうこれ以上言わないで」という限界がある
- 両方イライラして沈黙する
ここが壊れると、その後の支援も届かなくなります。「勉強した?」が地雷になるのはここです。
では何を言えばいいか。ポイントは「時間」ではなく「最初の一歩」を聞くことです。
- 「次の20分、何からやる予定?」
- 「いま困ってるのはどこ?」
- 「どこだけ一緒にやろうか?」
“全部できてるか”ではなく”今からどこに手をつけるか”を一緒に決めると、親は管理者ではなく伴走者の位置に戻れます。これは、親子関係を壊さずに受験期を越えるためのかなり重要な関わり方です。
2. 「非認知能力」は受験でも使う力

「非認知能力」というと、よく”我慢する力””粘り強さ”のように誤解されます。でも実際はもっと具体的です。受験期に必要なのは、次の3つです。
- 自分を高める力
- 自分と向き合う力
- 他者とつながる力
それぞれ、親がどんなふうに支えればいいかまで落として説明します。
1) 自分を高める力(自己管理・微調整する力)
これは「毎日2時間勉強する」のような大きい目標ではなく、「20分だけ集中してみる」「その後5分休憩する」といった小さな単位で自分を運転し直す力のことです。
親はそこを支えてあげてください。
- 「今日はどこを20分やる?」
- 「最初にやりやすいところからでいいよ」
- 「終わったら5分休憩にしよう」
“やったかどうか”ではなく、”スタートできたかどうか”を基準に会話していくと、子どもは失敗を引きずりにくくなります。「一度止まったら終わり」ではなく「何回でも再スタートできる」という感覚を持たせることが目的です。
2) 自分と向き合う力(感情を扱う力)
受験期は、不安やイライラを「なかったこと」にしようとすると反対に大きくなります。むしろ親がしてほしいのは、感情を言語化する手伝いです。
- 「今いちばん気になってるのはどこ?」
- 「そこの何がいや?」
これは”甘やかし”ではありません。感情に名前をつけると、子どもは「自分の状態を把握できている」と感じ、自分を少しコントロールできるようになります。これは本番の場面(面接・試験会場・朝の出発前など)でとても強く効きます。
3) 他者とつながる力(助けを求める力)
「自分でやりなさい」「自分のことは自分で」は、受験期には逆に機能不全を起こすことがあります。
たとえば三者面談。子どもが何も言えないまま大人だけで全部決まってしまうと、本人は”やらされている受験”だと感じやすい。これは、途中で折れやすい形です。
おすすめは、本人が短くでも自分の言葉を持てるように、事前に型を用意してあげること。
- 「最近こういうことがしんどいです」
- 「こういうやり方だと続けやすいです」
- 「だから、こういうサポートがあると助かります」
これは主張ではなく、共有です。大人の都合とぶつからない範囲で、”自分の希望を言っていいんだ”という感覚を育てることが、進学後の安定にもつながります。
3. 三者面談は「叱責の場」ではなく「設計の場」
特に11月ごろにある進路面談(三者面談)は、多くの親子にとって大きなプレッシャーになります。
- もう学校を決めなきゃいけないの?
- 欠席が多いから不利って言われる?
- 先生の前で、どこまで話していいの?
まず、落ち着いてほしいことが1つあります。この時期の面談は、最終決定ではありません。多くの場合は「方向性の確認」「このままいくなら何が足りていないかの確認」「次の一手のすり合わせ」です。
つまり、言い換えるとこうです。
- いまのままなら、どこが現実的か
- 志望校に近づくには何を優先するべきか
- 家庭と学校がどんなふうに役割分担するか
三者面談で聞いていいこと、聞いてほしいこと
- 提出物・授業態度・理解度など、先生が今の本人をどう見ているのか(具体で)
- 欠席・遅刻が評価や出願にどう影響するのか
- 推してもいい学校、避けたほうがいい学校の”理由”
- 推薦や面接など、準備が必要なものはいつから動けばいいのか
- 「今からできる現実的な一手を3つ挙げるとしたら何ですか?」
ここで大事なのは、「どうして内申が低いんですか?」と責任を問い詰めることではありません。大事なのは、「今から上げられる場所(=改善可能性)を具体的に教えてください」という聞き方です。
なぜかというと、受験が近い時期には”全体を直す”時間はもうありません。残っているのは”どこを優先的に押さえるか”だけです。そこを特定するのは、学校の先生の得意分野です。そこを引き出す面談にしましょう。
4. 「この子に合う学校」は偏差値だけでは決まらない
親の中には「とにかく受かってほしい」「安全校でいい」という気持ちになる方もいれば、「少しでも上を狙ってほしい」という方もいます。どちらの感情も自然です。
ただ、ここで一度だけ考えておきたい軸があります。それは「通えるか」という観点です。
”合う学校”かどうかは、こういう要素でも決まります
- 朝型か夜型か
- 人が多い環境が平気か、少人数の方が落ち着くか
- 自分のペースで進めたいか、周りと足並みを揃えるほうがやりやすいか
- 困ったときに相談できる場所や人が校内に見えているか
- 通学時間と体力のバランスがとれるか(往復の負担)
子どもが「がんばれば行ける学校」と「無理なく通える学校」は、似ているようで違います。不登校経験がある子や、朝の立ち上がりが不安定な子の場合、この差は特に大きいです。
選択肢は全日制だけではない
高校や進路の種類は、全日制だけではありません。定時制・通信制・サポート校・エンパワメント系の学校など、いまは選択肢がかなり多様化しています。
どれが正解というよりも、「その子が続けられる場所」を一緒に探すことが、結果的に”自立”に一番近いルートになることがあります。
親としては、偏差値だけでなく「うちの子が、自分のペースで自分の力を使える場所か?」という視点を持っておくと判断がぶれにくくなります。
5. 親の声かけは「追い詰める言葉」から「動ける言葉」へ
受験期に、親の言葉は本当に大きな影響を持ちます。良くも悪くも。
よくある“追い詰める言葉”
- 「このままだと落ちるよ」
- 「ちゃんとして」
- 「お兄ちゃんはもっと頑張ってたよ」
- 「もう時間ないよ」
言ってしまいそうになるのは、とても分かります。親も不安だからです。でも、これらの言葉は、子どもを動かすどころか「もう無理」と思わせて、手を止めさせてしまうことが多いんです。
では、どう言い換えるといいのか
| 追い詰める言葉 | 動ける言葉 |
|---|---|
| 「このままだと落ちるよ」 | 「次の20分は何からやる?」 |
| 「ちゃんとして」 | 「どこが一番やりにくい?一緒にそこだけやろうか」 |
| 「もう時間ないよ」 | 「いま不安なのはどの部分?」 |
| 「なんでできないの?」 | 「今日できたこと、どこまでにしておく?」 |
共通しているのは、”行動を小さく、今ここに戻してあげる”ことです。追い込むのではなく、動ける状態に戻す。これは親にしかできない支え方です。
6. 最後に:受験はゴールではなく「次の生活の入口」
受験の時期は、親も子も消耗します。気持ちも、体力も、お金も、時間も、全部です。だからこそ忘れやすいことがあります。
それは、受験は「終わり」ではなく、「次の生活の入口」だということです。
不登校経験がある子、朝がしんどい子、気持ちが揺れやすい子。そういう子たちは、「受かったかどうか」よりも「入ってから続けられるかどうか」で苦しくなることがあります。
だから親にできるいちばん大事なサポートは、合否だけを見ることではありません。「あなたが安心して過ごせる場所を、一緒に選んでいくよ」というメッセージを、何度でも伝えることです。
受験勉強は1人でやるものに見えます。でも、実際は家庭全体で支えるチーム戦です。
あなたの焦りは、まちがっていません。ただ、その焦りをそのまま子どもにぶつける必要はありません。
子どもが「大丈夫かも」「一緒に考えてくれる人がいる」と思える家庭は、崩れにくい家庭です。崩れにくい家庭は、最後まで走り切れる家庭です。
まとめ:受験期を乗り越える3つのポイント
- 生活・感情・対人の3領域を整える
点数や偏差値の前に、この土台があるかどうかが本番の力を左右する - 非認知能力(自己管理・感情調整・助けを求める力)を日常で育てる
受験はその力を発揮する場。親は伴走者として支える - 「合う学校」を偏差値だけで決めない
通える・続けられる・自分のペースを保てる、という視点を大切に
受験期は終わりではなく、新しいスタートです。親子で一緒に、一歩ずつ進んでいきましょう。
次に読む:関連記事
伴走支援(みちびき)ご案内
「進路選択に迷っている」「受験期の家庭運営が不安」という方は、みちびきの家庭教育コンサルティングにご相談ください。
一家庭ごとの状況に合わせて、現実的なプランを一緒に設計します。
👉 【お問い合わせ・LINE登録はこちら】
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














