自己肯定感の低さで挑戦できないとき|「どうせできない」を外す3ステップと家庭での実践
- 2025/10/10
- 2025/10/10

「失敗が怖い」「新しいことに踏み出せない」「挑戦する前に諦めてしまう」――お子さんのそんな様子に、戸惑いを感じていませんか。
母子登校と直接の因果関係は単線ではありませんが、”自己肯定感の低さ→挑戦回避→経験の機会損失”という連鎖は、一度始まると強化されやすい傾向があります。
この記事のゴール:「できない前提」から「小さくできた」へと流れを作ること。そして、お子さん自身が「できる」という実感を少しずつ積み上げていけるようにすることです。
【関連記事】母子登校の背景にある5つの要因と、育てたい非認知能力 – みちびき | 伸びゆく力を共に育む、親子のみちしるべ
要点
- 「どうせできない」という思い込み+失敗回避のパターンが、挑戦を止めている
- プロセス承認 → 捉え直し(リフレーミング) → 小さな成功の連続で、自己効力感を育てる
- 叱咤や説得よりも、”本人が気づく設計”が効果的
基本の考え方
- できた事実を認める
- 捉え直し(リフレーミング)
- 小さな成功を設計して積む
それぞれを具体的に見ていきましょう。
兆候チェック|こんな様子が続いたら要注意

お子さんに次のような様子が見られるでしょうか。
- 宿題・係・発表などで先送り/回避が増えている
- 「無理」「どうせ」「また失敗する」という口ぐせがある
- 失敗直後の自己否定(全か無か思考)が強い
- 褒められても受け取れない/他の子と比較にすり替える
ポイント: 1つだけなら普通の揺らぎの範囲内です。しかし、2〜3項目が連続して続いている場合は、注意が必要かもしれません。
2. 背景メカニズムをシンプルに理解する

なぜお子さんは「どうせできない」と感じてしまうのでしょうか。背景には次のようなメカニズムがあります。
学習された無力感(学習性無力感)
努力と結果の手応えが感じられない経験が続くと、「何をしても変わらない」という無力感を学習してしまいます。
安全志向の強化
失敗を避けることで短期的には安心できますが、経験は貯まりません。その結果、挑戦しないことが習慣化してしまいます。
評価不安
他者との比較や完璧主義が強いと、着手する前から自己防衛として「やらない選択」をしてしまいます。他者との比較がプラスに働くこともありますが、過度な比較は自信を喪失してしまう流れになることは理解しておきたいところです。
伸ばしたい非認知能力

この記事では、次の2つの力を育てることを目指します。
🔴自分と向き合う力
自分の感情(不安・怖さ)を受け止め、言語化し、前向きに捉え直す力です。
自分のプラスの感情と向き合うことは早退変ではありませんが、マイナスの感情と向き合うことは大変に感じることも多いです。しかし、それを受け止めることができるようになってくると、自然と前向きに捉え直す力を身につけることができていきます。
🔴自分を高める力
小さな成功を積み重ね、自己効力感を育てる力。つまり「できる」という見通しを実感する力です。
親御さんがすべてお膳立てして小さな成功を積み重ねていくことはできますが、それよりもお子さん自身が自分の力で成功を勝ち取る経験をする方が得られるものが多いでしょう。
基本方針:3ステップの流れ
ステップ1|できた事実を認める
毎日でなくて構いませんから、まずはお子さんができたことをしっかり認めてあげましょう。年齢的にできて当たり前のことを褒めると逆効果になることもありますので、お子さんが苦手なことやできなかったことができた時にしっかり認めてあげましょう。
例:学校の準備を親御さんから言われなくても自ら進んでできた時
「お母さんが言わなくても準備ができたわね。明日の朝慌てなくて済みそうね。」
ステップ2|失敗を”材料”として捉え直す
失敗をすると誰でもショックを受けると思います。また、子どもの知る世界は狭いですから大人以上に悲観的に受け取ってしまうこともあるでしょう。そんな時に、その失敗も経験する価値があったと教えてもらうと子ども達の価値観が変わってくる可能性が出てきます。
合言葉: 「できない方法が分かったわね。」
NG言葉:「なんでできないの?」→これは責めにつながり、思考を固定化させます。失敗しないように挑戦すらしなくなってしまいます。
ステップ3|小さな成功を設計して積む
大きな目標を掲げるのも大事ですが、なかなか達成しないと諦めてしまいがちです。目標到達まで細分化してあげると小さな成功を積み重ねていくことができます。
例:母子登校をしているお子さんに対して
大きな目標として“1人で登校できるようになる”を掲げ、その手前の段階で“教室の外でお母さんと離れる”→“お母さんの付き添いは下駄箱まで”→“付き添いは校門まで”→・・・
という流れでできることを一つずつ着実に進めます。
学校との連携
配慮は”具体的”に
学校への依頼は、できるだけ具体的に。
例:授業中に当たるのが嫌だという子に対する配慮
🔴指名して当てるのをしばらくの間やめてもらう
🔴座席や出席番号順などで当たるものに関しては子どもが頑張る
指名して当てられるのは突然のことなので嫌がる子どもは多いです。しかし、座席などで順番に当たるものに関してはその子だけ飛ばしてしまうと悪目立ちしてしまうでしょう。お子さんの学校で過ごす様子をより具体的にイメージしながら、どんなサポートがあると安心なのかを一緒に考えていけるといいでしょう。
ケース例(Before→After)
Before
テストが怖くて勉強を開始できない。「無理」と言って机から離れてしまう。
介入
- 5分だけ取り組む → 途中でやめてもOK
- 終わったら「できた事実」をカレンダーに(視覚化)
- 定着してきたら次のステップ(5分→10分など)
After(3週間後)
親から言わなくても自ら勉強するように。勉強する時間も少しずつ増えてきました。
避けたいNG対応(よくやりがち)
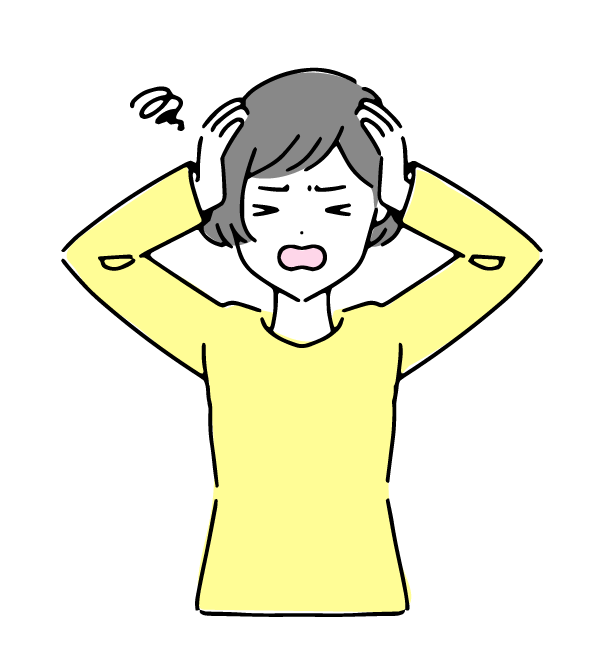
次のような対応は逆効果になりがちです。
- 「やればできる!」という根拠のない励ましのみ
- 成果だけを褒めて、着手や工夫を拾わない
- 比較(きょうだい・友達)やラベリング(「怠け者」等)
- 親が先回りして全部整える(本人の手応えが消える)
ミニワーク|そのまま使えるシート
できたことを親が認める
子どもが過去にできていなかったこと等ができていた場合、親御さんがしっかり認めてあげる対応をしましょう。自己肯定感が低いお子さんは、自分でできていることを忘れてしまいがちな傾向が見られます。頑張った点や工夫が見られた点なども一緒に認めてあげながら思い出させていきましょう。
親御さんが見てくれていることが分かると、子どもは安心しますし「また頑張ろう」などと前向きに捉えるきっかけになります。
リフレーミング表
| 元の言葉 | 捉え直し |
|---|---|
| できない | 「今はまだ。やり方を変えてみよう」 |
| 失敗した | 「材料が1つ増えた」 |
自己効力感スケール(0–10)
週末に自己採点し、変化を見える化します。
見える化することで、言葉では「不安」や「怖い」という見えない指標が見えるようになっていきます。学校に向かう気持ちに変化がみられるのか、変化が見られた場合はどのようなことをしたからなのかが分かっていくとお子さんも自分自身を理解するきっかけになっていきます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 褒めるのが苦手です。何を言えばいいですか?
A. 褒めることが難しいと感じる場合は、認めてあげると捉えましょう。事実→努力→工夫の順で、短く具体的に伝えるとよいでしょう。
例: 「3分座れたね」「自分でタイマー押せたね」
Q2. 小さくすると甘やかしになりませんか?
A. 甘やかしは「代わりにやること」です。小さくするのは、本人の成功確率を上げる設計です。
Q3. 続けられません。
A. すべてを完璧にこなす必要はないでしょう。まずはご自身ができそうなこと1つから始めるのが肝要です。慣れてきたら少しずつ増やしていくと無理なく続けられると思います。
まとめ|今日の一歩

自己肯定感を上げるというのは簡単ではありません。しかし、日々の生活の中で少しずつ培うことはできます。
プロセス承認 → 捉え直し → 小さな成功で、自己肯定感・自己効力感は”積み上げ型”で育ちます。
まずは今日できたことを親御さんが認めてあげるところから始めてみませんか。
伴走が必要な方へ
一人で進めるのが難しい、専門的なサポートが必要だと感じた方は、まずはご相談ください。
お子さんはまだまだ成長過程です。お子さんの小さな一歩が、大きな自信につながりますように。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














