母子登校の背景にある5つの要因と、育てたい非認知能力
- 2025/09/22
- 2025/10/21

「『ママがいないと学校に行けない』。朝になっても一人で教室に入れない――。
これは甘えやわがままではなく、子どもに”まだ育ちきっていない力(非認知能力)”があるサインかもしれません。
母子登校の背景を整理しつつ、どの非認知能力が不足しやすいのかを見ていきましょう。」
母子登校に潜む5つの背景要因
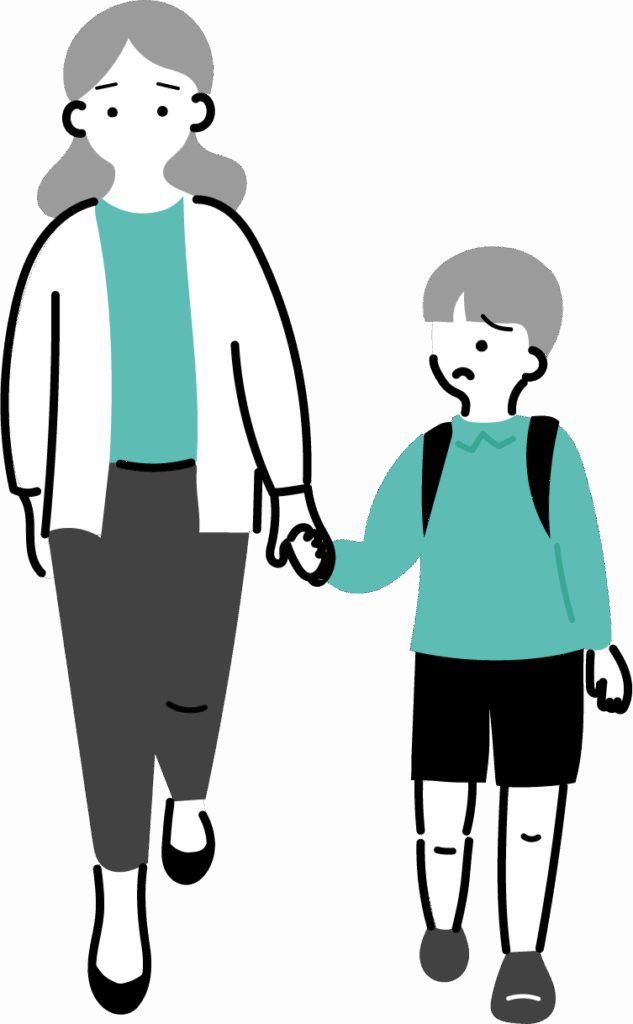
1. 分離不安・親子依存
親から離れることへの強い不安が根底にある状態です。「一人で大丈夫」という経験が少なく、親の存在が心の安全基地として必要不可欠になってしまっています。
伸ばしたい非認知能力
🔴自分と向き合う力 → 不安や緊張を自分でコントロールする自己調整力
🔴自分を高める力 → 新しいことに挑戦する勇気
要点
別れの不安は「感情を落ち着かせる・場面を切り替える・先が見える」の力がまだ育ち途中というサイン。
基本の考え方
親子で一緒に整える → 小さく着手 → 成功体験を積む、の順で進める。
母子登校の「分離不安・親子依存」|家庭でできる対策5選(非認知能力で支える) – みちびき | 伸びゆく力を共に育む、親子のみちしるべ
2. 学校生活への不安(対人・学業)
友達との関係が不安定だったり、授業についていけない不安、先生との相性によるトラブルなど、学校という環境そのものに対する不安が強い状態です。
伸ばしたい非認知能力
🔴他者とつながる力 → 人に頼る力、助けを求める力、協調性
🔴自分を高める力 → 困難に立ち向かう粘り強さ
要点
不安の源は「人間関係・学び・環境」のどこか(複数可)。正体が曖昧なほど不安は増幅する。
基本の考え方
原因を分けて見つける(人/学び/環境) → 一手ずつ調整(席・課題・関わり方) → 校内では「先生に相談」で対処を選ぶ。
学校生活への不安が母子登校を招くとき|親ができる対応と育てたい力 – みちびき | 伸びゆく力を共に育む、親子のみちしるべ
3. 自己肯定感の低さ
「どうせ自分はできない」と思い込んでしまい、挑戦から逃げる傾向があります。失敗への恐怖心が強く、新しいことに踏み出せない状態です。
伸ばしたい非認知能力
🔴自分と向き合う力 → 自分の感情を受け止め、前向きに捉え直す力
🔴自分を高める力 → 小さな成功から自信を積み上げる自己効力感
要点
「どうせできない」という思い込みと失敗回避が挑戦を止める。
基本の考え方
できた事実を可視化 → 失敗を「チャンス」と捉える力 → 小さな成功で自己効力感を積む。
自己肯定感の低さで挑戦できないとき|「どうせできない」を外す3ステップと家庭での実践 – みちびき | 伸びゆく力を共に育む、親子のみちしるべ
4. 家庭環境の影響
親が「一緒じゃないとかわいそう」と思い込んでしまい、結果的に依存関係が強まってしまうケースです。過干渉や家庭内の不安定さも影響することがあります。
伸ばしたい非認知能力
🔴自分と向き合う力 → 自分の気持ちを言葉で伝える表現力
🔴他者とつながる力 → 自立した人間関係を築く力
要点
過度な先回りや不安定な家庭リズムは、自律の練習機会を削る。
基本の考え方
子の発信を待つ → 役割と境界を明確化 → 親は「分からないことは説明 → 見守り → 必要時のみ手助け」に絞る。
家庭環境の影響で母子登校が続くとき|「待つ→境界→最小手助け」で自立を育てる – みちびき | 伸びゆく力を共に育む、親子のみちしるべ
5. 発達特性・心身の不調
敏感気質(HSC)や発達特性によって環境への適応が難しかったり、朝の切り替えが苦手な場合があります。身体症状が登校の壁になることもあります。
伸ばしたい非認知能力
🔴自分と向き合う力 → ストレスマネジメント力
🔴自分を高める力 → 生活習慣を調整する自己管理力
要点
特性や体調と環境のミスマッチが、朝の切替を難しくする。
基本の考え方
体から整える(睡眠・水分・光) → 道具・手順・時間で環境調整 → 必要に応じて専門家と連携。
親ができる第一歩
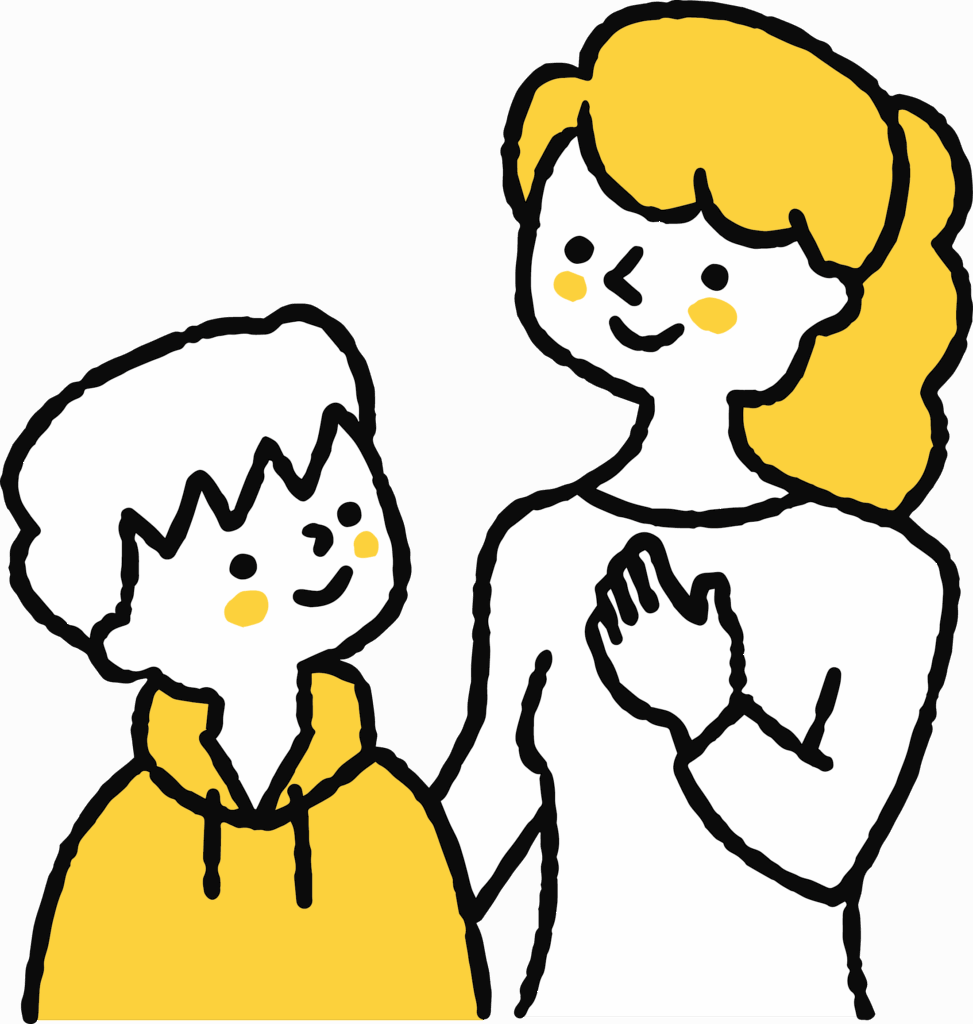
母子登校の状況に直面したとき、親として大切なのは視点を変えることです。
「どうしてできないの?」と責めるのではなく、足りない力を一緒に育てる視点を持つこと。母子登校は“依存”ではなく“未発達な力の表れ”として捉えることで、建設的なアプローチが可能になります。
小さな成功体験を積み重ねることが、自立への第一歩になります。子どもが「できた!」と感じられる場面を意識的に作り出し、その瞬間を一緒に喜び、認めてあげることが重要です。
登校動線の段階表

ルートA:いま教室まで同伴している場合
母子登校のケースの中には、教室の中まで親御さんが付き添っているというケースもあります。
このケースの場合はまず教室からお母さんが出るところからチャレンジしてみるといいでしょう。お母さんが居なくても大丈夫なシーンがあるはずですので、そこを狙って挑戦してみると上手くいきやすいでしょう。
- 教室内でお母さんが離れる時間を増やす
- 教室前で別れる
- 廊下まで
- 下駄箱まで
- 校門まで
- 学校の角まで
- 家の前まで
- 玄関で別れる
ルートB:学校で別れているが朝の切替が難しい場合(「到達点」を刻む)
教室までは入る必要はないけれど、学校までは付き添わなければ学校に行けないケースです。母子登校の中でも一番多いケースと言えるでしょう。
- 教室前
- 下駄箱
- 校門
- 公園の角など
- 家の前
- 玄関で別れる
進め方のルール
- 2~3日連続で達成 → 1段アップ
- 難しかった日は1段戻す(長居せず短時間で成功に着地)
- 達成基準(どれかでOK):着手できた/不安な時は「先生に相談」で切替
ここでは大きく2つのケースを挙げましたが、どちらにも言えることとしては“小さな目標を設定しながら焦らず、着実に進める”ということです。
「いつまでこの状態を続けるのだろう・・・」などと不安に思われるお気持ちや、周りのお子さん達と比べてしまい「早くしなくちゃ!」と焦ってしまうお気持ちはよく理解できます。しかし、焦ってしまうとより状況が悪化してしまうことが多いので、焦らず着実に前に進めていくことを意識していただければと思います。
まとめ

母子登校の背景には、非認知能力の不足が隠れているケースが多いです。
家庭教育の視点から、子どもと一緒に”力を育てる”関わりを意識することで、少しずつ『一人で行ける力』につながっていきます。
焦らず、責めず、一歩ずつ。子どもの成長に寄り添いながら、必要な力を育てていくことが、真の解決への道筋となるでしょう。
みちびきの伴走サポート
「どの段階から始めればいい?」「先生への伝え方は?」など、各家庭の状況に合わせて非認知能力を伸ばす声かけ・手順をご提案します。
みちびきの支援の特徴としては、
将来を見据えた支援
今日をしのぐだけでなく、感情の整え方・切り替え方・小さく始める力を育て、学校以外でも自力で回復できる土台をつくります。
性格傾向に合わせた“親の動き方”
気質・特性(不安の強さ、こだわり、刺激への敏感さ 等)に合わせて、声かけ・環境・ルールをアドバイスします。
経験者の知恵とケース横断の視点
現場で積み上げた多数のケースを横断し、再現性のある具体策を提供します。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














