学校生活への不安が母子登校を招くとき|親ができる対応と育てたい力
- 2025/09/30
- 2025/09/29

「友達関係が不安定で心配」「授業についていけない」「先生と合わない」——。学校という環境そのものに不安を抱える子どもは少なくありません。この不安が積み重なることで、母親と一緒でなければ登校できない「母子登校」につながることがあります。
本記事では、学校生活への不安が母子登校に影響する理由と、親ができる関わり方を解説します。
要点
- 学校生活の不安は 人間関係・学習・環境 の3つに整理できる。
- 不安の正体が曖昧なほど気持ちは増幅し、母子登校につながりやすい。
- 他者とつながる力(人に頼る・助けを求める)と、困難に立ち向かう粘り強さを少しずつ育むことが重要。
- 親が全て解決せず、子ども自身が「人を頼れる経験」を積むことが自立への第一歩。
基本の考え方
- まず不安の源を「人・学び・環境」に分けて明確化する。
- 優先順位をつけ、一つずつ小さく調整する(席替え・宿題調整など)。
- 校内では「先生に相談する」経験を積ませることがゴール。
- 最初は親が付き添ってもよく、やがて子ども自身が「学校には助けてくれる人がいる」と実感できるように導く。
学校生活への不安とは?
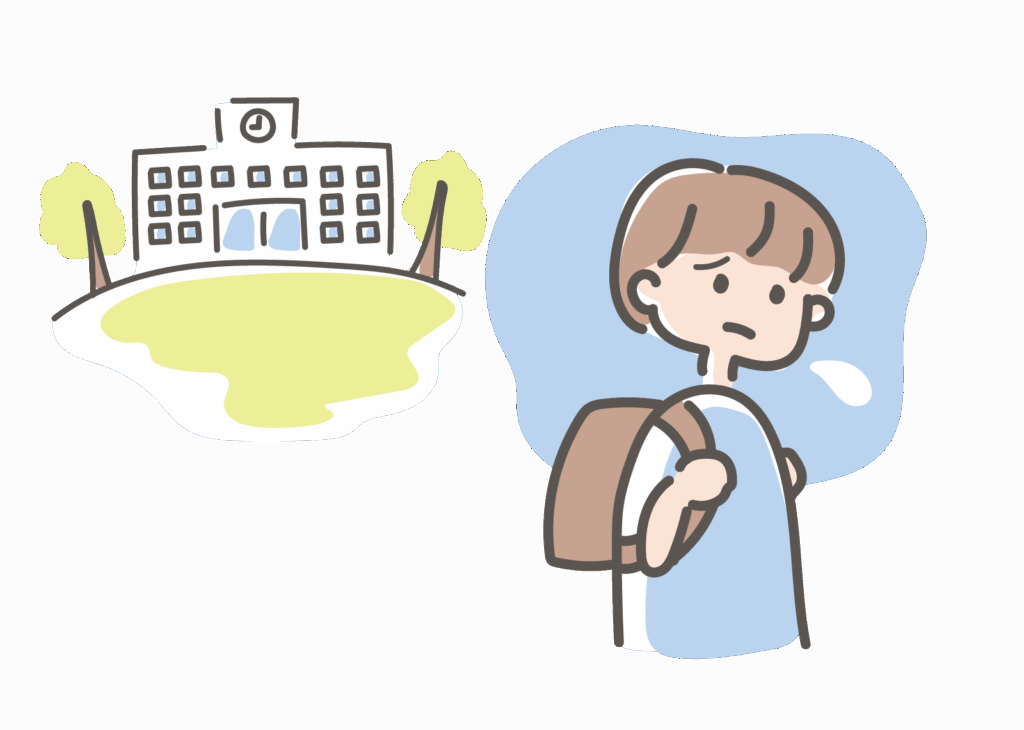
学校生活の不安には大きく3つの源があります。
人間関係の不安
友達とのトラブルや孤立感、グループに入れない不安など、対人関係に関する心配事です。
学習面の不安
授業についていけない、テストの結果が怖い、発表が苦手など、勉強に関連する不安です。
環境面の不安
先生との相性、教室の雰囲気、騒がしさ、校舎の構造など、物理的・心理的環境への不安です。
不安の正体が曖昧なほど、子どもの気持ちは増幅しやすく、母親と一緒でないと安心できない状態に結びつきます。
伸ばしたい非認知能力

母子登校からの自立を目指すには、子どもの中に次の力を少しずつ育んでいくことが大切です。
他者とつながる力
🔴人に頼る力
🔴助けを求める力
🔴協調性
親以外の人を頼る練習が要になっていきます。学校で困ったことがあれば基本的には学校の先生とお子さんとで解決できるようにサポートしてあげましょう。もちろん、すぐにできるわけではありませんから親御さんが仲介人となりサポートしてあげることは状況によっては問題ありません。しかし、親御さんだけでお子さんの問題をすべて解決してしまうと、お子さんが他者とつながる力を培う機会が削がれてしまいます。
自分を高める力
🔴困難に立ち向かう粘り強さ
これらの力は一朝一夕では身につきませんが、日々の小さな経験の積み重ねによって少しずつ育まれていきます。特にお子さんが失敗したときに責めるような対応をしないでおきたいものです。失敗したときに「できない方法が分かったわね。」とプラスに捉えていきましょう。
親ができる基本の考え方
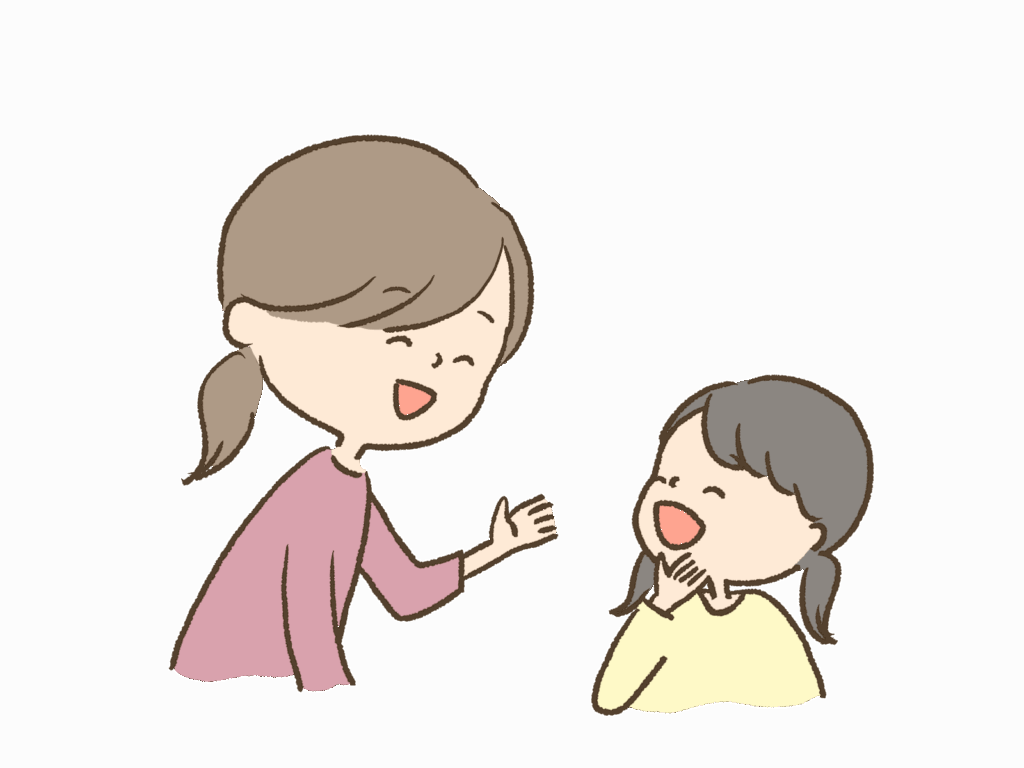
1. 不安の源を分けて探す
「人間関係」「学び」「環境」のどこに不安があるか整理してみましょう。子どもとの対話を通じて、具体的に何が心配なのかを明確にすることが第一歩です。
2. 一つずつ調整する
- 席の位置を変えてもらう
- 宿題や課題の量を調整する
- 学校内での問題を先生に相談する
ここに挙げたのは一つの例ですが、すべてを一度に解決しようとせず、優先順位をつけて段階的に取り組むことが重要です。また、親御さんがすべてを解決する必要はありません。お子さん自らの手で解決していけるよう手助けしてあげるとよいでしょう。
3. 「校内で助けを求める」経験を増やす
親が先回りして解決するのではなく、担任やスクールカウンセラーなど「学校の人に相談する」体験を積み重ねることが、自立への第一歩です。
最初は親が付き添っても構いません。大切なのは、子ども自身が「学校には助けてくれる人がいる」という安心感を体験することです。また、“先生に相談する”と一言で言っても、それに慣れていない子ども達にとってはとても緊張します。どのタイミングで先生に声をかけるのか?先生にどう言えばいいのか?など細かく確認してあげると安心するでしょう。
具体的な関わり方のポイント

家庭でできること
🔴子どもの話を最後まで聞く
🔴不安な気持ちを否定せず受け止める
🔴小さな成功体験を認めて褒める
「こうしなきゃ!」などと我々大人は容易に考えることができますが、そのせいで子どもにあれこれ言い過ぎてしまうことは往々にしてあります。まず第一にお子さんの話をしっかり聴いてあげましょう。お子さんが不安を口にした際に「大丈夫」とすぐに言ってしまいやすいですが、まずはその不安な気持ちを「そうだね、不安なんだね。」と受け止めてあげましょう。その上で、どうしたらいいのか等を一緒に考える練習を家庭でしていけるとよいでしょう。
また、家庭ではお子さんができたことに着目し小さなことでも一緒に喜んであげると子どもも自信を持てるようになってきます。これまで当たり前にできていることを褒めると「バカにされている」と捉える子もいますので、気を付けたいところです。
学校との連携
🔵担任との定期的な情報交換
🔵子どもの特性や配慮事項の共有
🔵段階的な目標設定と評価
学校では親以外の大人と関わるチャンスがたくさんあります。上記でも書いたように、親御さんがお子さんの困りごとをすべて解決してあげるのではなく、少しずつで構いませんからお子さんが親以外の人を頼れる練習をさせていきましょう。担任の先生にも事情を説明しておくと協力してくださることもあります。
まとめ
学校生活への不安は、母子登校の背景としてよく見られる要因の一つです。親ができるのは「不安を整理する手伝い」と「小さな解決体験を積ませること」。そのプロセスの中で、他者とつながる力や困難に向き合う力が少しずつ育まれていきます。
母子登校は「依存」ではなく「安心を確かめるための行動」です。子どもなりの対処法として理解し、批判せずに受け止めることから始めましょう。
安心の土台を広げる関わりを、家庭と学校の両輪で進めていくことで、子どもは徐々に自分の力で学校生活を送れるようになっていきます。焦らず、子どものペースに合わせて、温かく見守り続けることが何より大切です。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














