母子登校の「分離不安・親子依存」|家庭でできる対策5選(非認知能力で支える)
- 2025/09/25
- 2025/09/29
[関連記事]母子登校の背景5要因と、育てたい非認知能力(全体像)

「ママがいないと教室に入れない」「別れ際に大泣きして進めない」。
これは“甘え”ではなく、感情を落ち着かせる/場面を切り替える/先が見えるといった力(=非認知能力)がまだ育ち途中であるサインかもしれません。
ここでは、家庭で今日からできる最小の一歩を具体的にまとめます。
要点
- 決めた手順を毎日同じに——“変わらない合図”が安心と切り替えを支える。
- 第一歩は仕組み化:別れの儀式30–60秒/週次の見通しメモ/安心アイテムは1つ。
- 朝は短く・同じ手順:交渉を延ばさず、“今日は特別”を重ねない。
- 育てたい力:自己調整力+一歩踏み出す力。難しい日は1段階下げて短く成功。
- 頼る軸の移行:親→学校へ。先生に相談できる体験を増やす。
基本の考え方
- 手順固定:内容は何でもOK、毎日同じ順番で。
- 見える化:冷蔵庫に1週間の段階表。朝は確認のみ、1–2週で見直し。
- 安心のミニ装備:必要な子だけ1アイテム、慣れたらフェードアウト。
- 感情が荒れたら距離を取り「落ち着いたら戻る」。声かけは最小限。
- 小さく検証:木・金は維持、崩れる日は1段階下げる。
家庭でできる第一歩(3つ)
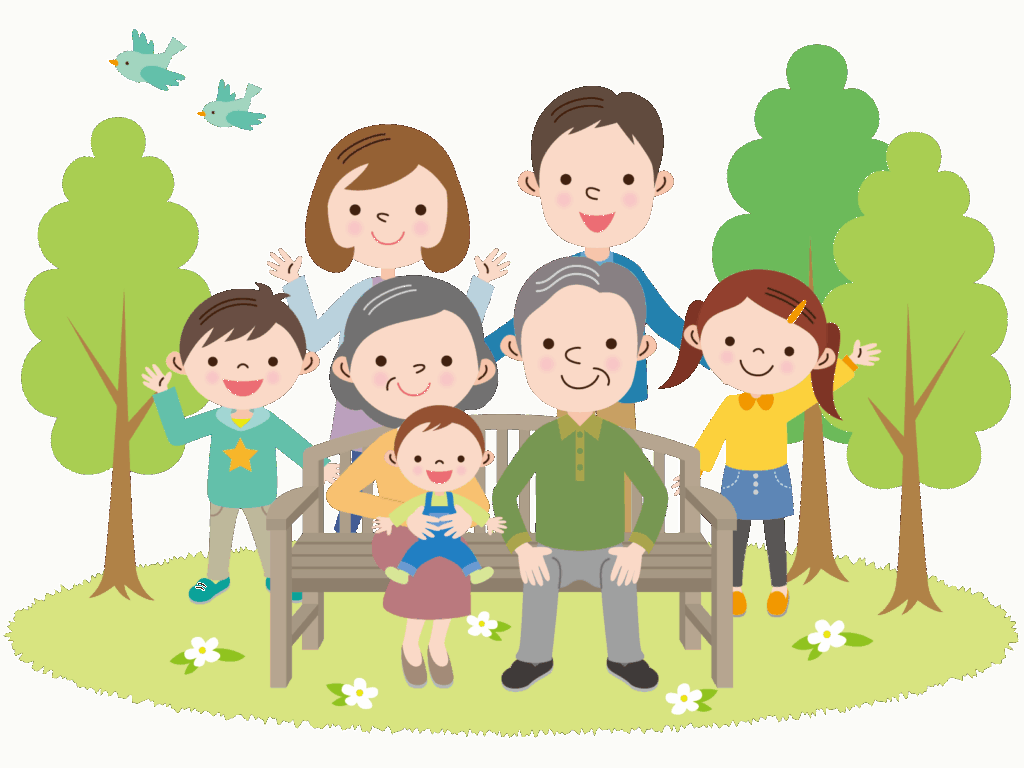
① 別れの「儀式」は見直すだけでOK
ねらい:毎朝の不確実さを“同じ手順”に置き換えて不安を下げる。
やり方例:(30〜60秒・毎日同じ)
- 深呼吸を1回する
- ハイタッチ
- 合言葉(例:「合図はハイタッチ、会うのは帰ってから」「今日は1限だけ作戦」)
- 親は振り返らずに離れる
NG:交渉を長引かせる/“今日は特別”の積み重ね
② 見通しは計画メモでOK
子どもは、「どれだけ頑張ればいいか分からない」という先が見えない不安を抱えやすいものです。逆を言うと、先が見えると不安は下がるということです。家のメモ用紙・ホワイトボード・チラシの裏・親のスマホなど、文字で可視化すると理解が早いでしょう。
運用:1週間などざっくりで構わないので見通し(計画)を立てていきましょう。
毎朝「どうする?」と聞くのも大変ですし、朝の不安な時間に子どもを更に不安にさせるような流れは避けたいところ。親子で確認できるようにリビングや冷蔵庫などに貼っておくと子どもが気になったときに自分で確認できるようにしておけるといいですね。
書き方例:
- 今週は教室の前までお母さんについてきてもらう
- 来週は学校の下駄箱まで
- 翌週は校門前まで・・・
③ 安心アイテム(必要な子は1つだけ)
母子登校を経験している子ども達の中には、頑張りたい気持ちはあるけれどもお母さんと離れると急に不安になるということが多いです。(だから母子登校をしているわけなんですけどね・・・😅)お母さんの身代わりではないですが、お母さんの代わりになるような安心できる物が実際にあると安心感を得られるお子さんもいます。お守りのようなイメージを想像していただければと思います。
絶対必要という話ではありませんから、お子さんが「あった方がいい」と思う場合は学校に持っていける範囲にはなりますが用意するのも一つでしょう。
例:小さなハンカチ/触感グッズ/短いメッセージ紙片。
フェードアウト:親御さんの居ない学校生活に慣れてくれば、自然と子どもがお守りのことを気にしなくなっていきますので、それまでは任せておきましょう。
伸ばしたい非認知能力と上げ方
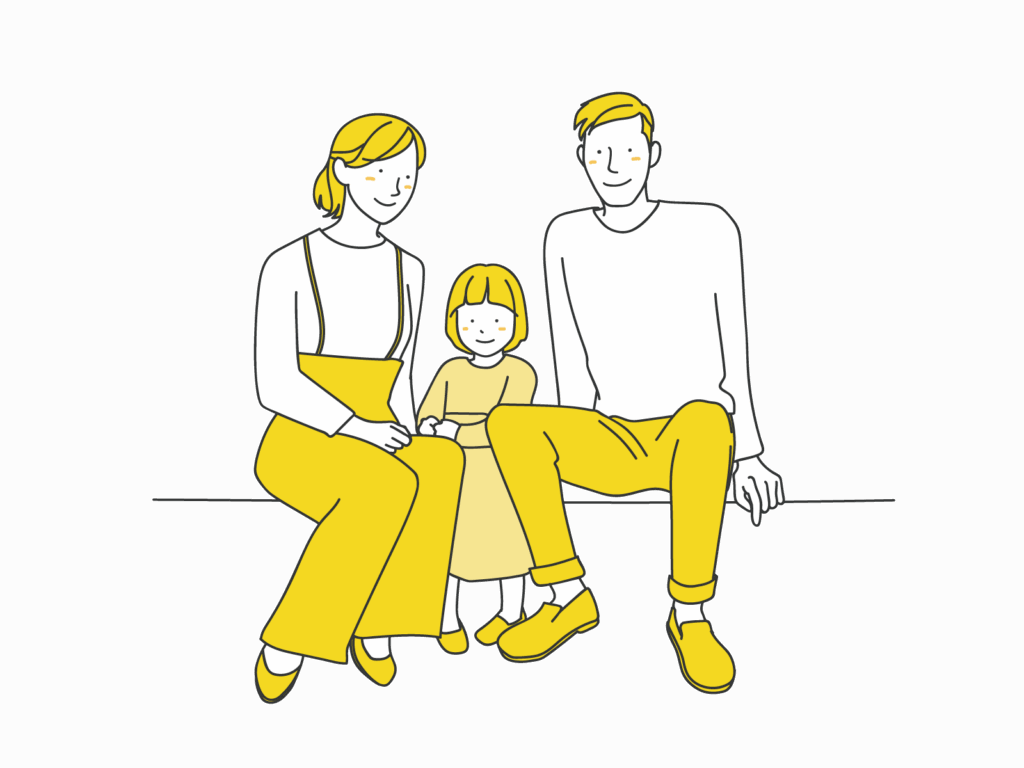
1.自分と向き合う力 → 自己調整力(不安・緊張を自分で下げる)
ねらい:子どもが自分の力で落ち着きを取り戻す。親は“場を整えて待つ”。
家庭での実践:子どもに自分と向き合う時間を与える
子どもがイライラしたり癇癪を起したりすると、親としては何とかして落ち着かせなきゃと焦ってしまう親御さんもいらっしゃるかもしれません。しかし、不要に親御さんから声をかけてしまうと余計に親への甘えが強くなり状況が酷くなっていくことは多いです。
子どもが癇癪やイライラを起こした場合は、極力親御さんはその場から離れて様子を見ていきましょう。
子どもにとって甘えられる存在になり易いお母さんは特に、お子さんの目の前に居ない方が落ち着くことが多いと言えます。ただ、親御さんが離れようとすると必死に子どもが親御さんにしがみついて阻止しようとしてくることもあります。その場合は、「落ち着いてお話ができるようになったら戻ってくるわ」などと必ず戻ってくるという話をして離れてみるといいでしょう。
親御さんが子どもと距離を取ることで、子どもは自分の感情と向き合う時間ができます。
2. 自分を高める力 → 新しいことに挑戦する勇気
ねらい:「やれない」から“まず一歩”へ。始めやすい仕組みを先に置く。
家庭での実践:子どもに自分と向き合う時間を与える
声かけの置き換え例(NG→OK)

母子登校のケースのでは、学校のある朝の対応は親御さんにとっても負担が大きいものです。焦りや不安や疲労感が募ると子どもに対してつい言いたくない言葉をかけてしまうこともあります。感情をそのまま子どもにぶつけてしまうとその傾向が強くなりますので、一旦心の中で言葉の変換ができる余裕があるといいでしょう。
すぐにできなくても問題ありません。人間はそんなものです。(お恥ずかしい話ですが、私も感情的になってしまうことはあります😇)「言っちゃいました・・・」とショックを受けられる親御さんが多いですが、まずはそこに気づけたという事実が大事です。気づかなければ発言や行動を変えることはできません。少しずつ、トライしてみてください。
- 「泣かないで、早く行って」
→ 「深呼吸1回して、合図でいこう」 - 「今日は絶対に教室まで行くよ」
→ 「不安な気持ちは分かるよ。(共感)でも、立てた目標を達成できたらかっこいいよね。(親の意見)」 - 「できないなら休むしかないでしょ」
→ 「難しかったら学校まで行って、先生と相談してみようか。」
よくあるつまずきと対処
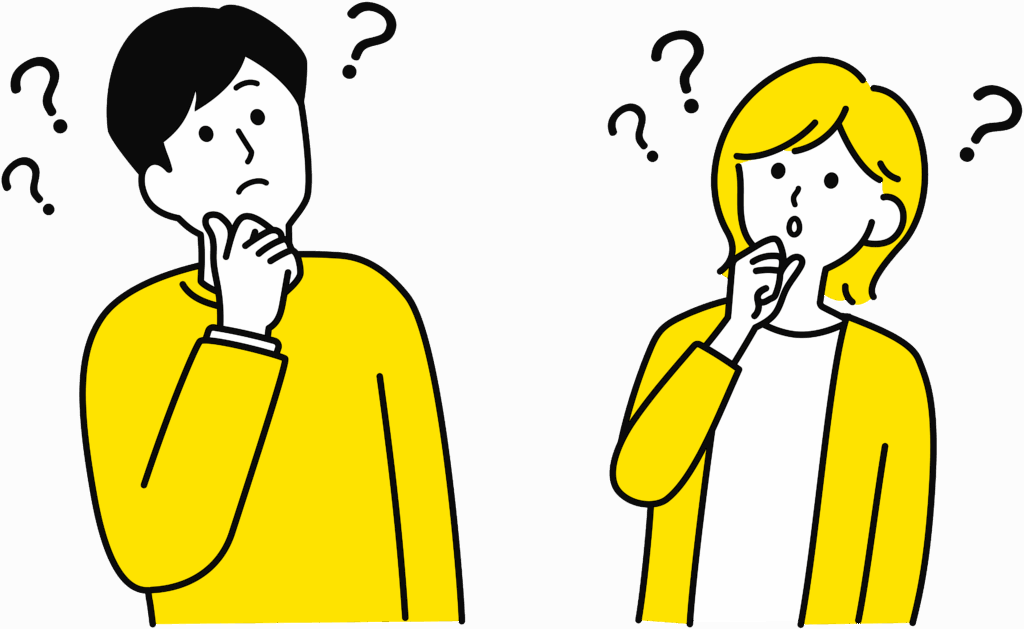
母子登校の現場では、目の前で我が子が泣き喚くこともあり親御さんにとってはダメージが大きいと言えます。「こんなに泣くぐらいなら学校に行かなくてもいいんじゃないだろうか・・・」と追い詰められるとそんな思いが出てくることもあります。
我々も学校がすべてとは考えていませんが、親御さんと話す中で“子ども達の将来を考えてどうしていくのがいいのか”という点に戻って対応面を考えます。
支援を進める中で親御さんが迷われる点を挙げてみました。
- 週の後半で崩れる:木・金は段階を上げない。維持でOK。
- 泣きが長引く:その日は1段下げて短く成功で終える/少し距離をとって見守る(子の視界に入りつつ、言葉掛けは最小限)。
まとめ

分離不安・親子依存は、自己調整力・切替力・見通し力を育てていく過程で自然と軽くなります。
整える → 小さく着手 → 成功体験を積み上げていきましょう。何よりも親御さん側が“焦り過ぎない”ということは母子登校の対応では大事になってきます。
学校に行けば困ることや心配事は出てきますので、基本的に学校内のことは「先生に相談」という流れにしておきたいです。お子さん自身が“親以外の人を頼れる力”を身につけてもらいたいですから、最初は親御さんのサポートを入れつつも次第に子どもだけでも誰かを頼れる環境は作っていきたいですね。
この“しくみ”が、子どもの「自分で行ける力」に変わっていきます。
みちびきの伴走サポート
「どの段階から始めればいい?」「先生への伝え方は?」など、各家庭の状況に合わせて非認知能力を伸ばす声かけ・手順をご提案します。
みちびきの支援の特徴としては、
将来を見据えた支援
今日をしのぐだけでなく、感情の整え方・切り替え方・小さく始める力を育て、学校以外でも自力で回復できる土台をつくります。
性格傾向に合わせた“親の動き方”
気質・特性(不安の強さ、こだわり、刺激への敏感さ 等)に合わせて、声かけ・環境・ルールをカスタムします。
経験者の知恵とケース横断の視点
現場で積み上げた多数のケースを横断し、再現性のある具体策を提供します。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














