【支援事例】“母子登校”を卒業できた日——子どもが自分の足で歩き出すまでの物語
- 2025/08/15
- 2025/08/13
母子登校で悩む親御さんは実はみなさんが思っておられるよりも多いと思います。不登校の数は文部科学省でも毎年数値化されていますが、母子登校のケースまで数値化することは殆どありません。
しかし、実際の現場の感覚としては母子登校に悩まれる親御さんは非常に多いと感じています。
ですが、その数と同等の相談があると言われるとそうではないのが現状です・・・。そうなる理由はご家庭それぞれ異なり、理由も様々ですが世間的に「学校に行けているのだからマシでしょう」という風潮も母子登校をされている親御さんの心的負担になっていることは確かです。
今回のブログ記事では、母子登校で悩む親御さんだけでなく母子登校を知らない方にも現状を知っていただきたいなと思いまとめました。世間的な風潮がいい方向に変わるといいなという想いと、母子登校で悩まれる親御さんが気軽に相談する場が増えるといいなと想いながら綴りたいと思います。
「このままでいいのか」と悩んでいたあの頃
「母子登校が続いています。いつまでこうしていくべきなのか…」
支援をスタートされたとき、お母さんはそう語っていました。学校には行けているけれど、常に親の付き添いが必要な状態。不安と責任感の中で、日々をどう乗り越えるかに悩まれていたご様子が、今でも印象に残っています。
「行けてるんだから問題ないのでは」という周囲の声と、心の奥底で感じる「でも、これでいいのかな」という違和感。そのはざまで揺れ動く親心を、私たちは数多く見てきました。
1. 支援開始前の状況|”通えてはいるけど”という苦しさ
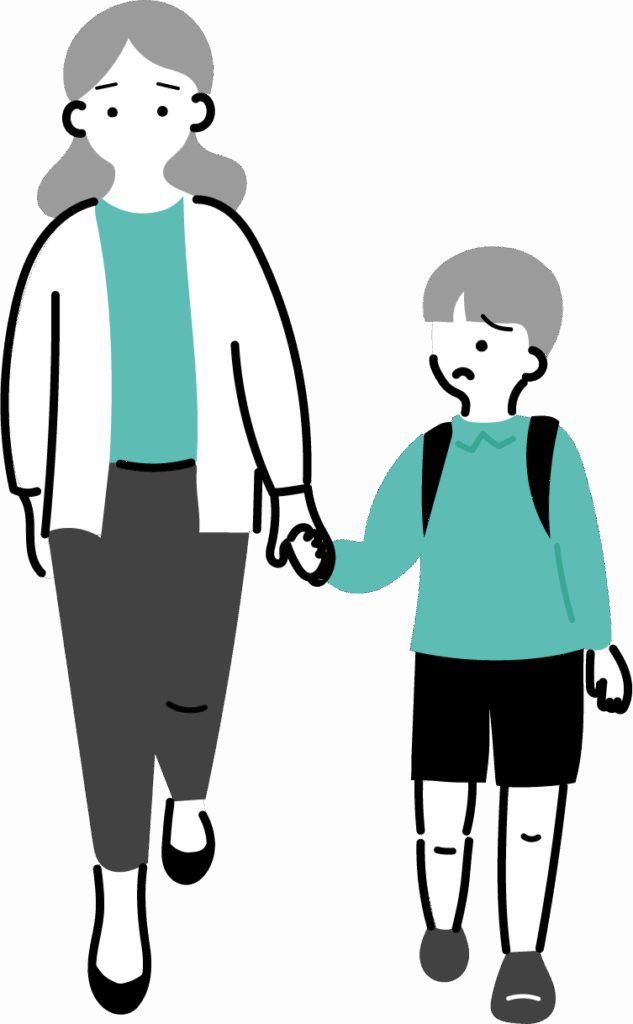
このご家庭のお子さんは小学生でした。母子登校の状態が続き、本人は学校に入れるけれどひとりで行くことは難しい状況。お母さんも「無理に一人で行かせるのは違う気がする」と悩みつつ、どうしてよいか分からずにいました。
「行けてるんだから問題ないのでは」という周囲の声に、母親自身も戸惑っていました。でも、毎朝の付き添いが日常になり、お母さん自身の生活も制約される中で、「このままでいいのか」という思いが日に日に強くなっていったのです。
支援者として感じたのは、”不登校”ではなくても、”親子で苦しい登校”は支援対象になりうるということでした。
表面的には「学校に行けている」状況でも、その背景にある親子の葛藤や将来への不安は、決して軽視できるものではありません。
2. 支援で取り組んだこと|”できた”を親が手放すプロセス

最初に整理したのは、「母子登校を続けることが目的ではない」という意識でした。お母さんが付き添う理由や不安を一緒に言語化し、手放せる準備を始めました。
もしかすると、この記事を読んでくださっている方からすれば「そんなこと母子登校で悩んでる親なら当たり前の事じゃない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。おっしゃる通りではありますが、この支援を受ける目標や目的を事前に親御さんと共有しておくことは、想像以上に大きな意味があります。
なぜなら、目的が曖昧なまま支援を始めると、日々の関わりや対応の方向性がバラつき、親御さん自身の意識も安定しにくくなるからです。
一方で、最初に「どこを目指すのか」を明確に共有できている家庭は、支援中の迷いが少なく、行動も一貫しやすくなります。
この“最初の共有”があるかないかで、その後の家庭の変化や子どもの変化のスピードが大きく変わる――これはこれまでの支援現場で繰り返し実感してきたことです。
そして、日々のやり取りや声かけを記録してもらい、親子の依存を少しずつほぐすサポートを開始。「今日の振り返り」や「小さなチャレンジ」の設計を共有しながら、段階的に自立への道筋を描いていきました。
印象的だったのは、お母さんが”自分がいなくても大丈夫になる日”を目指して行動を変えてくださったことでした。
「今日は校門まで」「今日は教室の入り口まで」といった具体的な目標を設定し、子どもの様子を見ながら調整を重ねました。時には後退することもありましたが、それも含めて「プロセス」として捉えることの大切さを、お母さんと共有していきました。
3. 親子の変化|”子どもが言葉にするようになった”

はじめは、お母さんが不安を先回りしてしまう様子がありました。「今日は大丈夫かな」「嫌じゃない?」といった声かけが、かえって子どもの不安を増幅させてしまうこともありました。
しかし支援を通じて、子どもが「今日はここまでならできそう」など、自分で言えるようになっていきました。お母さんも「全部見守らなくても大丈夫」という安心感が出てきて、「不安なときは、どうすれば乗り越えられるか」を一緒に考える流れができました。
親が手を引くタイミングを学ぶと、子どもも”自分で考える習慣”を育て始める。
その連鎖を感じた瞬間がいくつもありました。子どもが「今日は一人で行ってみようかな」と呟いたとき、お母さんが「そうね、やってみる?」と自然に応えられるようになったのです。
4. 「ひとりで登校できた日」|見守る勇気がもたらした一歩
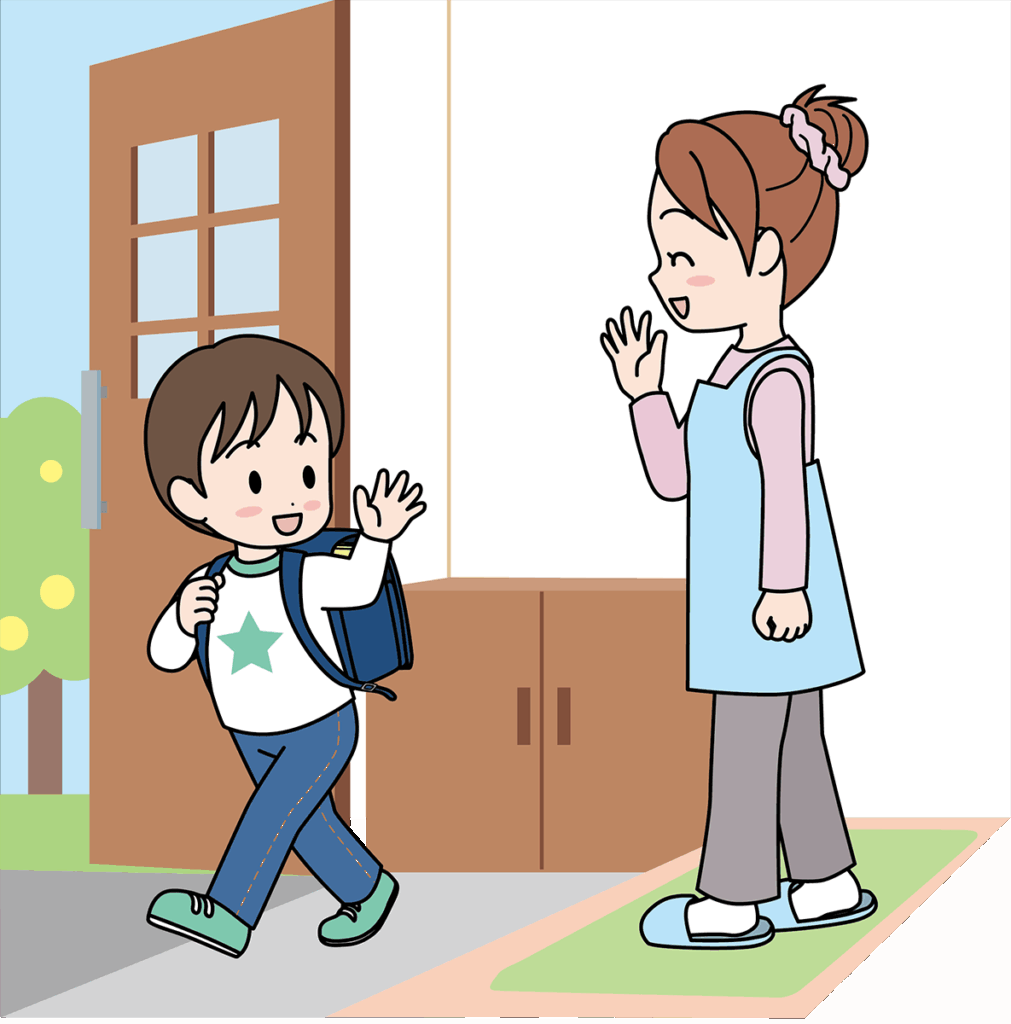
ある日、子どもが「今日は一人で行ってみたい」と話してくれました。お母さんも不安はあったが、「信じて任せる」ことを選びました。
玄関から出る後ろ姿を見送ったときの表情は、私も忘れられません。不安と誇らしさが入り混じった、複雑で美しい表情でした。
その後も波はありました。翌日は「やっぱり一緒に行こう」と言ったり、一人で行けた日でも学校で不安になったり。でも、再び親子で”支え合う形”が変わったのです。
以前は「お母さんがいないとダメ」だったのが、「お母さんがいなくても大丈夫だけど、不安なときは頼ってもいい」という関係性に変化していきました。
5. 支援を通して感じたこと|「離れる」ことは冷たいことではない
この事例は、「学校に行けている=問題ない」という見方がいかに危ういかを教えてくれました。
親子の”依存と自立”のバランスを見つめ直すことが、結果的に子どもの成長を支えるのです。
お母さんが「心から信じて送り出せたことは、私の人生の中でも大きな経験でした」と話されたことが、今でも胸に残っています。
「離れる」ことは決して冷たいことではありません。適切なタイミングで、適切な距離感を保ちながら、子どもの成長を信じて見守ること。それは、親としての最も深い愛情表現の一つなのかもしれません。
また、親子で適切な距離が保たれるようになってからは、親御さん自身も自分のことができる時間を持てるようになりました。母子登校中は常にお子さんと一緒に居なければいけない状況で、常に“お母さんであること”が求められていたのです。子どものことがどれだけ大好きで愛していたとしても、自分のやりたいことがまったくできない状況というのは、精神的にも追い詰められてしまうことはそう珍しくありません。
親子が笑顔で過ごせるために、いい距離感をしっかり保つということも大事だということです。
まとめ|”母子登校”は終わりではなく、プロセスの一部
母子登校は「問題」ではなく、そこからどう成長していくかの”過程”です。
親の支えが必要な時期があっても良い。でも、そこに”出口”をつくることが、子ども自身の未来につながります。
一人ひとりのペースは違います。すぐに変化が見える場合もあれば、時間がかかる場合もあります。でも、親子が同じ方向を向いて、少しずつ歩んでいけば、必ず道は開けます。
今回の事例が、同じように悩む方のヒントになれば嬉しく思います。
「うちも母子登校で悩んでいる…」という方へ
「みちびき」では、付き添い登校・行き渋りなどに悩むご家庭に寄り添った支援を行っています。
▶ お子さんの状況に合わせた具体的な関わり方をご提案します。
▶ まずは公式LINEまたは問い合わせフォームからご相談ください。
一人で抱え込まずに、私たちと一緒に歩んでいきませんか?
お子さんの「自分の足で歩く日」を、一緒に迎えましょう。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














