『勉強しなさい!』は逆効果?|子どものやる気を引き出す“本当の声かけ”とは
- 2025/07/18
- 2025/07/17
多くの親がぶつかる”あのひと言”
「勉強しなさい!」
宿題が山積みになっているのを見つけて、つい口にしてしまうこの言葉。でも、言えば言うほど子どもはやらなくなる。そんな経験はありませんか?
「今やろうと思ってたのに…」と言い返されて、親子でイライラが募る。そして結局、勉強は進まないまま時間だけが過ぎていく。
もしかすると今日も、リビングでゲームをしている我が子を見て「また勉強してない」とため息をついているかもしれません。将来のことを考えると心配になって、どうしても「勉強しなさい」と言ってしまう。そんな親御さんの気持ち、とてもよく分かります。
なぜ子どもは”勉強しなさい”で動かないのか
親として「将来困らないように」「選択肢を広げてあげたい」と思うからこそ、勉強してほしいと願う。その想いは間違いではありません。
しかし「やらされ感」が強くなると、子どもの心には反発・無気力・嫌悪感が生まれてしまうことがあります。「勉強=やらされるもの」という図式が定着してしまうと、本来持っている学習への好奇心や探求心が失われてしまうのです。
実は、人が何かに取り組むときの動機には、心理学的に大きく分けて2つの種類があります。この違いを理解すると、なぜ「勉強しなさい」がうまくいかないのかが見えてきます。
心理学で見る「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」
| 動機の種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 外発的動機づけ | ご褒美や罰など”外からの働きかけ”で動く | テストで100点取ったらゲームできる |
| 内発的動機づけ | 興味・好奇心・達成感など”内側の理由”で動く | 自分で計画を立てて問題を解くのが楽しい |
心理学者デシとライアンの自己決定理論(Self-Determination Theory)によると、内発的動機づけの方が学習の持続性・定着率が高いという研究報告があります(Ryan & Deci, 2000)。
つまり、外から「やりなさい」と言われて動くよりも、自分の内側から「やってみたい」と思えるようになった方が、長続きし、より深い学習につながるということです。
「勉強しなさい」は外発的動機づけの典型例。一時的には効果があるかもしれませんが、根本的な学習習慣の定着にはつながりにくいのです。
「勉強しなさい」を手放した家庭の変化
実際に声かけを変えた家庭では、どのような変化があったのでしょうか。
Aさん(小5男児の母)の場合

以前は毎日のように「勉強しなさい」と言っていたAさん。
しかし、ある日子どもが「漢字テストが全然覚えられない…」とぽつりとつぶやいたことをきっかけに、無理にやらせようとするのではなく、子どもの不安を一緒に整理することを意識するようになったそうです。
「どこが難しかった?」「覚えるとき、どんなやり方をしてるの?」と問いかけながら、子ども自身が工夫や対策を考えるようにサポート。
すると徐々に、「こうしたら覚えやすいかも」と自分から勉強法を試す姿勢が見られるようになりました。
「お母さんに言うと、自分の中も整理される」と、本人が話してくれたそうです。
親が“指示役”から“対話の相手”に変わったことで、勉強=自分ごととして捉える力が育ちはじめた事例です。
Bさん(中1女子の父)の場合

以前は「ちゃんとやったの?」「今日はどこやるの?」と声をかけるたびに、子どもが不機嫌になり、親子関係にもストレスがありました。
そこでBさんは、「問題集のどこをやるかは任せるね」「やりにくいところがあれば、声かけて」と、子どもに一歩任せるスタンスに切り替えました。
それ以降、子どもは自分でスケジュールを決めて進めるようになり、「これは今日やる」「この範囲は明日に回す」と、計画性と自己管理力が少しずつ育ってきたそうです。
Bさんは「気になることがあっても、本人から話してくるまでは口を出さないようにした」と話します。
すると逆に、「ここ、ちょっとわかんない」と自分から質問してくるようにもなったとか。
“管理”から“信頼”へ。
親の関わり方をほんの少し変えただけで、子どもが「勉強を自分ごととして捉える」姿勢に変わっていった一例です。
親が今日からできる、やる気を育てる声かけ&関わり方
①「指示」ではなく「問いかけ」に変える
✖「早くやりなさい」
↓
✔「今日はどこから始める?」
問いかけることで、子どもが自分で考え、決断する機会を作ります。自分で決めたことには責任を持ちやすく、継続もしやすくなります。
②勉強内容ではなく、プロセスや姿勢を褒める
✔「自分で始めたんだね」
✔「最後まで集中してたね」
✔「分からないところを質問できたね」
結果だけでなく、取り組む姿勢や過程を認めることで、子どもは「頑張ること自体」に価値を見出すようになります。
③「やらなきゃ」ではなく「やってみたい」を引き出す環境を整える
- 子どもの興味を尊重した教材選び
好きなキャラクターが出てくる問題集、興味のある分野から始められる参考書など - 達成感を味わえるミニゴールの設計
「今日は2ページ」「この単元が終わったら休憩」など、小さな目標を設定して達成感を積み重ねる
親の「願い」を”伝わるかたち”に変えるために
親の想いはきっと子どもに届きます。「将来のために勉強してほしい」「可能性を広げてあげたい」という愛情に満ちた願いは、決して間違いではありません。
でも、言い方とタイミングを少し変えるだけで、子どもの内側が動き出すのです。
「勉強しなさい」を手放す勇気が、子どもの”やりたい”を引き出す第一歩になります。
明日から、いえ、今日から試してみませんか?
きっと、親子の関係にも、子どもの学習への姿勢にも、温かい変化が訪れることでしょう。
さらに深く知りたい方へ
お子さんの学習習慣づくりや親子のコミュニケーションについて、より具体的なアドバイスやサポートが必要な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
HPの問い合わせフォームまたは公式LINEからご連絡いただければ、お一人お一人の状況に合わせたアドバイスをさせていただきます。
一緒に、お子さんの「やりたい」を引き出す方法を見つけていきましょう。
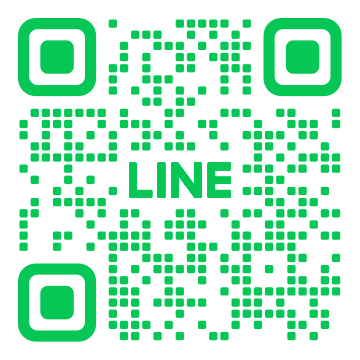
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














