『それ貸して』より『何分後に貸して?』の方が伝わりやすい、と思うよ。
介入しない勇気|兄弟(姉妹)喧嘩とのつき合い方—親の最小介入ポイント
- 2025/09/19
- 2025/09/12
最近、朝夕の小競り合いが増えたと感じたら、それは季節のせいかもしれません。今は「教える」より「見届ける」に舵を切る時期です。

9月終盤、ケンカが増えやすい理由
夏休み明けの”頑張り疲れ”と残暑、さらに行事ラッシュが重なるこの時期。子どもたちの心と体には思っている以上に負荷がかかっています。また、疲れているということを子ども自身が気づいていないことも少なくありません。
親の干渉が増えるほど、子どもたちの発散は力の弱い相手へと向きやすくなります。実は兄弟喧嘩は、主張・交渉・妥協・修復の練習の場。親が裁定しすぎるほど、子どもたちの学びが減ってしまうのです。
親の役割は「見届ける」+「安全の境界だけ」
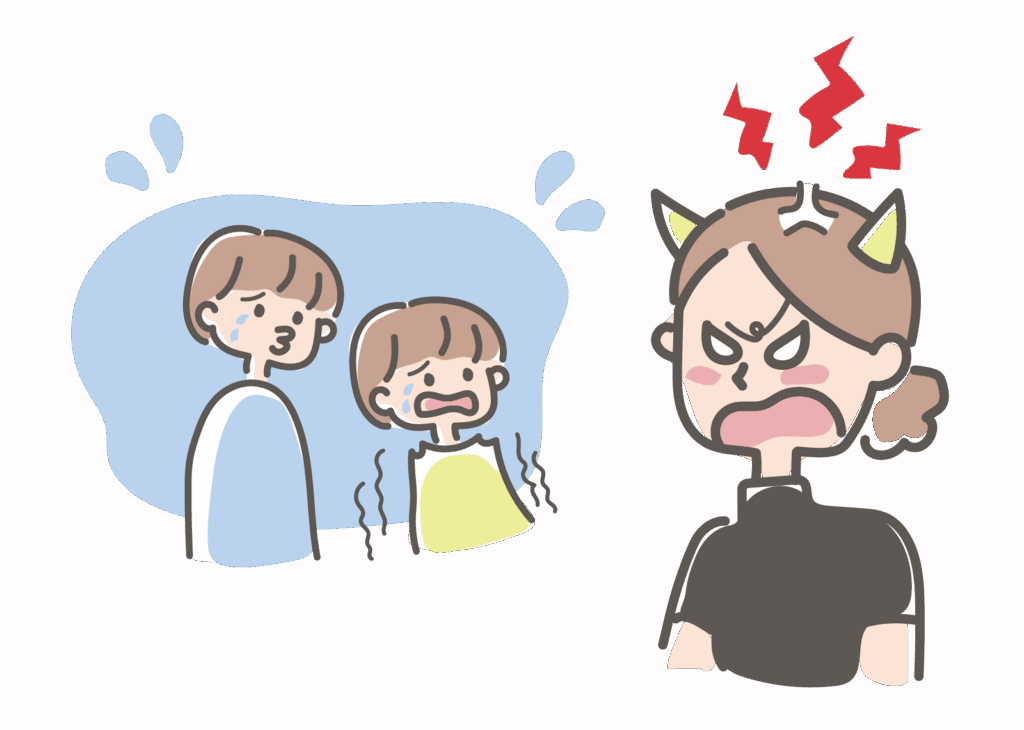
やらないこと
- 犯人捜し
- 説教
- 指示や提案
- 細かなルール作り
ここに挙げた内容は、実は多くのご家庭で行われています。気持ちは分かるのですが、これらを日常的にしていると子どもは「親が何とかしてくれる」と捉えるようになり、子ども達同士で解決することをすぐに諦めてしまう傾向が強くなります。
やること
けが・破損・夜間騒音など安全境界だけを告げるようにしましょう。経緯の聴取は不要でしょう。事の経緯を聞いてしまうとどうしてもどちらが悪いという判断に迫られることも多くなります。あえて経緯などは聞かず、課題は当人同士に返しましょう。
一言の例
「手をあげるのはお母さん悲しいわ。」
「2人の声が大きくてテレビの音が聞こえないから別の場所に行くわ。」
介入しないためにできること
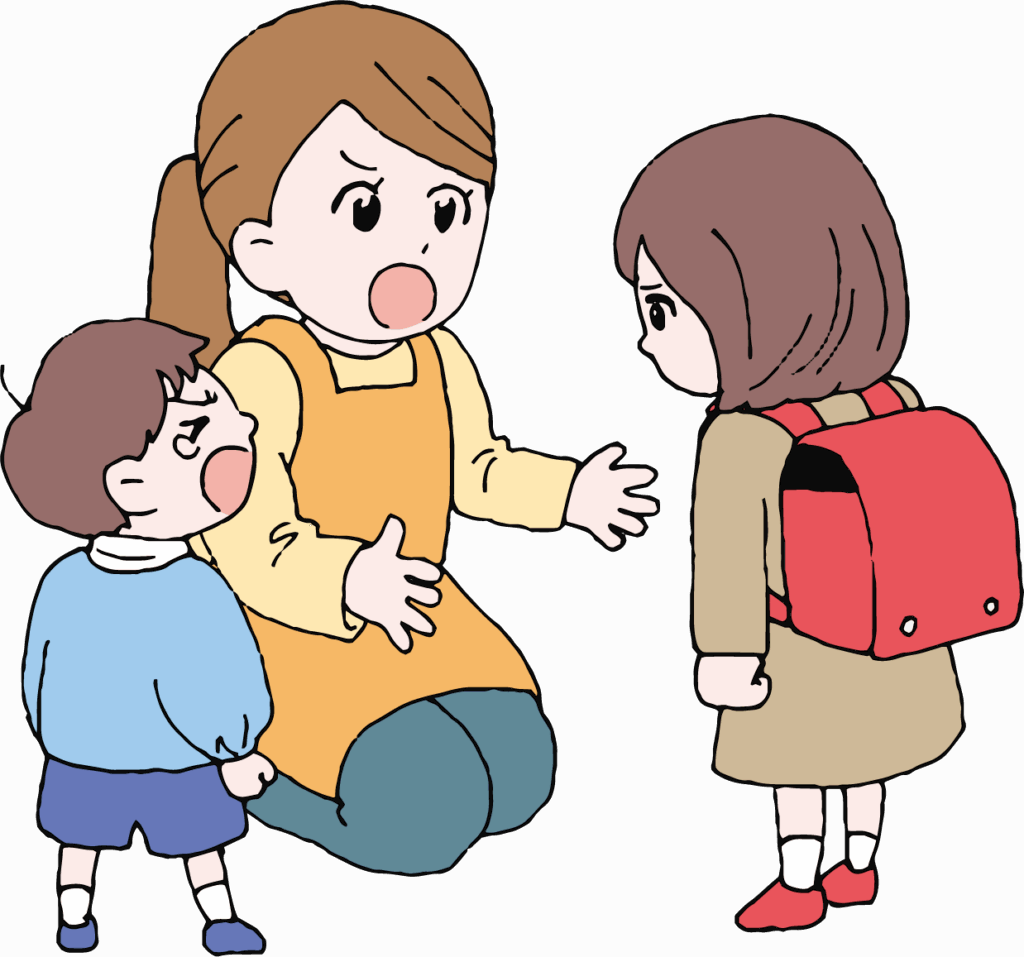
子どもが訴えてきたら
「お母さんに言われても困るな。」
とその場で親御さんが解決しない対応が望ましいでしょう。判断も解決も預けて、親は静かに退きます。
ケンカ後、子どもが話してきたら
親の意見を伝えるよりも、まずは子ども達の気持ちを受け止めることが大切です。
「そう感じたんだね」
「そこで止められなかったんだね」
求められるまで解決案は出しません。解決案を出す場合も、子どもの年齢や成長度合いによりますが、すぐに答えを提示した方がいい場合もあれば、ヒントを与えるだけに留めておく場合もあります。常に親が答えを提示しなければいけないわけではありませんので、ヒントを与えて子ども達が答えに辿り着けるのであればそっちの方が気づきも多いでしょう。
年齢別の最小フォロー
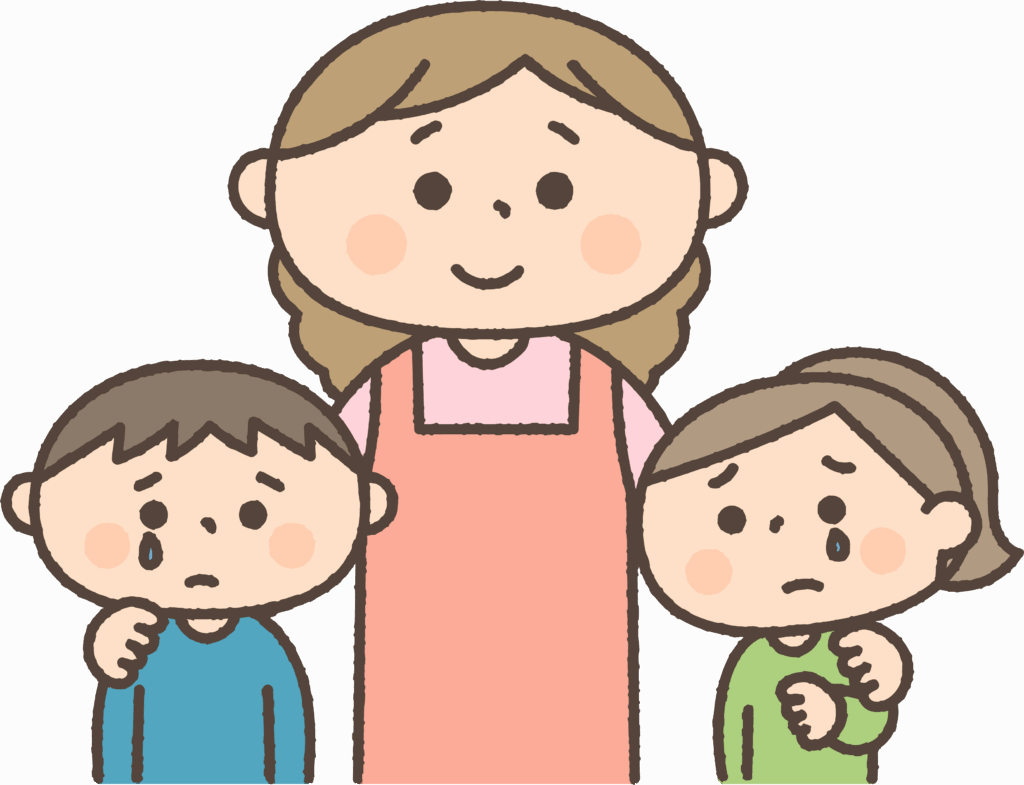
未就学児
共感ことば+短い選択肢(交換/順番)を提示。
自分の気持ちを言葉にすること自体がまだ未熟な年齢です。特に相手に自分の気持ちを受け止めてもらえなかったというショックが残っていることが多いですので、まずはそれを親御さんが受け止めてあげましょう。その上で選択肢を提示してあげることで解決に導いてあげることができるでしょう。
取り合いになったときの例
- 「それ、好きなんだね。——交換にする? それとも順番にする?」
- 「今すぐ使いたかったんだね。じゃあ、あと3回で交代にする?別のおもちゃと交換にする?」
- 「大事にしてたんだね。“終わったら貸して?”って聞く?それとも“これと交換しよ?”にする?」
順番待ちが必要なとき(ブランコ・おもちゃ・テレビ等)
- 「早くやりたい気持ちわかるよ。“3分のタイミングで交代”にする?“あと◯回で交代”にする?」
- 「やりたいね。“つぎ○○がやるね”って言う?それとも“あと1曲で交代ね”にする?」
- 「待つのたいへんだね。“となりで見てる→つぎ○○にする?”“先にジュース→戻って交代”にする?」
小学生
“伝わり方”の助言を親の意見として伝える。
まだまだ相手の立場に立って物事を考えるということが苦手な時期です。主観でしか物事を見ていない場合は、親の意見として伝えることで子どもに気づきを与えることができます。

親御さん
中学生
“見え方(印象)”を共有する。
感情優位で発言してしまうことは多い年齢です。客観的なものの味方というのはまだ苦手であることが多いですから、それを教えてあげることで子ども自身に次からどうするのかを考える余地を与えてあげましょう。

親御さん
理由がどうであれ、手を出す場面を切り取られると”手を出した人が悪い”と見られやすいよ。それはあなたの損になりやすいよ。
よくある誤解の整理
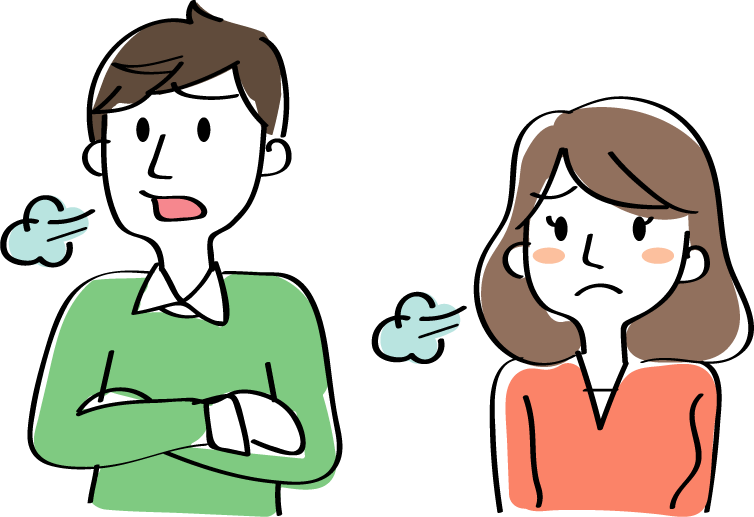
✅見守り=放置ではない:安全線は大人が守ります。
子どもが目の前で喧嘩しているのに、止めないのは親として役目を果たしていないのではないですか?などとご質問を受けることもあります。
しかし、私たちが「見守りましょう」と伝えているのは、何も「放置しましょう」という話ではありません。むしろ子ども達が危険な状況になる場合(けがをしそうな状況)は、親御さんがストッパーとなっていただく必要があると考えます。
✅公平より中立:肩を持たず、課題は当人へ返します。
一番やりがちな親御さんの対応として、どちらかの方を持ってしまうということが挙げられます。どちらかの肩を持ってしまうと、持たれなかった方が不満を抱えるようになり更に兄弟喧嘩が加速することもあります。
“喧嘩両成敗”という言葉があるように、注意する場合は両者に伝えるようにしたいです。
✅ “ルールがないと動けない子”にしない:ルール化より考える機会を残します。
喧嘩が増えてしまうと親御さんから「そんなんだったらルールにするよ!」と言ってしまう方も少なくありません。しかし、ルールを安易にせってしてしまうと家庭が窮屈に感じてしまうこともあります。何より、ルールがないと解決できないという子には育ってほしくありませんから、ルールを作成するのは最終手段ぐらいに捉えて解決策を模索する流れにしていけると、子どもの思考力も伸ばすことができるでしょう。
環境の微調整(ルール化しない”整え”)

時間帯への配慮
荒れやすい時間帯(夕方〜就寝前)は親御さんからの関与を薄くします。特に学校から帰ってきてからの子どもの様子を見て、機嫌が悪そうな場合はそっとしておくのが得策だと思われます。落ち着いてから子どもが話してくるようであれば、しっかり聴いてあげましょう。
取り合いが多い物への対応
親が先回りで買い足しするのは避けましょう。子どもから何も言われていないのに親御さんが動いてしまうという状況は、「親が解決してくれる」と子ども達が勘違いしてしまうでしょう。まずは相談して使い分ける練習をさせましょう。買うなら子ども側からの要望が出てから検討します。
近所配慮は”環境操作”から
窓を閉める、別室へ移る、時間帯をずらすなどでまずは対応しておきましょう。それでも子ども達の音量が変わらないのであれば、アイメッセージなどで困るということを伝えていきたいですね。
例外(早めの介入・相談が必要)
以下の場合は早めの介入や専門家への相談を検討しましょう:
- 繰り返す負傷
- 恐怖表情
- 著しい力の偏り
- 破壊行為
これまでの親子関係によっては、すでに親御さんが手を付けられない状態に陥っているご家庭もあるかもしれません。そういう場合は、上記の対応では解決できませんから専門家に相談し適切な対応をしていきましょう。家庭内のことではありますが、第三者を頼ることは決して恥じることではありません。
まとめ
兄弟喧嘩は子どもたちにとって大切な練習の場です。親の役割は見届け人と境界の管理者。ルールより余白を大切にし、子ども自身が考え、やり直す力を育てていきましょう。
家庭ごとの言い回しを整えたい方は、個別相談をご利用ください。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














