うちの子、全然勉強しないんです・・・。
「勉強しなさい」はもう古い!子どもが自ら学びたくなる環境づくりのススメ
- 2025/09/12
- 2025/09/17


親御さん
こんなお悩みを持つ親御さんは多いのではないでしょうか。ついつい「勉強しなさい!」と声をかけてしまう気持ち、とてもよくわかります。
でも、実はその声かけが逆効果になっているかもしれません。
今日は、支援現場で9年以上の経験を積む中で見えてきた「子どもが自ら勉強したくなる環境づくり」について、科学的根拠とともにお話しします。
「勉強は大切」だからこそ見直したい親の関わり方

SNS上で「勉強は絶対した方がいい。知識が少ないと狭い世界でしか物事を判断できない。」こんな発信を目にしました。——これは確かにその通りです。学びを通じて広い視野を持ち、柔軟に考えられる力は、これからの時代に欠かせません。
しかし、だからといって親が「勉強しなさい」と繰り返すことは、かえって子どものやる気を削ぐ原因になってしまいます。
私自身、支援者として9年以上の現場経験の中で、一度も親御さんに「子どもに勉強するよう声をかけてください」と伝えたことはありません。むしろ「無駄に声をかけないでください」とお伝えしてきました。
学術的に裏づけられた「内発的動機づけ」の重要性
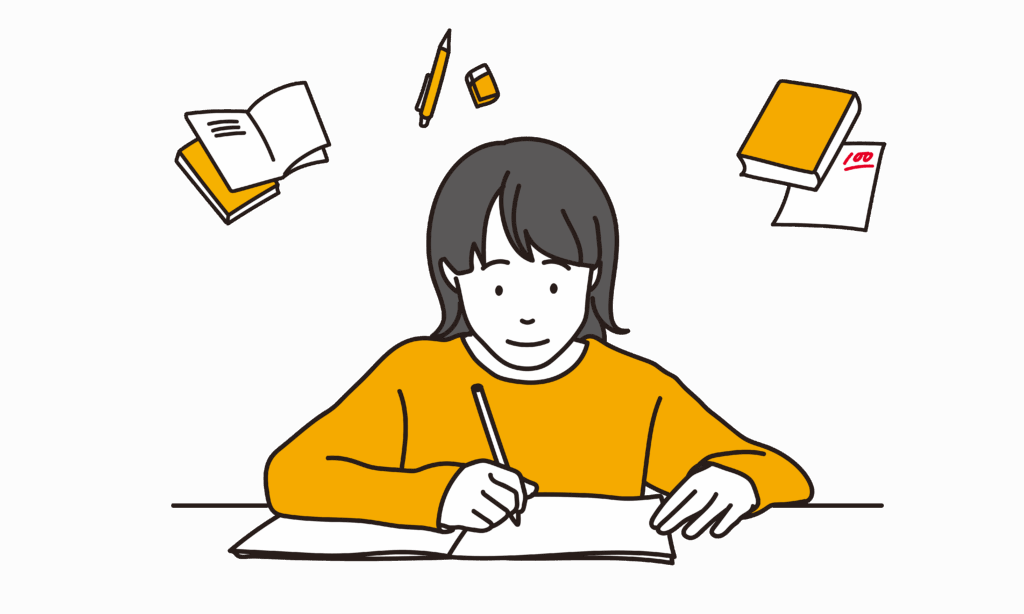
では、なぜ「勉強しなさい」が逆効果なのでしょうか。その答えは心理学の研究にあります。
自己決定理論(Deci & Ryan, 1985)によると、人は「自分で選んでいる」と感じられるときに最も意欲が高まるとされています。
つまり:
・外発的動機づけ(親から「やりなさい」と言われてやる)→ 短期的効果はあるが長続きしない
・内発的動機づけ(自分が「やりたい」と思ってやる)→ 長期的に学ぶ意欲と探究心が育つ
子どもに本当の学ぶ力をつけてもらうためには、一時的な強制ではなく、持続可能な学習意欲を育むことが重要なのです。勉強させようと躍起になり過ぎて、長続きしない方法になってしまっていませんか?
現場で起きている変化
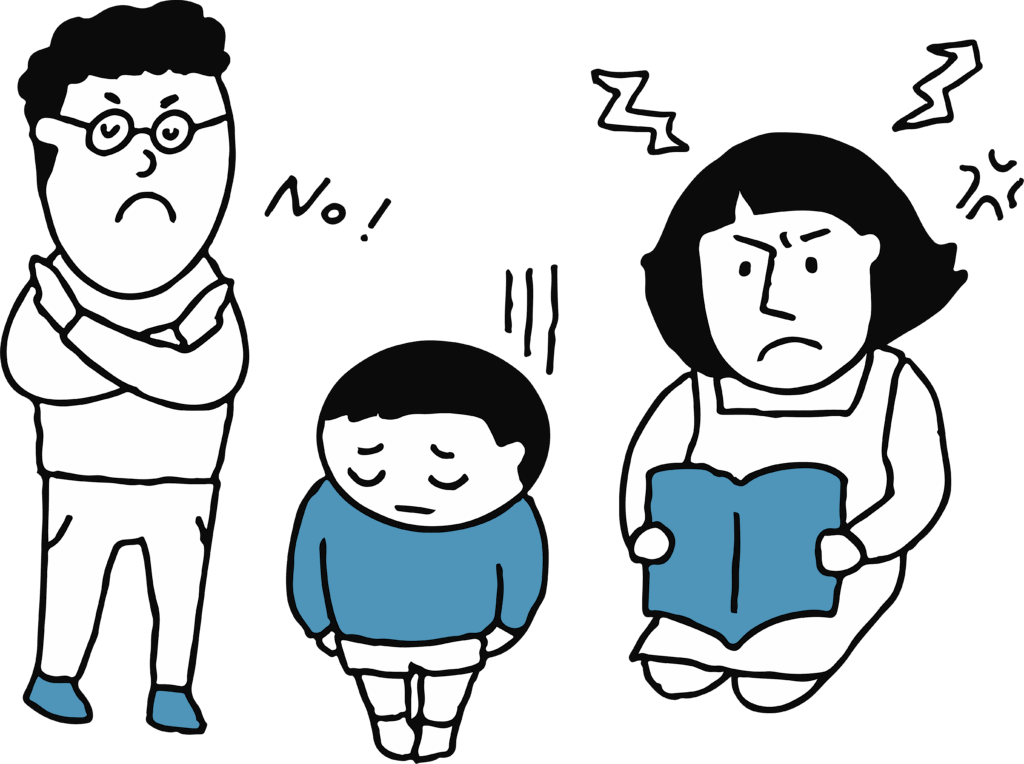
私は支援者として、一度も親御さんに「子どもに勉強するよう声をかけてください」とお伝えしたことはありません。むしろ「不要に声をかけないでください」とお伝えしてきました。
すると、どんな変化が起きたでしょうか?
支援前は「勉強しないんです😢」と相談されるご家庭でも、「親は勉強しろと言わない」対応に変えていただくと:
- 子どもが少しずつ机に向かうようになる
- 時間が経つと「勉強しないんです」という相談自体がなくなる
- 親子関係も改善される
これは「強制から自主性へ」のシフトが起きた証拠です。勉強の大切さを知るからこそ親は子どもに干渉をするわけですが、焦り過ぎて親の気持ちを押し付けないようにしたいものです。
「嫌い」にさせないことが最重要
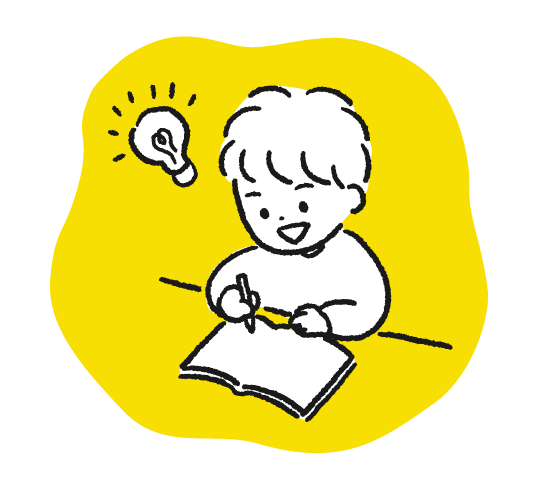
教育心理学の研究では、興味深い事実が明らかになっています:
一度「嫌い」と感じた対象を再び好きになるには、多くの労力を要する
つまり:
🔴嫌いになるのは一瞬
🔴好きになるのは時間がかかる
だからこそ、子どものやる気を削ぐ言葉かけや強制は絶対に避けなければなりません。「勉強嫌い」にさせないことが、親にできる最大の支援なのです。子どもの「好き」や「興味」を思う存分伸ばしてあげてください。そして「好き」の範囲が増えてくると自ずと子どもの世界も増えていくでしょう。子どもが見る世界が豊かになるよう、子どもの「好き」を広げるサポートをしてあげたいですね。
勉強に向かう力を支える「非認知能力」
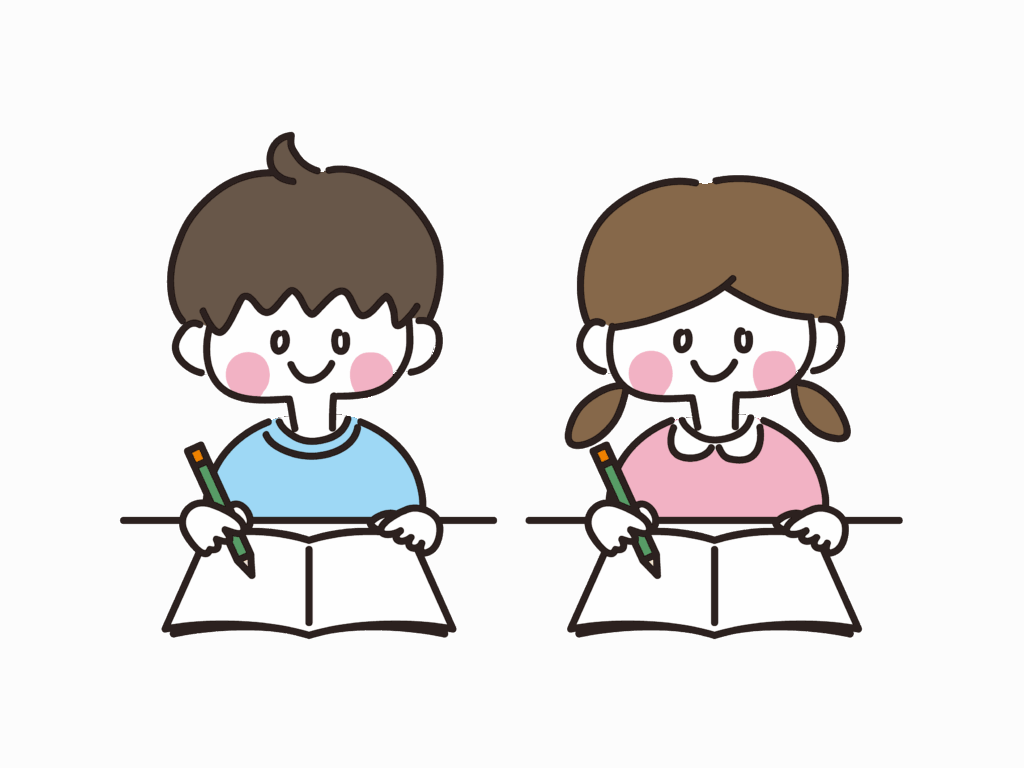
「勉強しなさい」と繰り返すのではなく、子どもが勉強に向かうために本当に必要なのは非認知能力です。
3つの非認知能力
1. 自分を高める力
🔵努力を続ける力
🔵成長マインドセット
続けるコツは「気合い」ではなく“仕組み化”。勉強に対して苦手意識を持ってしまっているお子さんは、始めるまでのハードルが一番高いことが多いです。無理に勉強に対するハードルを上げるのではなく、子どもが「やってみようかな」と思えるレベルまでハードルを下げ、毎日同じタイミング・同じ場所で“短く着手”できる環境を作ると、勉強に向かうまでの迷いが減ります。
できる・できないではなく、「どうすれば一歩前進できるか」に視点を置く考え方。失敗は“情報”として扱い、試した方法や工夫を言語化すると次の一手が見えます。親であれば子どもに“できて欲しい”と思う気持ちから間違いばかり指摘してしまうこともあるでしょう。それでは子ども側のやる気はどんどん削がれてしまいます。伝え方を意識しつつ、次につながる方法を目指していきましょう!
2. 自分と向き合う力
🔵感情をコントロールする力
🔵自己理解
「やる気が出ない」は甘えだけではありません。未整理の感情や体の状態のサインを示していることも。大人でもやる気が出ない時はありますから、気持ちには受け止めてあげましょう。その上で感情を整えるルーティン(深呼吸・温かい飲み物・短いストレッチ)をセットにすると学びのスイッチが入りやすくなります。ルーティンに関しては、親子で相談して決めていけるといいですね。
「自分はどの時間・科目・方法だと進みやすいか」を知ることが遠回りに見えて最短ルートとなるでしょう。得意な入り口(音読/書く/見る)や、集中が切れる前の“限界時間”を一緒に見つけておくと、無理なく続くでしょう。
3. 他者とつながる力
🔵周囲から学ぶ力
🔵協力す頼る
上手な人のやり方をまねることは、学びを深める近道です。とくに「観察 → 模倣 → 自分用に調整」の3ステップで回すと効果的。教科書の解法だけでなく、友だちや動画の進め方(手順・時間配分・道具の使い方)も学習資源として取り入れると、理解も手数も一気に増えます。子どもがうまくいかないと投げているときは、一人の人生の先輩として人を頼る大切さを伝えてみるのもよいでしょう。
また、「助けを求める/役割を分ける/確認し合う」といった関わりがあると、学びは続きやすくなります。家族の“学ぶ時間”をそろえるだけでも孤独感が減り、手が止まりにくくなります。(例:子ども=読み上げ、親=メモやタイムキーパー)
勉強したくなる背景にあるもの
子どもが勉強を「やりたい」と思える背景には、以下の要素が不可欠です:
- 自己決定感:自分で目標を立てられる
- レジリエンス:つまずいても立ち直れる
- 安心感:親に見守られている実感
これらはすべて非認知能力の育成によって支えられています。
子どもが「勉強したい」と感じる土台は、自己決定感・レジリエンス・安心感の三つです。自分で選べる体験が増えるほど自己決定感が育ち、「うまくいかなかった」を次の作戦に変えられるほどレジリエンスが鍛えられ、否定されず見守られる関係があるほど安心感が広がって挑戦回数が増えます。
これはそのまま、みちびきの非認知能力の三分類――自分を高める力(自己決定)/自分と向き合う力(回復と調整)/他者とつながる力(安全基地)――の実践でもあります。
親にできる最も大切なこと
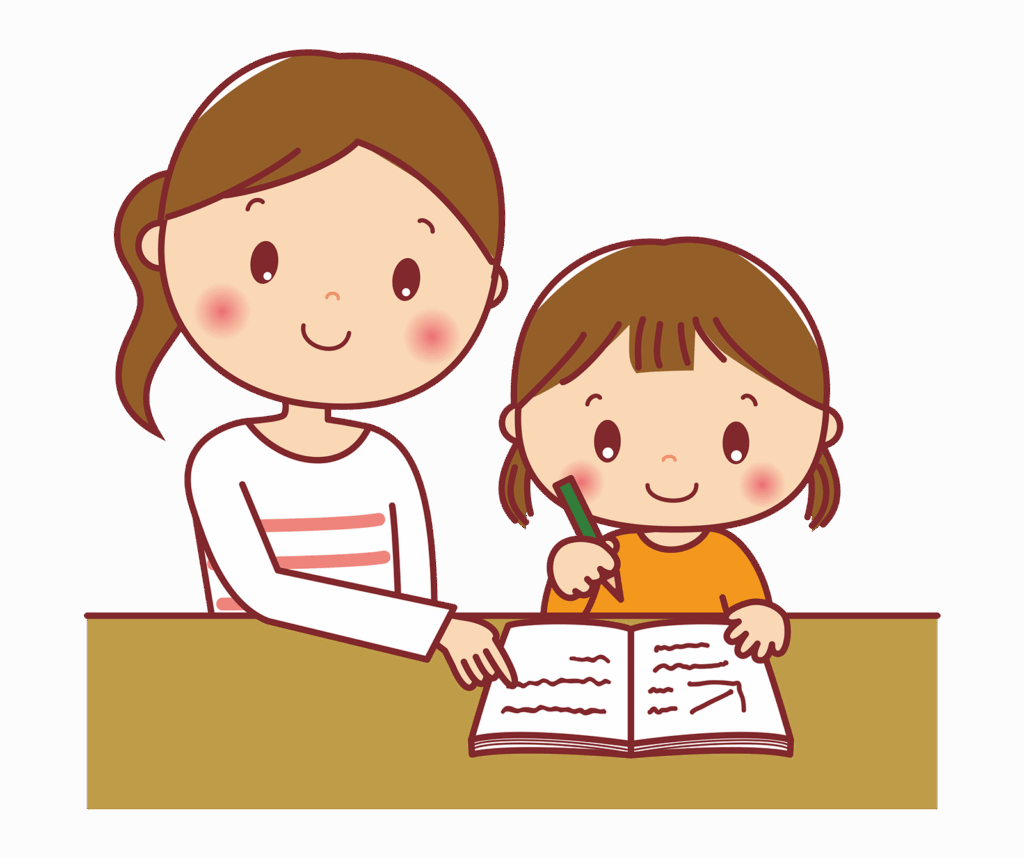
では、具体的に親は何をすればいいのでしょうか?
答えは意外にシンプルです。
✅ やるべきこと
- 子どもが興味を持った瞬間にそっとサポートできる環境を整える
- 子どもが自ら勉強したくなる小さな仕掛けを添える
- 見守る姿勢を保つ
❌ やらない方がいいこと
- 「勉強しなさい」と命令する
- 勉強を強制する
- 子どもの興味を無視する
それだけで充分なのです。
「非認知能力を伸ばす」と言われると何か特別なことをしないといけないんじゃないかしらと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはないのです。日常生活の中で十分伸ばしていくことができます。
実践のポイント:「環境づくり」の具体例
物理的環境
- 学習しやすいスペースを確保
- 興味を引く本や教材を手の届く場所に
- 集中できる時間帯を見つける
心理的環境
- 子どもの小さな成長を認める
- 失敗を責めずに一緒に考える
- 子どもの「なぜ?」を大切にする
関係性の環境
- 親自身も学ぶ姿勢を見せる
- 子どもとの対話時間を大切にする
- 信頼関係を基盤とした見守り
まとめ:新しい教育観への転換
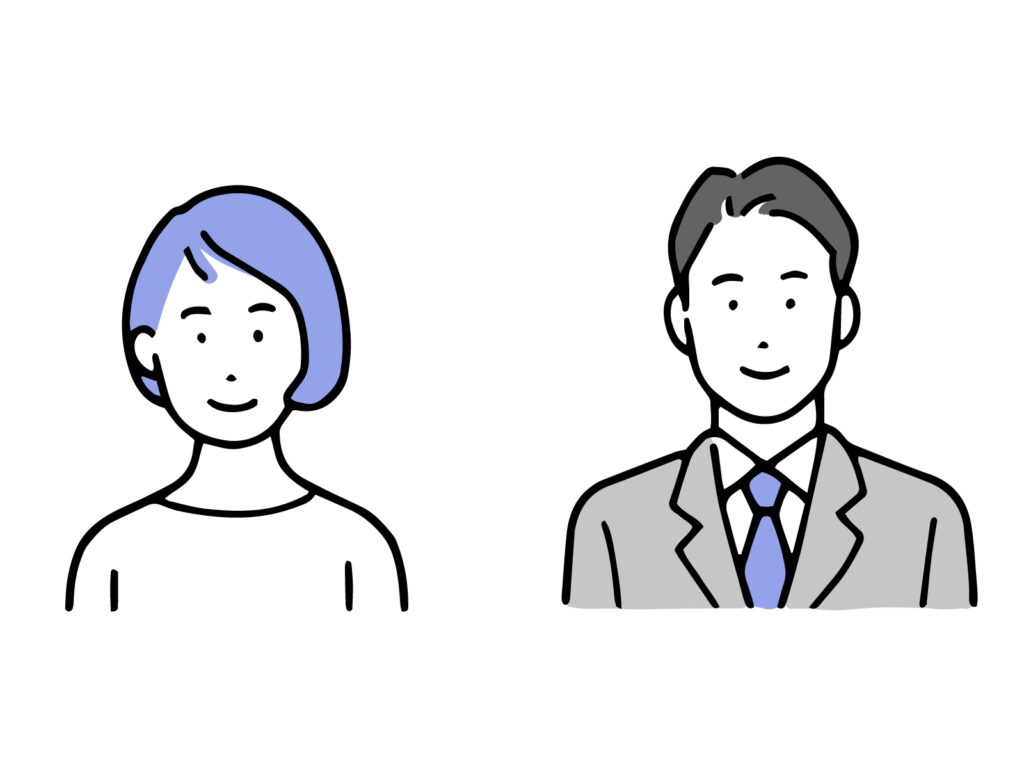
現代の教育で大切なのは:
- ❌「勉強させる」発想から
- ⭕「勉強したくなる」環境づくりへ
この転換です。
4つのキーポイント
- 「勉強しなさい」は逆効果
- 内発的動機づけを支える環境づくりが大切
- 「嫌い」にさせないことが最大の支援
- 非認知能力の育成が学ぶ力を根本から支える
知識を押し込むのではなく、子どもが自ら学びたいと思える土台づくり。これこそが、これからの時代に求められる教育支援の姿です。
「勉強させる」のではなく、「勉強したくなる」環境を一緒につくっていきませんか?
この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。子育てに正解はありませんが、科学的根拠に基づいたアプローチで、親子ともに笑顔になれる学習環境をつくっていきましょう。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














