🧒「ぐずってるのに、なにも言わない…」年中・年長のぐずりの解説と対策
- 2025/08/08
- 2025/08/15
4歳ごろの”ことばにならないモヤモヤ”にどう向き合えばいい?
「ぐずってるのに黙ってる」場面、ありませんか?
4歳前後のお子さんに、こんな様子が見られることはありませんか?
- ぐずっているのに、「あーうー」など赤ちゃん語のような声しか出さない
- 「どうしたの?」と聞いても黙って目をそらす or 見つめてくるだけ
- 「言ってくれないと分からないよ」と伝えても、ますます硬直してしまう…
言葉が育ってきたと思っていたのに、急に赤ちゃん返りのような反応をされると、戸惑ってしまう方も多いと思います。
親御さん側もまだ余裕がある時は、「待つ」姿勢を保てることもありますが、日々の忙しさや疲れが溜まっている時は堪忍袋の緒が切れることもありますよね・・・。
子どもの中で起きていること
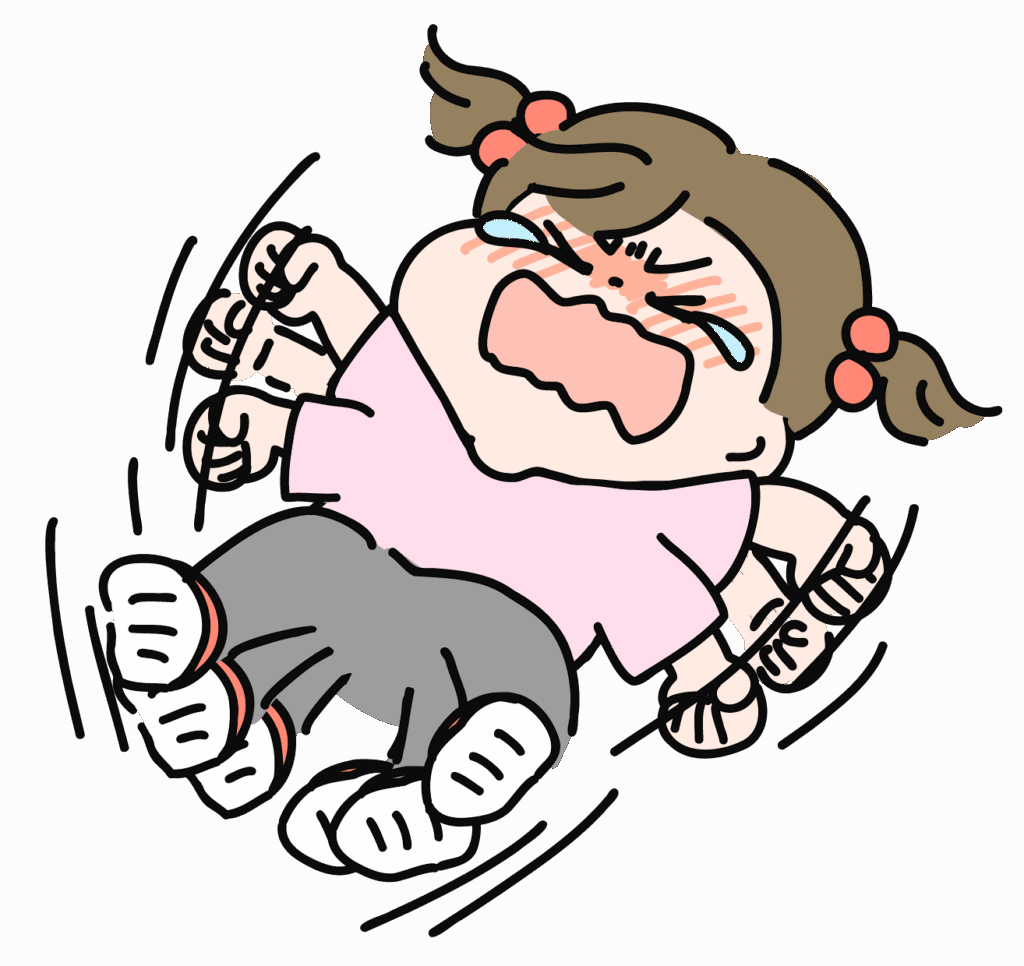
このような「ことばにならないぐずり」は、感情の処理・表現の未熟さから起きていることが多いです。
1. 感情が大きすぎて処理しきれない
幼児期の脳は、特に扁桃体(感情)>前頭前野(思考・制御)という状態。感じたことをすぐに言語化するのは、まだ難しいのが自然です。
2. 「うまく言えない」ことへの恥ずかしさや怖さ
自己主張と羞恥心の間で葛藤し、「うまく言えないなら言わない」が防衛反応として現れることも。
3. 「言っても分かってもらえないかも…」という不安
過去の体験から「どうせ分かってもらえない」という学習(学習性無力感)が入っている場合、沈黙で自分を守ろうとする子もいます。
🔍 発達心理学では、自己主張(assertiveness)や自己表現(self-expression)の発達は、5歳以降まで時間をかけて育つとされており、4歳ごろはまだ不安定な時期です。
逆効果になりやすい声かけ
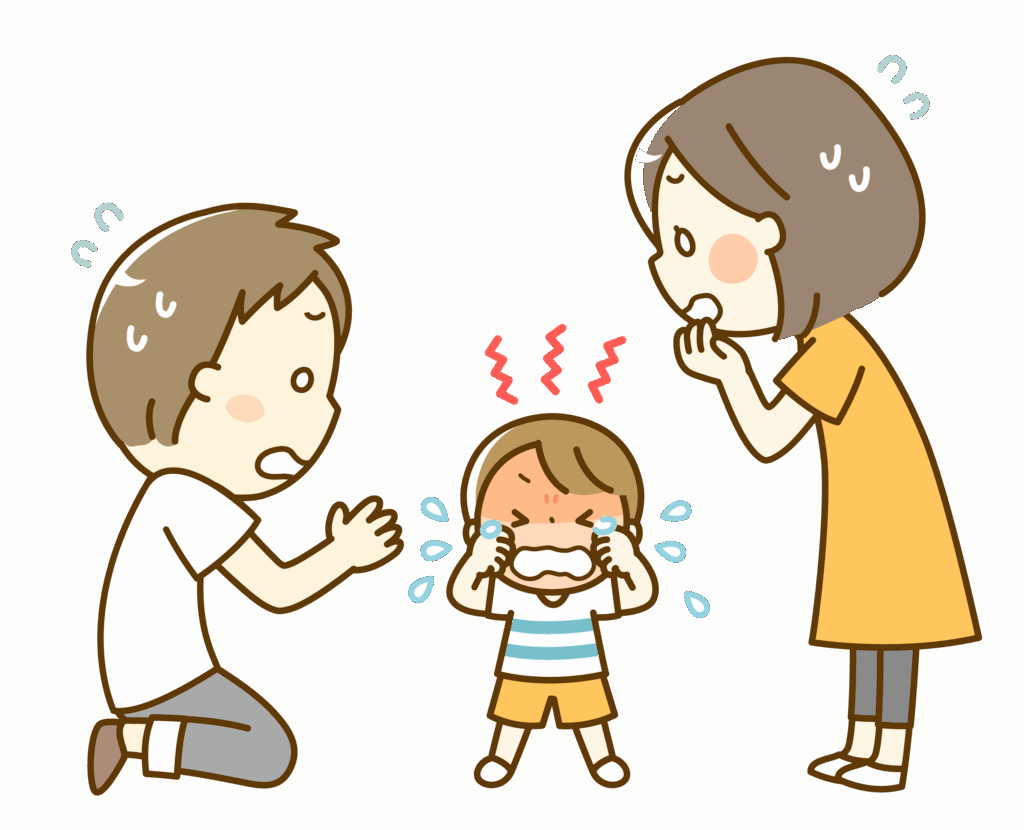
親としてよかれと思って言ってしまいがちな言葉が、子どもにとってプレッシャーになることも。
❌「言ってくれないと分からないよ」
→ これは言い方次第ですが、子どもは「言わなきゃダメなんだ」「怒られてる」と感じやすいこともあります。責めるような言い方は避けていきましょう。
❌「赤ちゃんじゃないんだから」
→ 自尊心を傷つける言葉に。かえって幼い反応が強くなることも。否定されたと捉えると、子ども側から強い反発が出やすいです。余計にぐずってしまう・・・ということも多いでしょう。
❌「いい加減にして!」
→ 感情が伝染し、関係がこじれるリスクも。こう言いたくなる親御さんのお気持ちも分かります。しかし、感情を子どもにぶつけても怒りや恐怖で子どもをコントロールするという流れになり易いでしょう。苛立つお気持ちを一旦落ち着かせてから対応していけるといいですね。
安心を伝える声かけ5選
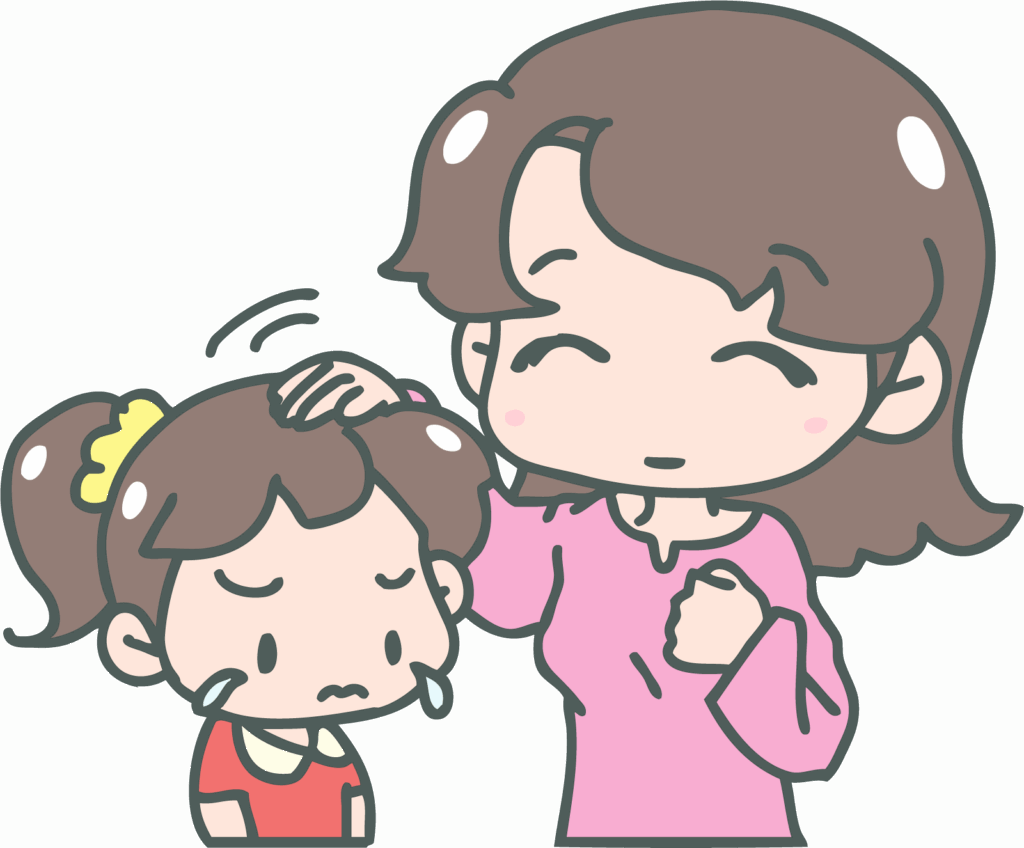
ここでは、心理的安全性を確保しつつ、気持ちの言語化を促す声かけを紹介します。
✅ 1.「うまく言えないくらい、モヤモヤしてるのかもね」
→ 気持ちを代弁することで、「そう、それ!」と内面が整理される
✅ 2.「悲しい?悔しい?それともイヤだった?」
→ 選択肢を与えることで、答えやすくなる(※yes/noで選ばせるのも◎)
✅ 3.「今は話せなくても大丈夫。ママここにいるからね」
→ アタッチメント理論でも重要な「そばにいる安心」を伝える
✅ 4.「あとで絵で描いてくれてもいいよ」
→ 言語以外の手段で自己表現を支える。プレイセラピー的アプローチ
✅ 5.「話せるようになったら、教えてくれると嬉しいな」
→ 子ども自身が「話してもいい」と思えるタイミングを尊重する
ことばにできない=ダメじゃない

「言葉が出ない」という状態は、決して悪いことではありません。
むしろ、
- 自分の感情に気づき、ためて、整理しようとしている証拠
- 感情コントロールや自己認識といった非認知能力の土台が育っている最中です
大人が「答えを引き出す」のではなく、「安心して表現できる環境」を整えることで、子どもは少しずつ”伝える力”を身につけていきます。
🌱まとめ
| NGな声かけ | OKな声かけ |
|---|---|
| 「言わないと分からないよ」 | 「うまく言えなくてモヤモヤしてるのかもね」 |
| 「赤ちゃんじゃないでしょ」 | 「今は言えなくても大丈夫だよ」 |
| 「早く言って」 | 「あとで教えてくれても嬉しいな」 |
📩「どう関わったらいいか分からない…」そんな時は
毎日お家のこと、お仕事のこと、子ども達のこと・・・と頑張っている親御さん達にとって、子どもの「ことばにならないぐずり」や「表現しきれない気持ち」とどう向き合えばいいのかと悩む親御さんは非常に多いです。
そして多くの親御さんが一人で抱えておられることも少なくありません。
みちびきは、家庭教育と非認知能力の視点から、あなたのご家庭に合わせたサポートをしています。
「うちの子ではどうなんだろう?」と思われる方はお気軽にご相談ください。順にお返事させていただきます。
▶ ご相談・最新情報はHPもしくは公式LINEからどうぞ。
プロフィール


佐藤 博家庭教育コーディネーター/
代表カウンセラー(みちびき)
15年間、不登校や母子登校のご家庭を訪問支援。子どもの「自分で社会とつながる力」を育む土台づくりに尽力。文科省協力者会議委員やいじめ対策委員も歴任。「傾聴で終わらせない、変化につながる関わり」が信念。お子さんへの直接支援に加え、ご家庭の課題を可視化し、親御さんと共に解決するスタイルが特長。家庭教育等の講演・研修も多数。「家庭からはじまる社会的自立支援」を推進します。

鈴木 博美家庭教育コーディネーター/
統括ディレクター(みちびき)
家庭教育アドバイザー・訪問カウンセラーとして9年間、不登校や親子関係に悩むご家庭を支援。2025年、支援10年目を迎えます。全国の家庭への直接支援を通し、親御さんとの対話で子どもの社会的自立をサポート。家庭内の会話や関わり方を可視化し、非認知能力を育む声かけや実践的なアドバイスで親子に伴走。保護者向けセミナーや講演も多数。「支援に迷う方こそ安心して相談できる存在」を目指し、家庭の再構築に丁寧に取り組みます。














